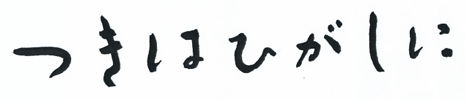
ENOMOTO BASON RYOICHI
俳句エッセイ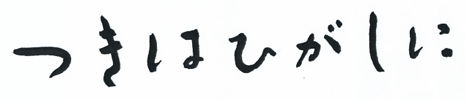 |
|
| 榎本バソン了壱 ENOMOTO BASON RYOICHI |
25 子規逝くや四百頁の大部の中
新聞「日本」の記者として日清戦争に従軍し、遼東半島柳樹屯からの帰途、佐渡国丸船上で子規は喀血した。明治二十八年(一八九五)五月、「十七日 朝大なる鱶の幾尾となく船に沿ふて飛ぶを見る。此時病起れり」と記している。正岡子規二十八歳。この日から、明治三十五年(一九〇二)、「九月十九日(旧暦で八月十七日)午前十二時五十分頃、「八重(子規の母)の、「のぼさん、のぼさん」と呼びかける声に虚子は起こされた。(松山以来旧知の)鷹見夫人も唱和するその声には切迫感がある。律(子規の妹)も病間となりの四畳半から起き出してきた。時々うなっていた子規が、ふと静かになった。鷹見夫人と昔話をしていた八重が手をとってみると、冷たい。呼びかけにも反応しない。顔をやや左に向け、両手を腹にのせて熟眠しているかに見えるが、額は微温をとどめるのみであった。子規の息は、母親の眼を離した隙に絶えていた。」時に子規三十四歳と十一ヵ月、『子規、最後の八年』は、その夜までの八年間の緻密な記述である。 病という闇に火ともす鱶の群れ ずるるはすでにこの本を読了していた。綿密な取材と精緻な記述、さすがノンフィクション・ノベルの雄、関川夏央渾身の傑作である。実に読み応えがあって面白い。正岡子規という人の魅力がじわじわと伝わって来る。不治の病床にありながら、絶倫の文芸活動に挑む凄まじくポジティヴな精神と、その生命力に最後まで心が踊った。しかし、読後の印象で一つだけ気になったことがあった。それでふと、もう一度目を通したくなったのである。それはずるるの高浜虚子に対するイメージが一変したことであった。 『ホトトギス』を子規から受け継ぎ、若き碧悟桐と相克を繰り返しながら、出版を成功させ、俳壇の超大派閥を作り上げる虚子。「『ホトトギス』であらずば俳人であらず」のような強固な地盤を築き、最後には文化勲章までもらった虚子に、なんとない敬遠感を抱いていた。確かに屈指の俳人たちを多く育てた。句作の平均点からいえば、子規より上かもしれない。ましてや碧梧桐の俳句など問題にならない。しかしずるるは、碧梧桐や中村不折の書や、その前衛性に限りない親近感を抱いていた。「俳句がうまいことがなんだ!」が、結局碧梧桐が俳句を止めてしまうのも、虚子に敗北したことからだろう。ただし、荻原井泉水を経て、尾崎放哉、種田山頭火の二人の自由律の俳人が碧梧桐の系から出たことは、俳史の中でどんなに貴重な事実かしれない。 桑原武夫の『第二芸術論』にたいしても、「「第二芸術」といわれて俳人たちは憤慨してるが、自分らが始めたころは世間で俳句を芸術だと思っているものはなかった。せいぜい第二十芸術くらいのところか。十八級特進したんだから結構じゃないか」と嘯く虚子に桑原は「いよいよ不適な人物」と思ったという。まるで俳壇の天皇を気取ったような、俳句を自ら卑下して揺るぎないふてぶてしさではなかろうか。異端分子を粛正するように日野草城らを『ホトトギス』同人から除名した独裁者的な決裁にしても、その後草城の病床を訪ねて円満和解する豪腕さも、丸ビルなんかに『ホトトギス』の発行所を持っていたことも、余計な先入観だが、鎌倉の大仏さまのようなどっぷりとしたその風貌にも、違和感を感じていた。ともかく、虚子は俳壇を大膨張させた貢献と、それによる俳句のホビー的大停滞をひき起こす元凶として、ずるるは虚子が嫌いだった。もっとも、そのホビーの末端で、言葉遊びをしているにすぎない蕎麦屋の店主が、近代の大俳人に腹を立ててもしょうがない事ではあるが。それが、関川のこの本を読んで、若き日の虚子の、子規に対してもゆるぎない主張と自主性を持っていたその生き方に、「あれっ?」と思わす虚子像を目撃した思いがあった。それを確かめようと再度、ずるるはページをくくっていた。 虚子虚像巨像に育つ明治の期 碧梧桐と虚子の最初の確執を思わせる文章がある。「明治二十四年八月、碧梧桐は松山の中学に復学して五年生となり、二十六年九月、三高文科予科に入学した。虚子より一歳上であった碧梧桐だか、このとき虚子の下級生になった。三高正門前の下宿屋で同宿した碧梧桐は、虚子が短い期間のうちに「聖人」を脱し、大言壮語のきみのある文学書生にかわっていることに驚いた。」その四年後、明治二十八年十二月九日の午後、道灌山山頂で、ひそかに自分の後継者たらんことを望んで、学問をしたらどうかと諭す子規に、虚子は長く重たい沈黙のうち「私(あし)は学問をする気はない」と答える。「問いとも叱責ともとれる言葉への回答であった。」「子規は虚子の怠け癖、あるいは悠揚迫らなすぎる日々の態度を飽き足らずに思っていた。勃興する新文学や女性にたやすく心を揺らす虚子を不安に思っていた。」しかし、「虚子は自由人であった。同時に頑固であった。虚子は明治二十年代末の知識青年としてはめずらしく西洋的思想に強い憧れの念をもたなかった。」「虚子は、その沈黙のうちに、子規の深い失望と憔悴を読みとった。」虚子はいった。「升(のぼ)さんの好意に背くことは忍びん事であるけれども、自分の性行を曲げることは私には出来ない。つまり升さんの忠告を容れてこれを実行する勇気は私にはないのである。」「虚子はそのあと、子規に見放された心細さを感じながら上野の山をあてどなく歩いた。のみならず、病身の子規を自分の最後のひと言が絶望せしめた、という悔いが残った。しかし虚子は同時に、自分を束縛する巨大なものから解放され、五体が天地といっしょに広がったような気分を味わいもした。複雑な心境であった。」関川の名文のせいかもしれない。しかし、虚子の偽らない、媚びない、愚直な程のストレートな言動は、後の俳句の世界を束ねる駘蕩とも思える性行の一端を読んだように思えた。いずれにしてもその後子規とは瓦解し、『ホトトギス』を結局になうことになるのではあるけれど。 親でも子でもなくそれ以上の冬の空 明治三十一年初夏、虚子は松山の老母の病が重いので、妻子をともなって帰省すると子規にいった。その時は、萬朝報の仕事に就いていた虚子だったが、帰省を手紙で社に連絡しただけだった。「虚子はわからない、と子規は思った。素直なのに強情だ。落着いているように見えて乱暴だ。要するに、萬朝報の仕事におもしろみを見出せなかったのだな。辞めても構わぬというつもりなのだな。」そう思った。子規は近くの仕出し屋から料理をとり、虚子と晩餐をする。一本の酒を添えて自らも盃に半分だけ口にした。 六月三十日、松山から柳原極堂が来て、いよいよ『ホトトギス』の発行が立ち行かなくなり廃刊にしたいと申し出た。子規は『ホトトギス』を東京に移転させて、虚子に受け継いでもらいたいと考えた。虚子に長い手紙を書いた。「飄亭、碧梧桐、露月等には多きを望む事出来ぬ。つまり貴兄(虚子)と小生と二人でやっていかねばならぬ。」ラブコールである。その頃虚子は長兄に三百円の借金を申し出、総合文芸誌発刊の構想を立てていた。子規からの手紙を読んで、虚子は道後温泉に行った。「それは毎夕食後の習慣であった。湯の湧き口から自分のよい分別が流れ出て来るように虚子には思われ、闘志が身の内にみなぎるのを感じた。」翌日手紙を再読して、子規に手紙を書いた。「然り。大兄と両人でやる。大兄が御病気の時は、小生独りでやる。」虚子が上京したのは、八月の下旬に入った頃であった。 湯に沈む体よりあふるる夏闘志 明治三十一年十月十日、東京版『ホトトギス』(第二巻一号)が出た。(第一巻は松山で出したものを総した)「虚子はできあがった雑誌を使いの者に持たせて子規宅に届けさせた。子規は、「雑誌の出来一体わるくない。」「天気はよくなる、雑誌は出来る、快々」としたため返書を使いに託した。薄くはあったが(六十四ページ)、子規の目には満足すべき出来であった。自分のグループの雑誌を持つという宿願を、ついに果たしたのである。」虚子は東京発行の『ホトトギス』を千部刷った。松山での『ホトトギス』は三百部刷っても余った。冒険だったが、自信はあった。ともかくそれくらい売れなければ、話しにならない。「印刷所から虚子の神田錦町の家に運びこまれた雑誌を、本屋がつぎつぎとりにきた。そうこうするうち二時間で千部が品切れとなった。何度目かの追加分をとりにきた本屋の小僧が、いっぱしの商売人らしい口調で、千部再版してもはけますよ、と虚子にいった。」結局、虚子は五百部を再版した。 明治三十二年五月二十二日、虚子は急性大腸カタルで駿河台の山龍堂病院に入院した。『ホトトギス』発行の激務がたたったのだろう。月末に見舞いにきた碧梧桐が言った。「雑誌は休刊にしおるか。其れとも私等(あしら)が手伝ってよければ、手伝って出すことにしようか。」虚子はこたえた。「私は休んでもええと思うのだが、ノボさん(子規)に相談しておくれ。」虚子はむしろ休刊したかった。二、三日後、病院を再訪した碧梧桐は、「私自身でも、何だか遣って見度いような心持もするのだが、お前に異存があれば止めよう。」碧梧桐の口調は率直であった。虚子は、異存があるとはいえなかった。」出来上がった『ホトトギス』を、療養先の伊豆修善寺で見た虚子は、「碧梧桐が自分の色を存分に出している。」と思った。虚子はほどなく『ホトトギス』編集に復帰するが、子規の亡くなる明治三十五年頃は、俳書の刊行に力を入れ、雑誌実務は碧梧桐が担っている。 碧過ぎて虚空に見えし五月空 子規は、「九月十八日は朝から様態がおかしかった。宮本医師を、陸(くが)家の電話を借りて呼んだ。異変を知った羯南(かくなん)がやってきた。午前十時すぎ碧梧桐がきた。子規の様子を見た碧梧桐が律に、虚子を呼んだかと尋ねた。いえ、まだ、と答えた律の声に、子規が、「高浜(虚子)を呼びにおやり」と小さな声でいったので、十一時頃、碧梧桐が再び陸家の電話を借りに行った。」 戻った碧梧桐と律の介添えで、唐紙をつけた画板に辞世の句を書く。「糸瓜咲て痰のつまりし仏かな」。四、五分後、「啖一斗糸瓜の水も間にあはず」、さらに四、五分後、苦しい気息を整えて逆側に、「をととひのへちまの水も取らざりき」と書くと、三たび筆を捨てた。落ちた筆の穂先が、敷布を少し染めた。この間、子規は終始無言であった。「八時前に子規は目覚め、コップ一杯の牛乳をゴム管で吸った。この朝、陸家から届けられたおも湯を、わずかに口にして以来であった。「だれだれが来ておいでるのぞな」と子規が尋ねた。「寒川(鼠骨)さんに清(きよ)さん(虚子)に静さん(碧梧桐の姉)」と律がこたえた。それが、子規の生前に発した最後の言葉となった。子規はそのあと直ちに昏睡に入った。」 子規は深夜に逝った。「虚子は住まいの近い碧梧桐と鼠骨に知らせるべく表へ出た。(略)寝静まった街区に虚子の下駄の音が響く。十七夜の月がものすごいほどに明るい。「子規逝くや十七日の月明に」虚子の口をついて出たのは、この一句であった。」「虚子が子規庵に戻ると、月光におよばぬランプの黄色い光に照らされた三人の女性が、死者のそばに座していた。八重は虚子を見て、鷹見夫人にこういった。「のぼさんは清さんが一番好きであった。清さんには一番お世話になった」それから八重は泣き伏した。隣室の四畳半から、気丈な律の泣き声が聞こえた。彼女はひっそりとそちらに移っていたのである。」 子規逝くや四百頁の大部の中 「うーん、清さんが一番好きであった、か。」陳蕎麦ずるるは、氷が溶けて水っぽくなった焼酎の残りを一気に呑んだ。「十七日の月明り、でもあるまいが」と、ぼそぼそ店を抜け、表に出た。夏の月が出ていたが、ぼんやりと涙でにじんでいる。 夏の月涙の縁に遊びけり (つづく) |
東京バウハウハデザイン専門学校で教鞭をとる老教授下奈出三郎は、京都タワーの下にある本屋の棚の前にうずくまっていた。清瀬春夏や、綾小路さゆりの上司である。老朽化した土産売り場や、営業不振のスペースに割り込んで来た100均ショップのあるその上の三階に本屋はあった。京都関係の本が多いことと、美術書を中心とした古書も売っている。展覧会カタログなどが多い。京都で開催されたデザイン関係の学会の帰りに、立ち寄ったのだ。それにしても、東京スカイツリーの開業にわくこの時期に、何ともわびしい閑散とした光景である。寒空はだかの『東京タワーの歌』を思わず口ずさむ。 寒空は唱う京都タワーにのぼっタワー 古書コーナーの一角に『季刊「銀花」』が三十冊ほど列んでいる。下奈出はそこにうずくまるように座り込んだ。一九七〇年代発行のものばかりで、きっと蔵書していた人が一括放出したのだろう。あるいは『銀花』を愛読していた所有者が亡くなって家族が処分したのか。下奈出が大学を卒業して、デザイン会社に勤め出した頃の出版物である。表紙デザインは杉浦康平で、その独創性にも当時から下奈出の興味を惹いていた。何冊かを引き抜いて購入することにする。一冊525円。当時の定価で560円だが、『銀花』の価値を知るものには破格の値段である。なかでも、一九七二年発行第十二号、「幻想の版画家谷中安規」の特集を見つけて下奈出は心ときめいた。佐藤春夫や、内田百閒に可愛がられた異才の版画家で、戦後間もなく餓死している。栄養失調である。身近にいた料治熊太が安規の生き様を詳細に綴っている。以前から興味のある作家だった。宝物をかかえる舌切り雀のじい様のように階段を急ぎ足で下り、一階にあるスターバックスに飛び込んだ。 餓死遺才幻想の画師安規の忌 谷中安規の作品は三十四葉掲載されている。お知らせのコーナーには、遺された安規自刻の版木から復刻した作品二点を添付した特装版を頒価三千円で売っている。当時知っていたらきっと買ったのにと、悔しく思う。しばらく安規の特集に目を通してから、パラパラとページをくくると、書店では気がつかなかった萩原朔太郎の自筆生原稿、ほぼ原寸大の俳句論のページに行き当たった。十一ページに渡っている「俳句に於ける枯淡と閑寂味」、芭蕉の俳句を中心に語っている。『萩原朔太郎全集』全五巻(新潮社刊)にも未収録という貴重な原稿である。『俳句新聞』に寄稿したものだ。 閑寂味嫌いて彷徨の詩人おり ─僕は昔、若い時には俳句が大嫌ひであった。その嫌ひの理由は色々あったが、主として俳句の特性である枯淡味や閑寂味が、青年の自分に理解できない為であった。ただ蕪村の俳句だけは、南国的の明るい色彩に富み、比較的に枯淡や閑寂味が少ないので、青年の自分にもよく解って愛讀した。 近頃になってから、僕は芭蕉に深い興味を見出して来た。それは芭蕉のポエヂイの本質に、非常に純一なリリシズムを発見したからである。 こうして始まるその俳句論は、「芭蕉の本質を貫くものは、蕪村よりも尚若々しく、純粋で情熱的なリリシズムである」とつなげる。そして朔太郎は、俳壇、歌壇の批判に論を展開する。歌壇を見ると「世の終り」を感じるし、俳人たちはそうしたことをどう見ているのか、と警鐘する。そして俳句の世界に敷衍する「老人趣味」を厳しく批判する。解りもしないで、「枯淡や、閑寂味」を振り回す老俳人たちを痛罵している。五十代になり「老人」を自らの中に自覚するようになった朔太郎が、まるでそれを忌避するように、歌人、俳人たちの「老人趣味」を許せなかったのは、自戒の念もあったのだろう。下奈出は我が身を批判されているように、さみしい思いを持った。まわりを見渡せば、初夏のスターバックスの店内は、観光客も混じって若い人たちが多く座っている。 スタバにもカラカラと初夏アイスカヒ 解説を書いている伊藤信吉によると、四十代後半で朔太郎は「能」に惹かれていく。友人を誘ってよく観能に出かけている。この『俳句新聞』に書いた原稿は、五十歳の時に書いた朔太郎の『芭蕉私見』の論旨とほぼ一緒だという。その少し前の四十八歳の時に『郷愁の詩人与謝蕪村』を書いているが、能にハマる時期と一致する。朔太郎の東洋回帰、日本回帰の時期である。 伊藤信吉は、朔太郎が蕪村に惹かれたのは、「島崎藤村以来の近代詩の情操に近似している」からだと指摘する。これは、芳賀徹の蕪村論にもしばしば指摘されていることだ。朔太郎は、短歌、俳句、詩(近代詩、現代詩)を、特に分けて考えていない。詩的リリシズムの享受という点で差別をしていなかった。そのひとつが蕪村の「青春的リリシズム」への評価であり、芭蕉の「情熱的リリシズム」であったと見ることができるだろう。「詩はリリシズム」なのである。「抒情、か」下奈出は、アイスコーヒーのカップをカラカラゆらしながらつぶやいた。 夏雲に遮られておりリリシズム (つづく) |
23 辞書を読むSM嬢の艶黒子
SOVASOVAで行われる風月亭花鳥の落語会は、満席の賑わいである。陳蕎麦(ひねそば)ずるるは自慢そうに金谷ケリーと清瀬春夏を迎える。奥の席にはすでに五室剛と綾小路さゆりが、日本酒を呑みながら蕎麦の箸をすすめている。新蕎麦も一年がくればひねる。年々歳々、歳々年々何かが微妙に変化しているのだ。 花も人も同じからずや蕎麦ひねる デジャヴの似ている分の違いかな 「談志師匠が亡くなりましたからね、何かゆかりの演目でもと思いましたが、こんな時候ですから、まずはひとつにぎやかなお話でも」といいながら、花鳥は『頭山(あたまやま)』をやり出した。さくらんぼの種をのんで、頭から桜の樹が生えて来る。すると近所のものが頭に登ってきて、その樹でお花見を始めるというとんでもなくシュールな話だ。うるさくて仕方がないから頭から桜の樹を引っこ抜くと、大きな穴が空いて、そこに水が溜まり池になる。すると今度はみんなが釣りにやってくる。たまらず本人はその池に身投げしてしまう。カフカの小説よりも凄い、国芳のだまし絵を見ているような滑稽さだ。江戸という時代の野方図な想像力を堪能する。 頭から桜噴き出す脳天気 頭の池に身投げも出来る自由かな 会のあと、ケリー、春夏、五室、さゆりら、数人が残った。春の山菜の天ぷらで酒。五室とさゆりはまだ続いている。ケリーと春夏も微妙な関係になっていた。微妙とは少し変なだけで、関係というのはみんな微妙なものなのかも知れない。五室とさゆりも微妙だ。決して奇妙ではない。あり得る範囲での妙。しかし妙は、人が思っているよりも、よほどいいかたちのものかも知れない。 「それにしても花鳥さん、今日の枕に出て来た『シンカイさんの定義』だけど、実に妙ですね」「そう、絶妙! ネタはね、ある作家と言ってますが、実は赤瀬川原平さんの『新解さんの謎』(文春文庫)という本でね。あれ、五室さん知らない? 二十年ほど前にちょっとしたブームになりましたが」と言いながらずるるが文庫本を持ってくる。「これこれ。実は私が花鳥さんに振ったネタでね」「そーなんですよ」と花鳥。「うちの店に、あの有名なアナウンサーのMさんが時々くるんだけどね、Mさんが、こんな本知ってるかってちょこっと、そこで読んでくれたんですよ。あの声でですよ。(と、向こうのテーブルを指さしながら、ページを読みだす) れんあい【恋愛】特定の異性に特別の愛情をいだいて、二人だけで一緒に居たい、出来るなら合体したいという気持を持ちながら、それが常にかなえられないで、ひどく心を苦しめる・(まれにかなえられて歓喜する)状態。 スゴイでしょ、これがある辞書に書かれている文章そのままなんだから。出来るなら合体したい、ですよ。常にかなえられないで、まれに合体出来るんですね、それで歓喜する。歓喜しないといけない」「わたしは、いつも歓喜しますよ」とさゆり。「えらいね、さゆりさんは。でもね、いつもしちゃうと、恋愛ではなくなっちゃうのかも知れない」「単なる愛の営み」「う、春夏ちゃん、大人になったね」「おかげさまで」 「合体がまたいい。 がったい【合体】起源・由来の違うものが新しい理念の下に一体となって何かを運営すること。「公武合体」。「性交」の、この辞書でのえんきょく表現。 新しい理念の下に一体となって運営する。たとえばセックスすることを、そんなふうに認識してする人いないよね。でも、間違ってはいない気がする。いや、そうした認識を持ってこそ、しなくてはいけないんだという気がしてきたね」「ずるるさん、そんなむずかしく考えていたら、合体出来なくなりますよ。合体はセックスすることのえんきょく表現なんだから」「でもなんか、合体の方がリアルに感じる」とさゆり。「セックスしようって言われるより、合体したいって言われた方が、ショックかも」「言う奴いるかな」 「そう、そこがシンカイさんの凄いところ。性交がまたいい。 せいこう【性交】成熟した男女が時を置いて合体する本能的行為。 まず成熟していなくては、性交にならない」「でもそれって、勃起出来るかどうかって」とさゆり。「なるほど、それは正しいかも」「いや、男の子は小さい頃から結構勃起しますよ」と花鳥。「自分がいつ頃から勃起し出したかなんておぼえてないなあ」とケリー。「挿入出来るかどうかはわからないけど、とんがる」「そうにゅうことですね」「おやおや」「確かに成熟が終わった老人もだめだわ」とずるる。「実感ですか」「やや。大切なのは、『時を置いて』ということなんです」「本能的な行為をするのに、成熟度を感じますね」と春夏。 「で、シンカイさんて何なんですか」と五室。「三省堂の新明解国語辞典なんですよ。それも4版目ぐらいから、凄くなり出す」「実は、赤瀬川原平さんに、『新解さんの謎』を書かせたSM嬢という人物がいるんですね。文芸春秋の社員なんだけど、この人が『新解さん』の魅力を発見するんです。中学に入学したSM嬢は、父親からこの三省堂の新明解国語辞典を贈られる。すぐに同級生の男子がその辞典を貸して欲しいというので貸すと、返されたあとにいくつかの項目のところに赤線が引かれているのに気づくんですね。【恋愛】【合体】【キス】【陰茎】【勃起】のようなHな言葉にね。それでSM嬢は、新解さんのある種の魅力、あるいは異常と行ってもいいかも知れないその表現の迷宮に落ちていくんです」 「赤瀬川さんに『新解さんの謎』を書かせたあと、自分でも『新解さんの読み方』(リトル・モア刊)という本を書きます。これが徹底して凄い。なにしろ新解さんに出会ってから二十年間、電車の中でも新解さんを読み続ける。私ね、アマゾンで古本見つけて買いましたけど、109円、送料250円。これね。ついでに『新明解国語辞典第4版』460円も入手しました。家宝です。しかし、SM嬢の本が109円というのには、ある種の胸の痛みを感じました。1090円でもいい。いや、10900円でもいいと、ほんと、思いました」「入れ込んでますねえ」「入れ込んでる。SM嬢の凄いところは、各版の新解さんを徹底して読み比べている。そして、新解さんの心の変化まで読み取ってしまった。『新解さんの読み方』には、SM嬢の顔写真まで出ていて、その艶黒子の妖艶なこと。SM嬢、本名鈴木マキコって言うんですよ」 辞書を読むSM嬢の艶黒子 新解さんという迷宮に入るSM嬢 「SM嬢のことはわかったけど、結局凄いのはその辞書を編集した新解さんと言うことになる」「うーん、さすがケリー君。そうなんです。累計2000万部を超えるという人気辞典で、それはまさに新解さんの力と言っていい。面白い刺激的な辞典を作ろうという情熱が爆発する。鈴木マキコさんのこの本にも終盤で出てくるけど、山田忠雄という編集主幹が『新解さん』の正体なんです。その前身の『明解国語辞典』から、金田一京助の名前が筆頭だけど、忠雄の父親の孝雄が編集に参画し、『新明解』になる頃から、『新解さん』の忠雄が登場する。その後に、忠雄の息子の明雄も、この『新明解』にかかわるという、なんと親子三代にわたる汗と涙と笑いの結晶なんだ。AKB48じゃないけど、逢いたかったー、逢いたかったー、逢いたかったー、イェイッ!」「マキコさんを通して、赤瀬川さんも山田忠雄さんに会おうとしているようだけど、新解さんは『会わない方がいいでしょう』と、一蹴したようですね」「そこは、興味本位ではない、学者なんですね」 「『新解さんの読み方』の最後、340ページに山田忠雄さんの新聞に載った死亡記事が切り抜かれて、SM嬢のノートに大事に貼ってある写真が出ている。これね! 小さくてね、凄く読みにくいのだけど、よーく読むとこう書いてある。一九九六年の二月の記事です。 山田忠雄氏(やまだ・ただお=元日本大学教授・辞書史研究)6日午後9時23分、心不全のため、東京都武蔵野市の病院で死去、79歳。葬儀、告別式は10日正午から武蔵野市八幡町1の1の2の延命寺で。喪主は長男明雄(あきお)氏。自宅は武蔵野市吉祥寺東町3の27の9。三省堂『新明解国語辞典』の編集主幹を務めた」 陳蕎麦ずるるは、本から顔を離すと、虚空を仰ぐようにぽつりと言った。 「何かの因縁ですかね。この延命寺って、うちの菩提寺なのよ」 (つづく) |
南フランスで、コマーシャルフィルムのフェスティバルがあった。金谷ケリーがかかわったコマーシャルがノミネートされて、フェスティバルに出向いたが、残念ながら入賞は逃してしまった。その帰りひとりパリによって二日ほど過ごすことにした。久し振りのパリ、それにしてもノエルも、ヌーヴェルアンも終わったソルドの街は、ただ寒いだけだ。大きなブランドの紙袋を抱えて歩くアジア人女性は、今では日本人とは限らない。中国人だったり、韓国人だったりするから、やたらに声もかけられない。 人に土地の記憶というのもがあるとすれば、ケリーにとってパリは、実際に住んで蓄積した記憶ではないけれど、書籍や、画集や、展覧会、映画で経験したフランスの、それもパリの思い出が色濃く形成されていた。植草甚一が一度もニューヨークに行かずして、ニューヨークの隅々までを知っていたというエピソードに似ている。その後実際に植草がニューヨークに行くとその通りだったという後日談もあるほどだ。 アンドレ・ブルトンの『ナジャ』を読んで、ナジャが出没したストラスブール通りの「まったくなんの役にもたたない」サン・ドニ門とか、ブルトンが好んで集めたアフリカの木彫の仮面や、小さな人間像とか、モンパルナスの女神としてアーティストたちに愛され、モデルをしたり、自らもドローイングをして人気を博したキキ(本名はアリス・プランという)。彼女は、マン・レイと「火山のような恋」をして、六年間を同棲し、キスリングとも熱愛した。その彼らが愛したモンパルナスのレストラン、ラ・クーポールは、二十世紀初頭のアーティストたちのポートレートや、アートが空間を仕切っている。『ミラボー橋』が大ヒットするアポリネールは、マリー・ローランサンとの恋に破れ、第一次大戦に従軍して頭を負傷する。ブラックもだった。しかもアポリネールはスペイン風邪でころりと死んだ。 ディアギレフ率いるバレエ・リュス(ロシアバレエ団)には、ピカソも、ミロも、デ・キリコも、ブラックも、パクストも、コクトーもかかわった。明治の豪商木綿問屋の三代目バロン・サツマ(薩摩次郎八)も、バレエ・リュスを追っかけた。当時日本からパリに渡った画家たちは、四百人ともいわれるが、その多くを薩摩は支援している。百年も前、日露戦争(1904—05)があり、第一次大戦(1914—18)が始まり、ロシア革命(1917)が起こる。そんななかで、なんでこんなに芸術が花咲いたのだろうか。貧困と迫害の流民たちのエネルギーが、こんなにまでにポジティヴに世界を表現した。さまざまなスタイルのアートを生み出した。 しかしアートの記憶は今やすべて、文化ではなく観光になり始めている。ケリー自身、パリを歩けば文化に触れるのではなく、観光地をさまよっている気持ちになってしまう。昔の記憶をたぐればそこがカルチャーから遠ざかる。ルーブル美術館も、ガルニエ宮(オペラ座)も、エッフェル塔も記憶の収蔵庫でしかない。そのエッフェル塔の脇、ブランリ河岸に出来たケ・ブランリ美術館を覗いた。透明なガラスの巨大な壁沿いに歩くと、ランドスケープ・デザイナーのジル・クレモンの仕掛けるブッシュが待ち構える。そこをくぐり抜けるうち、巨大な赤い船腹を見せるノアのような建屋が見えてくる。奇才ジャン・ヌーヴェルの傑作である。ケリーは思わず「おーっ!」と、声を上げてしまった。 オセアニア、アジア、アフリカ、アメリカの原始民族芸術の宝庫だ。ジャック・シラク大統領(当時)の肝煎りの構想だったこの美術館も、賛否両論が渦巻き大騒ぎの結果の開館だった。しかしこうして見ると、フランスの民族学に対する好奇心と研究心は、法外なものである。ブルトンが生きていたら、さぞかし驚嘆したのではないだろうか。コレクションのほんの一部だという展示数も、展示デザインも群を抜いて魅力がある。ケリーはそこが観光の名所とされていたとしても、充分に満足するものがあった。 ボザールの横を抜けて、ギャラリーや古書店を覗き、サンジェルマン・デ・プレに向かう途中で日暮れて、まだ時間は早かったが小さなビストロに入った。ワインを選び、二、三品の料理を頼んで小さな道の閑散とした風情をぼんやりと眺めていた。ふと、「たまには飲まない?金曜日とか」「いいよどのへんで」去年の夏の会話が聞こえてきた。「人生相談は苦手だよ」「相談はしない。勝手に告りたくなって」「それは、彼を愛しているからだね」「そうかも知れないし、そうじゃないかも知れない」「じゃあもう、コメントの必要もない」「私のうちでもう一杯飲まない?」「いいよ」タクシーの中で握りしめてくる清瀬春夏の暖かい掌を思い出していた。その夜の春夏との、深くて静かな愛の時間を思い出していた。同級生という関係が二人を遠ざけていたが、その夜の春夏の肉体に成熟した女性の力を感じた。「美しいな」と思った。けれどもそれから、春夏からは連絡がなくなった。「そうか、オレから連絡すべきだったのか」。エッフェル塔の下で買った小さなエッフェル塔をケリーはバッグから出して掌にのせ、それからテーブルの上に置き、包装紙の裏に一句メモした。何となく買ったエッフェル塔だったが、そうだ、これは春夏にあげよう。東京に帰ったら手渡そう。「エッフェル塔だぜ、土産が!」ケリーはビストロの隅でひとり声を出して笑った。 エッフェル塔 La tour Eiffel 掌に小さく尖る世界土産 Le souvenir mondial s'eleve mignonnement dans la paume ブルトン Andre Breton 超現実的ナジャに繋がる通底器 Vases communicants attaches a Nadja, surrealiste マン・レイ Man Ray キキの背のfの字型のヴァイオリン Un violon avec la lettre f au dos de Kiki コクトオ Jean Cocteau 阿片吸引人體組織デッサン画帖 Opium, et corps sur son carnet アポリネール Guillaume Apollinaire 頭蓋骨割れて詩溢るゝミラボー橋 Le Pont Mirabeau, le poeme deborde du crane casse デュシャン Marcel Duchamp 便器車輪既製品(レディメイド)の反芸術 Le ready-made, la fontaine et la roue de bicyclette, est anti-art ルーヴル美術館 Musee du Louvre 遺跡より生え出すガラスのピラミッド La pyramide en verre sortie des vestiges オペラ座 Palais Garnier 怪人もエトワールも拍手食らいて生き Le fantome et les etoiles vivent d'applaudissements パスティス pastis 菜の色の肉桂(ニッキ)の香呑み人を待つ Attendre quelqu'une en buvant l'arome d'anis colore fleur de colza アン・ドゥミ un demi 泡立ちて心ざわめく逢魔ケ刻 Au crepuscule quand une bulle augumente et mon coeur est agite エスカルゴ escargot 野の星のマイマイツブロ銀河系 Galaxie, les etoiles telles qu'un escargot dans les champs オ・ピエ・ド・コション Au Pied de Cochon 豚の足で牡蠣の山崩す檸檬汁 Casser la montagne d'huitres au pied de cochon et le jus de citron 仏訳=ひるたえみ (つづく) |
21 君がためか今冬極めて寒いノダ
「ノダ君の気持ちはとっても嬉しいけど、きっとうまくいかなくなるよ」「どうしてそう決めるのさ」「私がもっと年を取ったら、ノダ君、私のこと嫌いになる」「勝手に決めないでよ。それはオレの気持ちだよ。オレが決めることでしょ」「きっとそう決めると思う」「そう決めないよ、絶対」二人は口論して、それから、セックスした。うとうとしてまたセックスして、口論になって、朝、ノダ君がうなだれるように部屋を出て行くのを、春夏は見送った。 それから、ずっと部屋が寒くなった。エアコンを28度にしても、春夏は暖かくならなかった。「でもさ、これはきっと、私から望んだことだから、これには耐えないといけないんだ」目の前の幸せを保持して生きていくという勇気がなかった。決断出来なかった。悲観的になることが、自分にとってマイナスであることはわかっていたが、決めないで続けるより、決めて終わることを望んだ。「だからって、これからの私に何があるのだろう。何も起こらないということはないとしても、いいことが起こる可能性は減る」後悔もあった。ノダ君に申し訳ない気持ちもあった。ノダ君はばったり来なくなった。 春夏は夜一人、厳しい冬の句を探して俳句の本をめくっていた。 病雁の夜寒に落ちて旅寝かな 松尾芭蕉 老いが恋忘れんとすれば時雨かな 与謝蕪村 ひいき目に見てさえ寒し影法師 小林一茶 冬灯死は容顔に遠からず 飯田蛇笏 冬蜂の死にどころなく歩きけり 村上鬼城 鉄鉢の中へも霰 種田山頭火 咳をしても一人 尾崎放哉 流氷や宗谷の門波荒れやまず 山口誓子 毟りたる一羽の羽毛寒月下 橋本多佳子 あはれ子の夜寒の床の引けば寄る 中村汀女 鯛の骨たたみにひらふ夜寒かな 室生犀星 木がらしや目刺にのこる海のいろ 芥川龍之介 鮟鱇の骨まで凍ててぶちきらる 加藤楸邨 雪はしづかにゆたかにはやし屍室 石田波郷 水枕ガバリと寒い海がある 西東三鬼 遺されて母が雪踏む雪明かり 飯田龍太 冬の葬列吸殻なおも燃えんとす 寺山修司 ずらり書き並べてみて、ホットワインで体を温めながら、あらためて春夏は膝を抱えて読み返しだした。 「俳句って、のほほんとしているのが目立つけど、厳しい俳句、結構あるね。芭蕉、そうだよなあ、病気の雁だったら、夜の寒さに耐えかねて落ちて死んでしまうかもね。蕪村、年とって人を恋したりしちゃいけないんだよね。でも、年寄りだって、恋をする。とりわけさみしい時雨ね。一茶、ふむ、部屋の行灯に揺れる自分の影法師、ひいき目に見なくったってさえなかったんだろうな。蛇笏、これも部屋の明りか。死者はまだほんのり赤く見えるけど、じきに死者の顔になるだろうって句なのかしら。鬼城、だいたい蜂が冬まで生きているってのが間違いだよな。でも、死にきれないっていうのもつらいね。山頭火、鉄鉢に霰がコツコツ当たってる感じ。手が凍えて、脚の指も凍えて、もうヤバいって状態。放哉、コホンて音が、自分しか聞こえない孤絶。誓子、宗谷はだめな船で『南極大陸』のドラマつまらなかったけど、流氷のオホーツク海は寒いよなあ。多佳子、鳥の毛毟ったら、寒くなくっても鳥肌でしょ。多佳子らしい激しさだなあ。汀女、この人、子供の句がいいね。部屋は寒いけど、母子の関係が暖かいね。犀星、鯛の骨って、鯛のかたちしているあの辺の骨かな。畳が冷えきってるんだよね、きっと。龍之介、干物にされてもなお、海の色を眼球にとどめてるなんて、龍之介の執着を読むようだね、木枯らしの音も効いているよね。秋邨、顎に鈎引っ掛けられて、吊るされて、そのまんまぶった切られるんだから、処刑だね。その後は、煮えたぎる鍋にぶち込まれて、ハフーハフー食われてしまう。波郷、病室から雪の向こうに見える霊安室を見ている。また誰かが死んだ。次は自分かしらって、思ってるのかな。三鬼、水枕が必要なんだから、熱があるんだよね。それにしても、ガバリって音感から、冬の寒々とした海を連想するなんて、さすがね。龍太、蛇笏が死んで、夜に雪道を帰ってきたのかな。雪明かりだけを頼りにサクサクトボトボサクサクトボトボ。龍太の後ろを歩いている母親の気配。修司、これも葬式か、冬の葬式はそれだけで厳しいかも知れない。死者はすっかり死んでしまっているのに、吸殻がまだくすぶって燃えようとしている。まるで生に執着する自分みたいに。でも、死ぬんだったら、やっぱり冬かな。悲しいものね、寒いだけでもう充分に」 春夏は、ホットワインをもう一杯つくって、ふうふうしながら呑んだ。 「ノダ君、君は私のこと、きっと憎んでるよね。でも、私はノダ君のこと、まだ好きだよ。私のこと、憎んでてもいいから、思い出してね。まだ、君に忘れられるのが辛いの。それにさ、テレビに野田どじょう首相が出るたんびに、ノダ君のこと思い出しちゃうんだ。困ったもんだね。でも、春になったら、もう、忘れてもいいよ。今ね、必死に激寒の俳句書こうとしてるの。不幸な私をきちんと書こうと思ってね。でも、私には激寒の俳句なんて書けないよ。ほんとは不幸じゃないのかも知れないね。なんか、バカみたいな句しか浮かばないから。でも書いとく」 君がためか今冬極めて寒いノダ (つづく) |
|
20 霧深し背伸びして見る回教徒 煌々と照る望月に群雲がせわしなく重なり、また離れ、池の面がうっすらと明滅しているようにも見える。そのほとりを風月亭花鳥は早足で歩いていた。いや別に時間にせかされていたわけではなく、秋風が急に冷たくなってきたからだ。動物園の方角から大きな鳥の鳴き声が聞こえてくる。花鳥は大声で、鳥の鳴き真似をした。「ゲオゲオー! おっとこれじゃあレンタルビデオ屋だ」向かうは、言わずと知れた陳蕎麦(ひねそば)ずるるのSOVASOVAである。 「寒くなったね」「こうなると燗酒ですか」「獺祭(だっさい)でも温(ぬく)めましょう」「いいなあ、子規先生でも思いながら一杯」「子規が獺祭書屋主人と自称したのは、やっぱりカワウソみたいな髭を生やしていたからでしょうかね」「でも獺祭は山口の酒ですよね」「となると山頭火の地元。そういえば山頭火の実家も酒蔵だね」「じゃあ、今日は二人合わせてと」「いいね」蕎麦粉で作ったクレープをつまみに、二人はテーブルに向かい合った。 「これ『寺山修司の「牧羊神」時代』(朝日新聞出版)、読んだ?」緑色の帯の本を手にずるるは言った。 「いや、知らなかったです」と、花鳥。 「松井牧歌(寿男)という人が書いているんだけどね。寺山が一九五一年十五歳で青森高校の文芸部に入り、翌年には青森県高校文学部会議を組織して、同時に全国の高校生に呼びかけて十代の俳句雑誌『牧羊神』を創刊する。その時大阪から参加したのが松井牧歌でね。当時のことが詳しく書かれている。寺山との文通も全部保管していて、東京に出てからも頻繁に会っているんだ」 「寺山って人は、人懐っこい性格だったようですからね、牧歌のどこかにきっと興味を持ったんでしょうね」 「そう、やっぱり俳句の力かな。例えば、寺山が青森市の野脇中学校で運命的に出会う京武久美、彼の『父還せ空へ大きく雪なぐる』を、『父還せランプの埃を草で拭き』(われに五月を)と改句し、さらに短歌にして『作文に「父を還せ」と綴りたる鮮人の子は馬鈴薯が好き』と展開して、短歌研究新人賞を獲る。この『チエホフ祭』の応募の時のタイトルは『父還せ』だったわけで、京武を鮮人にしてしまっているんだね。同じように、牧歌の俳句『紫陽花の花のくらさよ学に倦む』を、『芯くらき紫陽花母へ文書かむ』と寺山が書き換える。牧歌にとっては『学燈』で石田波郷に二席で選ばれた作品だ。寺山の類似句への抗議を悔しく回想しているね。しかも寺山はさらに、『紫陽花の芯まっくらにわれの頭に咲きしが母の顔となり消ゆ』と、短歌にまでして、牧歌をぶちのめしてしまう」 「こうなると、よく言われるような剽窃などではなくて、もう刺激された作品に無条件で、反射神経で反撃してしまう、格闘家ですね」 「しかも、異種格闘家になっていくね。牧歌はネフローゼで新宿の社会保障中央病院に入院していた寺山を見舞ったりもしているけど、寺山がラジオドラマや、演劇の脚本を書くようになって、どんどん時代の寵児になっていくと、必然二人は疎遠になっていく。結局、寺山との少年時代の関係を、牧歌は封印してしまう。ところが、牧歌の主宰する『水路』という句会に参加していた岡井輝毅という人が、『一滴』という写真と俳句のコラボ誌を立ち上げ、岡井のすすめでそこに寺山修司との回想記を連載し始める。それが、平成十七年。ところが二年半で牧歌は急逝してしまう。つまり未完なわけなんだけど、それを整理して出版にこぎつけた」 「牧歌の忸怩たる思いもひそんでいる一著というわけですか」 「その中の、『牧羊神』5号(54年)の座談会(六名参加)『火に寄せてー恋愛俳句の可能性』という、面白い話しが写されている。橋本多佳子の『雪はげし抱かれて息のつまりしこと』に話しが及ぶ。松井牧歌が『恋愛の頂点だね』と評すると、京武久美も共感し『これは日本間だと解釈したいんだ』と発言する。それを受けて寺山が、『これは屋外でなければだめ』と修正する。私たちも普通この句は激しく降る雪の中で抱き合っていると解釈しているよね。ところが、奈良から出て来ている宮村宏子という子が、天理大の学生で演劇をやっていたらしいけど、『絨毯のしかれた暖炉のある部屋をまず想像してごらんなさい。『雪はげし』は室から見た雪の激しさで、だから満ちたりた幸福感があるのだと思います』と切り返している」 「へー、寺山のいう屋外は確かに劇的な解釈だし、我々もそんな風に思っていたけど、よくよく考えれば大人の多佳子ともあろう人が、はげしい雪の中で抱き合っているなんて、そんな馬鹿なことをするかなという反省もあるね。ただし、満ち足りた幸福感というよりも、やっぱり哀切感ですね。『息のつまりし』だもの、苦しいんですよ、どこか。それにしても、語感的にもいい作品ですね。YUKI/IKI HAGESHI/TSUMARISHI」 「雪の中で抱き合っているというのは、やっぱり考えてみると、切羽詰まった抒情だね。昔、日活映画で藤原審爾原作の『泥だらけの純情』(63年)っていうのがあったけど、浜田光夫のチンピラやくざと、吉永小百合の外交官の令嬢が恋に落ちて雪山で心中してしまうという、そんな陳腐なストーリーを連想するね。もっとも私はその『泥だらけの純情』見て、泣いちゃったけど。高校生の時に」 「わははっ」 「笑い事だよね。ところで宮村宏子のいう『絨毯で暖炉の部屋』というのも根拠がないわけではない。『橋本多佳子全集』(立風書房)第一巻の口絵に、多佳子の亭主、豊治郎の設計した和洋折衷の三階建自邸の写真が載っている。小倉市にあった櫓山荘。これがまさにそういう家だね。多佳子の生活環境にはそれがあった」
「そうなんだけど、そのあたりの資料にお目にかかったことがない。あるいは軽くあしらわれて、玄関払いにあったのかも知れないし。その時、牧歌の友人で、丸谷タキ子という少女俳人が天理市にいて、その子のうちで寺山の歓迎句会をやっている。寺山はその丸谷さんに相当興味を持っていた」 「天理大の宮村宏子さんも、丸谷タキ子さんも、生きていれば今七十六、七歳のおばあちゃん。ちょっと会ってみたいなあ」 「その頃、寺山は『牧羊神』を発行しながら開催した「全国高校生俳句コンクール」が成功して、五四年『俳句研究』の編集長石川桂郎を口説いて、「俳句研究社新人賞・全国学生俳句祭」を企画する。驚いたねー、弱冠十八歳の少年がだよ」 「恐るべし、寺山修司ですね」 「この俳句祭は呼びかけただけで実現はしなかったみたいだけどね。審査員の一人として声をかけられた飯田龍太は、一度は引き受けるのだけど、寺山が龍太に自分の作品を送りつけたことに疑問を持って降りる。そのことは龍太の『龍之介と寺山修司』という文章で述懐しているね。それにしても当時の気鋭の俳人を、選者に名を連ねさせた政治力というか」 「寺山は投稿魔でしたから、あちこちの句誌、雑誌に投稿して、すでに有名な高校生俳人だったみたいですね」 「地元の俳誌『暖鳥』『青森よみうり文芸』、不死男主宰の『氷海』、多佳子主宰の『七曜』、受験雑誌の『学燈』や『蛍雪時代』出しまくってぼんぼん選ばれていた。彼は七〇年に『トマトケチャップ皇帝』という実験映画を撮っているけど、子供たちによる大人狩りの映画だ。「俳句祭」の企画はそれに似ているね。学生たちが俳句革命運動を目指すものだった。しかも転覆しようとする前の世代の力を利用してだよ。これは一筋縄の若者の考えではないね」 「うまく行ったら協力した前の世代も谷に突き落とす」 「そこまで考えていたかはわからない。でも俳句の世界のイニシャチブを握ろうとはしていたね。しかし失敗した。由井正雪か、天草四郎みたいにね」 「でもそこでその「俳句祭」は実行できなくてよかったかもしれませんね。うまくいってしまっていたら、寺山は第二の虚子で終わっていたかもしれませんよ」 「ふーむ、確かに。青年ゆえの性急な行動が挫折を招いた。そして短歌に移り、短歌研究新人賞を獲り、それがまた剽窃騒ぎで追放される。逃亡者のように、表現の国を渡り歩き、越境をくり返していくんだね」 「一所不在ですか」 「いや、全所存在みたいな欲望があったんじゃないだろうかね。寺山がギブアップしたのは、最後の病気だけだった」 「それにしても、寺山修司の世代の連中は、橋本多佳子や、中村草田男、石田波郷、秋元不死男、山口誓子、加藤楸邨、西東三鬼などなど、ひとつ前の世代に大いに影響されて、思想から語彙まで写すように作句している。昭和二十年代という時間の檻の中でね。そして芭蕉が西行の和歌を規範にして、31を17に圧縮する、あるいは引き算したようにもね。西行の『とくとくと落つる岩間の清水くみほすほどもなきすまいかな』を、芭蕉は『露とくとく心みに浮世すすがばや』と書き換えた。平安末期から江戸元禄期にトランスレートとトランスポートを重ねる」 「ということは、私たちにも自分でも気がつかないうちに、俳句を作るときの思想、ちょっとおおげさかな、ライフスタイルみたいなもの、語彙、はやりをインプリントされているってこと?」 「うん、そんなことを漠然と考えていたんだ。我々の場合は一九六〇年代の文化の中で間違いなく形成されているはずだね」と演歌、フォークソ 「それは、詩歌的には三島由紀夫でも、安部公房でも、大江健三郎でもないね。きっング、GS(グループサウンズ)だね。ビートルズは外国語だし、クレージーキャッツだったり、坂本九だったり、森進一や、八代亜紀、タイガース。だったら、青島幸男、永六輔、川内康範、阿久悠、なかにし礼・・・」 「そうかも知れないんだよ。こうした大衆化された言語感覚の中で、私たちの文芸の基礎は固まってしまっている。恐ろしいだろ!」 「うおーっ! 寺山修司に敬意を表して『霧深し』と言えば『背伸びして見る回教徒』でしょ」 「『しみじみ』とくれば『ぬるめの棺がいい』。死にたくなるね、ほんと。獺祭、ぬる燗もう一本やるか!」 以下、陳蕎麦ずるると、風月亭花鳥の系図化された詩歌の源流的作句を記しておく。 港町ブルース 霧深し背伸びして見る回教徒 舟歌 しみじみと死ねばぬるめの棺がいい 花の首飾り 首飾り編む乙女らのヒナゲシ野 勝手にしやがれ 窓際に背を向けしまま別れかな なごり雪 なごり雪落ちては解ける問題集 また逢う日まで 逢えるかはわからぬ別れドアを閉め 恍惚のブルース 溺れても恋が命の女あり ブルーシャトー 森と泉ブルブル青い冬館 (シャトー) 襟裳岬 忘れきて春の岬は何もなし 長崎は今日も雨だった わわわわー一人にかけた恋の雨 白い色は恋人の色 想い出の色足もとに白く咲き (つづく) |
清瀬春夏から、メールが来た。「たまには飲まない?金曜日とか」「いいよ、どのへんで」金谷ケリーが春夏の指定したビストロに行ったのは、金曜日の午後八時。春夏は窓際の奥の席で手を上げた。キャンドルの小さな光で春夏の顔が仄赤く見える。「どうしてまた?」「誘っちゃだめ?」「いや、春夏に誘われたら断れない」「どうして?」「さあ、断りにくい」「ふーん、元気?」「元気だよ。春夏も元気そうだね」「元気だけど、不安定」「人生相談は苦手だよ」「相談はしない。勝手に告りたくなって」「やっぱりそういうことか。聞き流すのは得意だよ。存分に」「ふー、ちょっと安心」「緊張するようなことなの?」「さあ、冷静に聞いてくれる人が欲しかった」「やれやれ、大変な仕事そうだ」「止めようか、やっぱり」「そこまで言っておいて止める気?」「興味あるんだ」「ふむ」 密会の女は仄か燭に揺れ 金谷ケリーはさっきまで読んでいた日野草城のことを、ぼんやりと思い出していた。ネットで取り寄せた復本一郎の『日野草城─俳句を変えた男』(角川学芸出版)。同氏の『俳句とエロス』(講談社現代新書)で、草城の若干の情報は読んでいたが、『ホトトギス』同人除名の件から、第一句集『花氷』(昭和二年六月刊)の秘話、『ミヤコ・ホテル』を巡る事情を詳しく検証している。年譜を見ると、昭和六年に甲川政江(のちの俳人、晏子)と結婚している。しかしそれ以前の作品に「妻」がしばしば登場するのだ。不思議に思っていたらそれが大正十年、草城二十一歳の時に婚約した佐藤愛子であることもわかった。二人は大正十五年に婚約を解消し、愛子は医師と結婚。『花氷』出版の翌年に亡くなっている。草城は紀州白浜に療養見舞いにいっているので、愛子は体が悪かったようだ。病名は書かれていないが、結核だったかも知れない。周辺の情報を整理すると、奇妙なことに日野草城と愛子の間には性的な関係はなかったという。しかしこの第一句集には、濃厚なエロティシズムを秘めた作品であふれている。 『花氷』 妻も覚めて二こと三こと夜半の春 人妻となりて暮春の襷かな 春の灯や女は持たぬのどぼとけ うららかに妻のあくびや壬生念仏 朝すずや肌すべらして脱ぐ寝間着 翩翻と羅(うすもの)を解く月の前 ぼうたんや眠たき妻の横坐り ひなげしや妻ともつかで美しき 十八歳の時に乾性肋膜炎に罹り、それからの病質は五十六歳で亡くなるまで草城に潜在する。過度の細菌恐怖症であったらしく、身体的接触にも極めて神経質であったのかも知れない。草城は愛子との関係を『明日の花』という小説で詳しく描いている。愛子がモデルという葉子は、『結婚て一体どんなものなのかしら?あたし早く結婚してみたいわ。』それに対して草城がモデルの隆夫が『やどうも恐れるなあ。』と反応している。しかしそのニュアンスはけっして拒絶しているものではない。うれしそうに聞こえる。若い日野草城はなぜ「妻」というものにこだわったのか。 妻という名の牢奥に光る女体あり 「それがさあ、今変なことになっちゃっていて、しあわせなんだけど、ちょっとどうしていいか困ってるの」「ふーん、しあわせならそのままでいいじゃない」「うーん、しあわせなんだけど、ちょっと普通じゃない」「普通じゃないしあわせなんて、いいじゃない」赤ワインが来てグラスに注がれる。「ひとまず、乾杯!」「乾杯」「もしかして、のろけ?」「そう聞こえるかもしれない。でも違うの」「ややこしそうだね」「だから勝手に告るって」前菜の盛り合わせが来る。ケリーは手際よく二つの皿に取り分ける。「ありがとう。大人だね、やっぱり」「こんなことは子供でもする」「そんなことないよ」「まあ、いろいろな人がいるからね」「いろんな人がいるね、ほんと」肘をついて頬に手のひらを当てながら春夏はフォークで前菜を口に運んだ。「大丈夫?」「じゃないかも」春夏は、金谷ケリーを見つめながら、ノダ君とのことをぽつぽつ語り出した。 「なりゆきってあるじゃない。卒業生を学校に呼んで授業してもらって、一緒に飲んで、それで、つき合うようになって」「普通じゃない」「でも教師と教え子で、七歳年下だよ」「ぜんぜん、異常じゃない範囲だね」「そうかなあ、浅はかだったかなって反省しているの」「どうしてさ。うまくいってるんでしょ」「まあ、で先週、結婚したいっていわれて」「いいじゃない。遊びのつもりだったの?」「うーん、すごくいい子だから。断る理由がなかった。でも、結婚なんて考えてもなかったし、彼とはね」「本気で惚れたんだね。それで妻にしたいって」「そうかな、ちょっと舞い上がってるって感じ? 私は、彼の妻になんか絶対なれないし、彼が旦那だなんて考えられない」「すぐなれるさ。じゃなければ妻でも旦那でもなくていい、一緒に暮らすだけでいいんじゃない?」「そうかなあ。結婚ってファミリーになるんだよ。子供作ったりとか。色々考えると、結局うまくいかなくなるって思うの」 妻という鉛の衣脱ぐ肢体 日野草城は二十一歳の時にすでに「妻」の俳句を詠んでいる。しかし許嫁はいたが独身である。草城の「妻」という幻想が、俳句を一段と妖しくしているのだ。金谷ケリーは清瀬春夏のビストロでの話しを、まるでデジャヴのように聞いていた。春夏の相手の彼は、果たして春夏を「妻」に迎えようとしているのだろうか。ケリーは自分のなかに、「妻」という概念がまったく欠落しているように思えた。いやそれは、今の若い男たちに共通した思いなのかも知れない。妻でも、女房でも、連れ合いでもなく、パートナーなどと気取る人もいるが、どれもがしっくりしない。自分が亭主や旦那というポジションに座っている映像が思い浮かばない。夫婦というのが、いまではけっして輝かしい黄金分割で囲まれているものではなくなっている。春夏はそれを年齢差で強く認識したのかも知れない。 草城は昭和六年、三十一歳で結婚し、翌年第二句集『青芝』を上梓する。しかしこの句集には、『花氷』のような執拗なエロティシズムを感じない。 『青芝』 春暁や雨を疑ふ妻の耳 寝おくれて妻のかかぐる蚊帳の裾 足のうら二つそろへて昼寝かな 相手のせいかも知れない。幻想の「妻」と、現実の「妻」には大きなギャップがあったのかも知れない。結局それが結婚から三年、昭和九年『俳句研究』に発表した虚構の新婚旅行の俳句『ミヤコ・ホテル』十句となって結実し、エロティシズム俳句の金字塔となる。ひいてはそれが、『ホトトギス』同人から除名される事態にまで発展していくのだ。 『ミヤコ・ホテル』 けうよりの妻と泊まるや宵の春 春の宵なほをとめなる妻と居り 枕辺の春の灯(ともし)は妻が消しぬ をみなとはかかるものかも春の闇 薔薇匂ふはじめての夜のしらみつつ 妻の額に春の曙はやかりき うららかな朝の焼麭麩(トースト)はづかしく 湯あがりの素顔したしも春の昼 永き日や相触れし手は触れしまま うしなひしものをおもへり花ぐもり 結婚後三年、虚構の新婚旅行は、ふたたび草城に凄まじい想像力のエロティシズムを成立させる。それは春夏の彼が、春夏に「妻」を幻想するそれよりもはるかに現実を知った上で構築する「妻」という虚構を磨き上げた結果だった。『花氷』で描かれた愛子の媚態は、あるいは本当に想像力で塗り込められた幻想だったのかもしれない。ともあれ、第二次大戦に向かう社会風潮の中で、『ミヤコ・ホテル』はそのように受け止められ、俳壇からの凄まじい攻撃の標的になってしまう。 黄金分割な関係などなし春褥(しとね) ワインボトルは二本目が空きそうになっていた。「これはやっぱり、春夏の問題だからね。春夏が決めることだね」「そうだね。それはもう決まってるの。彼とは結婚しないってね。それで、別れるって」「それは、彼を愛してるからだね」「そうかも知れないし、そうじゃないからかも知れない」「じゃあもう、コメントの必要もない」「だから最初から、勝手に告るって言ったでしょ」「そうだったね」「そう。ありがとうね、ケリーさん。ご迷惑かけたお礼に、私のうちでもう一杯飲まない?」ケリーは春夏の顔をじっと見つめながら、「いいよ」とだけいった。春夏はテーブルの上のケリーの手を握った。 日野草城の『ミヤコ・ホテル』を、中村草田男も激しく非難した。 「肉体とか女性とかに属する範囲内から題材を採取してくること、それだけが格別批難に価しようわけではない。たヾ俳句の如き、作者の「たましひ」とかヽりあふ事柄のみを扱ふ心境芸術の中へ、斯る人生の厳粛なるべき情景を持ち来しておきながら、対象の中へ謙虚なる態度を以て沈潜しようとする気配もなく、これをたヾ一場の玩弄物と化し去つてしまったことが、なんとし手も許せないのである。」 当時すでに草城は、無季俳句を標榜する、新興俳句(草城は必ずしもその呼び方に共鳴していなかったようだが)の拠点『旗艦』を起し、有季定型で花鳥諷詠を基本とした高浜虚子との差異を明確に意識していたのである。草田男のこの強い口調での批難は、尊師たる高浜虚子を意識しての一文のようにも取れるし、『ホトトギス』同人削除という決定への援護射撃のつもりであったのかも知れない。それにしても、草田男にも「妻」を詠んだ俳句がその後多く作られていくのだが。 『火の鳥』(昭和十四年) 妻二タ夜あらず二タ夜の天の川 妻抱かな春昼の砂利踏みて帰る 妻恋し炎天の岩石もて撃ち 妻のみ恋し紅き蟹などを歎かえめや 『万緑』(昭和十六年) 虹に謝す妻よりほかに女知らず 玉菜は巨花と開きて妻は二十八 『来し方行方』(昭和二十二年) 子を抱くや林檎と乳房相抗(さか)う 『美田』(昭和四十二年) 子のための又夫(つま)のための乳房すずし これらの世界も、草城の描くエロティシズムの地平にあるように見える。しかし、草城を批難するリベラルで、民主主義的な中村草田男の良識家ぶりと、教条的な「夫婦」や「親子」に対する想念を真っ当に評価して、これらの俳句を読むと、なにやら極めて矮小で鬱屈した観念の世界を覗いているような息苦しい思いに変容する。あるいは、昭和の十年代というのが、そのように窮屈な時代だったのかもしれないが、草田男は、エロティシズムを観念の牢獄に押し込めようとしたことになる。 妻というものに価値在りし昭和かな 清瀬春夏はタクシーの中で金谷ケリーの手をずっと握りしめていた。結婚という幻想から、現実をみ戻そうとし、若い彼、ノダ君を裏切ることによって、愛する彼を諦めようとしているようにも見えた。しかし、金谷ケリーには結婚という想念がまったく見えない。そして草田男のような結婚に対する思想がまったく理解出来ないでいた。幻想であれ、草城のエロティシズムを信じたいと思った。いずれにしてもどうであれ今夜は、ゆるやかに無条件に、ケリーは春夏の思いの通りにつき合おうと考えていた。それが春夏に対する友情だし、愛情だと思った。ケリーは春夏の手を強く握り返した。 (つづく) |
18 家も車も方舟となる春濁世
身の熱いところ冷たいところさぐる春 清瀬春夏は、勤めているデザイン専門学校で行った、卒業生を呼んでの特別授業のあの日から、ゲストで来たノダ君との関係が続いていた。最近では週に一度は会うようになっている。ノダ君は土曜日の遅くに春夏の部屋に来て、春夏の用意した料理で持参のビールか、ワインを飲み、寝た。夜半にもう一度交わり、明るくなってからまた交わり、そのままノダ君はいつも昼近くまで爆睡した。春夏は遅い朝にそっと一人起きてシャワーを浴び、テレビを小さな音量で点け、コーヒーを煎れてトーストを齧った。それからテレビを消して、ノダ君が起きて来るまでのあいだ本を読んだり、小さなソファでうたたねをして過ごした。自分の部屋に若い男の子がいるというそのことだけで、春夏には満たされるものがあった。 春まだき男は珈琲の香にも起きぬ ノダ君とのことは、綾小路さゆりには話していた。あまり具体的にではないけれど、さゆりが五室剛のことを春夏に話すので、なんとなく少しづつバラすようになってしまった。月に一度くらいの二人の飲み会で、それとなく男友達の情報交換をしている具合だ。時々ゲストも混じったが、女だけの話しは過激になりがちだった。さゆりは五室という愛人がいながら婚活をしっかりと目ざしていたが、春夏にはまだ全てがぼんやりとしていた。でも、ノダ君との関係がこのまま続くとは思っていなかったし、七歳という年齢差によるいつかくるだろう破綻は、覚悟しているつもりだった。窓から見える大きな辛夷の木が、真っ白い花をたわわにひらき出していた。 終わりなぞ数えては生きられぬ辛夷咲く 先週来た時ノダ君は、デザイン専門学校で同級生だった麻生さんが、今度の東日本大震災で津波に飲まれて行方不明になっていることを話した。「麻生さんて、麻生メイちゃん?」「そう、メイ」「ほんと?」麻生さんは元気なかわいい子で、春夏もよく覚えていた。卒業後、故郷の仙台に帰って、デザインスタジオで働いていたが、カメラマンの許嫁が出来て、彼と一緒にモデル事務所を始めることになっていた。その矢先だった。両親と電話で「これから車で逃げる」と話したあと、連絡が途絶えてしまったらしい。その話を聞いてから、テレビでくり返し流れていた津波の映像が、恐ろしくリアルなものに思えた。見たくなくなった。テレビの映像は、原子力発電の事故から、被災者たちの避難生活の情報に変わり出していたが、津波に浮く家屋や自動車のそのひとつに、麻生メイと許嫁もまた閉じ込められ流されたかと思うと、春夏は息が詰まった。 家も車も方舟となる春濁世 ノダ君は今日来たとき、黒いジャケットを着てきた。「麻生の遺体が見つかったらしいので、仙台に行くかも知れない」と、ドアのところで春夏に告げた。それからビールを飲んで、ベッドに入った。春夏はすぐにセックスする気持ちにはなれなかったが、ノダ君はすごく興奮している。それをなだめるようにしているところにケータイがなったのだ。それから二人は気ぜわしく、なにかに追い立てられるように交わった。「死んでしまわないうちに」と、春夏は自分に奇妙な説得をしていた。 ノダ君が着替えているのを春夏は見ていたが、自分でもパジャマを着てベッドから出ると、大きなストールを肩に捲く。立ち上がるとノダ君が春夏を抱きしめた。「行くね、春夏さんの分まで拝んでくる」ノダ君はいつの間にか春夏のことを、先生ではなく、春夏さんと呼ぶようになっていた。ひとつの車に四人でいくのだから、春夏が乗る余裕はある。でもそこまでノダ君と行動を一緒にするのは、はばかられた。「ごめんね、ほんとに私の分まで拝んできてね」春夏はノダ君に念を押す。ノダ君は静かにドアを開けて振り返ると、目で合図するように春夏を見ながらドアを閉めた。足音が少し聞こえて消えた。真夜中、春夏は一人になったと感じた。 なきがらや秋風かよふ鼻の穴 蛇笏 たましひのたとへば秋のほたるかな その男の母が亡くなって、そこに蛇笏が行く。秋風が渺々と吹き込んで来るその部屋に、老母は鼻孔をかっとあけて横臥している。まるでこの冷たい風を胸一杯に吸い込んでいるようではないか。 芥川は、友人に蛇笏の魅力を語られるが、最初は一向に興味が持てずにいた。ところがしばらくして、蛇笏の力を知る。両者は双方の俳句を評価する仲になる。蛇笏は自殺した芥川への、それでもその魂を秋の蛍のようにはかなく、しかし輝いていたことを惜しまない。 水洟や鼻の先だけ暮れ残る 龍之介 有る程の菊抛げ入れよ棺の中 漱石 雪はしづかにゆたかにはやし屍室 波郷 芥川は、水洟の句を辞世の句のように語られているが、生前からこの句を揮毫しているらしい。お気に入りの句なのだ。「自嘲」と前書きの有るこの句は、芥川自身の死への弔いとも読まれている。「鼻」が人間にとって動物的な名残ということから、洟を垂らしているその鼻先の他は、自分の野生はまるで死んでしまっているようだと言っているのだ。そしてついに、ヴェロナールとジャールを致死量飲んで死ぬ。 芥川が私淑していた夏目漱石も、松山での正岡子規との知遇で俳句にのめり込んだ。修善寺で吐血し療養中の漱石のもとに、可愛がっていた小説家、歌人の大塚楠緒子の死の知らせが入る。自分は弔いにも行けないがせめて、有るだけの菊の花を棺に入れてくれないかと訴えている。 石田波郷も自分の病と闘い続け、それを俳句に多く残している。療養所にいて今日もまた、一人逝った。その遺体安置室の寒々とした光景を舞い降る雪のなかに描写する。いずれ私もあの部屋に横たわるのだろう、という諦念と恐れにも読める。今度の震災には特別な屍室などない。学校の体育館や、ボーリング場、そして納められるところもなく、路傍に横たわる屍もあるという。 むざんやな甲の下のきりぎりす 芭蕉 塚もうごけ我泣声は秋の風 愁ひつつ岡にのぼれば花いばら 蕪村 松尾芭蕉の弔い句は激しい。『おくのほそ道』から二句。老将斎藤実盛が源義朝より賜った兜が小松の多太神社も納められている。それを観に行くと兜の下からきりぎりすの鳴き声が聞こえてきた。討死した実盛の無念さに芭蕉は共振する。同じく金沢で、可愛がっていた若い弟子の一笑に、折角会えると思って訪ねたのに亡くなっていた。その驚きと悲しみとで墓参した芭蕉の激情が現れる。「今吹いているこの秋風の音は、私の泣声だぞ、聞こえるか!」と叫んでいるのだ。 しかし与謝蕪村の句はやさしい。下総国結城(茨城県)の友人、早見晋我(北寿)の死を悼んでの句。おろおろとなす術もなく歩き、気がつくと丘に登っていた。しかしそこには鮮やかに野薔薇が咲き乱れている。まるで晋我と浄土で遭遇しているようではないか、と自らを慰めている。 燭の灯を煙草火としてチエホフ忌 草田男 燭台に灯る蝋燭の火で煙草をつけるという中村草田男は、まるでハンフリー・ボガードのようなカッコよさだ。その日はチエホフの命日だった。「忌俳句」は、文人の命日をきっかけに詠む俳句だ。しかし著名な文人の命日ではなくても、すべての日は誰かの命日なのだから、すべての俳句は「忌俳句」でもある。三月十一日は、メイと許嫁の忌でもあり、同時に亡くなった多くの人の忌でもある。清瀬春夏はぼんやりと本を閉じた。 しかし、人の死によって自分の現在に覚醒するということもあるのだと思った。若くして連れ合いを失い、寡婦となった桂信子のいくつかの俳句がそうだ。 ふところに乳房ある憂さ梅雨ながき 信子 窓の雪女体にて湯をあふれしむ 自分は愛する人を失っても、体は若い女のまま。そのことがかえって、私を悲しませます。この長梅雨の時期はまして。この乳房のやりようのない存在感に、春夏は衝撃を受けた。そして、その肉体をして信子は別の雪の夜、一人湯船につかる。もうそれは乳房でなく、自分の体すべてが満ちているというのに、自分はひとりだという現実を受け止めようとする。だからこそそこに濃密なエロティシズムが醸成される。
真夜の湯の春の方舟われひとり (つづく) |
メールの着信音がする。綾小路さゆりは腕をのばしてベッドサイドのテーブルに置かれたケータイをとった。薄いアンダーウエア一枚のさゆりの胸の下に、五室剛の寝顔があった。五室は覆い被さってきたさゆりの背中にゆっくりと手をまわすと、その胸を自分の顔の方に引き寄せた。唇がアンダーウエアの上から乳首を探して乳房をはう。そうさせながら、さゆりはメールの返信を打った。「終わった?」と五室は言った。「ええ、庭博士からでした。ガルデンカフェに行くけど来ないかって」「それで」「彼が来ているので行けないと、返信しました」「いいの?」「いいの。庭博士は私の婚活の応援団長だから」「でも私は婚活の相手としては不適当かも知れない」「そうだけど、彼は彼です」「彼、」と言いかけて五室は黙った。 庭博士については、五室とさゆりの会話に時々登場した。庭園学の研究者で、自らもガーデン設計に携わったりもしていた。ガルデンカフェもそのひとつで、さゆりの住んでいるところから一駅となりにあった。小さな庭を囲んだ居心地のよいカフェだった。庭博士は数十名のガーデン愛好家のサークルをつくっていて、日本中の名庭巡りをし、時には外国にもメンバーを連れて行った。さゆりもときどき東京の庭園を庭博士たちと廻っている。 さゆりが数年前に婚活宣言をした時から、庭博士は色々アドヴァイスしてくれるようになっていた。しかし相手を紹介することはなかった。庭博士とは親子ほど年が違っていたが、さゆりを娘のようには見ていなかった。明らかに女性としての興味を現した。二人きりになると強くハグしてきた。さゆりも無理に拒否せず、応えて抱き返した。勿論このことは、五室に話さないでいたが、そういう時はかならず、橋本多佳子の「雪はげし抱かれて息のつまりしこと」という句を思い出した。 さゆりの太腿が触れている五室の股間が昂まっているのを識ると、さゆりは起き上がって、五室に跨がりゆっくりと迎え入れた。背中を反らせて上下に小さく動いていると、五室の両の手がアンダーウエアをたくし上げて、ゆったりと揺れる乳房を下からしっかり握りしめてきた。さゆりの乳房は美しい紡錘形をしていた。薄紅色の乳暈も小さく、乳首はくわえるのがはばかられるほど、若々しく膨らんでいる。五室はさゆりのからだが好きだった。しばらくそうしていたが、五室はさゆりの肩を抱いて胸を合わせ、態を入れ替えると、上になってしっかりとからだを入れ直し、激しく動いて果てた。下にいるさゆりは五室の背中を抱きしめていた。五室はごろりと上向きに寝た。しばらく大きく息をしていたが、おさまるのを待ってさゆりは起き上がり、五室の腹の上に溜まった精液をティッシュで拭い、まだ勃起しているペニスと、それから自分を拭った。五室はかすれる声で「ありがと」と言った。 月と雲とまた上になり下になり 「庭と言えば、俳人はよく庭を詠んでいますね。ごく身近な自然の空間ですから、それをジッと観察しているだけでも、俳句になります。 鶯や餅に糞する縁のさき 松尾芭蕉 秋深し隣は何をする人ぞ 古庭に鶯啼きぬ日もすがら 与謝蕪村 桃源の路地の細さよ冬ごもり 牡丹散て打ちかさなりぬ二三片 鶯の啼くや小さき口あいて 妹が垣根三味線草の花咲きぬ しら梅に明くる夜ばかりとなりにけり 是がまあつひのか雪五尺 小林一茶 涼風の曲がりくねつて来たりけり 痩蛙まけるな一茶是に有り いくたびも雪の深さを尋ねけり 正岡子規 鶏頭の十四五本もありぬべし 糸瓜咲て痰のつまりし仏かな 赤い椿白い椿と落ちにけり 河東碧梧桐 いくらでもありますが、どれも何となく似ていませんか。日本の庭というのはほんとうに小さい宇宙だったんですね。植物と、小さな生き物しかいません。芭蕉も蕪村も鶯を詠んでいますが、似てるでしょう。蕪村は芭蕉を高く評価していましたから、勿論、意識してつくっていると思います。庭には鶯がよく似合う。それと春が来たというよろこびでしょうかね。梅に鶯というけれど、梅もよく詠まれる。蕪村の「しら梅に」は絶句と言われていますが、体も衰えて、庭先の白梅ばかりを見ているだけの毎日ですよ、と言った感じでしょうか。「妹が垣根」は、祇園の妓女、小糸との恋が終わる頃、彼女の家のまわりをほっつき歩いている。すると、垣根にペンペン草が生えている。まるで小糸のような可憐さでね。未練なんですね。「桃源の路地の細さ」も、一茶の「是がまあ」や、「涼風の曲がりくねつて」も、閉じ込められた空間に、あきらめにも似た気持ちで、何かがやって来るのを待っている。子規は晩年病床にいて、庭ばかり見ている毎日だった。鶏頭の花が咲けば鶏頭を、糸瓜が咲けば糸瓜を。絵も描いていますね。なにしろ写生の人ですから。雪が降ればどのくらい積もったかを、頻繁に家人に訪ねている。松山の人だから、積もるほどの雪が珍しかったんじゃないでしょうか。碧梧桐の「赤い椿白い椿」も、蕪村の「牡丹散て」にまったく重なりますね。時間の流れを確認し、心の疲れを再生するそんな装置でもあったんでしょうね。そう考えれば、さゆりさんは確かに私の庭なのかも知れない。そして、小さいのにいつも迷い込む。迷い込みながら満たされて行く」 「なんか高級な感じがして、ありがとう。でも私、膣前庭というのを持ってますから、そこが私の庭。小さな宇宙の入り口かもしれませんね」「凄い発見です。私はいつもその庭先に立ち、そしてあなたに入って行く」 膣前庭という小さき花の宇宙あり さゆりの婚活はやや低迷していた。五室がいることも、庭博士も遅延の理由だったかも知れない。すこしずつ満たされているということが、飢餓感を弱めていた。しかしさゆりは、一緒に生活するパートナーをあくまでも求めていた。多くの人と人生を一緒にやるチャンスはあるけれど、誰でもいい訳ではない。選ばれる人間は限られる。それは心の芯に熱いフィラメントが灯るような感覚があるかどうかだ。さゆりはその微妙な光の振動のようなものに、神経を集中するようになっていた。予兆のようなものはあった。 「わたし結婚するかもしれません。人生を一緒につくる人がやっぱり欲しいですから」「私じゃだめ?」「だめです。五室さんの生活を壊したくはない」「ただ愛し合う関係、でいいですか?」「そうですね、まあシンプルに」「身勝手な関係であることは十分に承知しているし、さゆりさんの人生の邪魔をするようなことだけは、したくない」「いいえ、私こそ。ありがとう。そういう五室さんが好きです。でも、やっぱり結婚はしたいんです」五室はさゆりの大きな胸の間に顔を埋めた。すこし湿っていてラフランスのような匂いがした。五室はこの匂いが好きだった。 胸の谷の発酵激しラフランス 五室はさゆりに陰茎を握らせ、自分もさゆりの陰毛の上に手をおいていた。「二週間も会わないと、辛い」「からだが欲しいだけで?」「からだを求めることは、重要なことだよ。もしかしたら、御飯よりも。メシは自分一人でも食える」「あなたは、ワインやケーキを持ってきてくれるわ」「でも、タタリガミにやられたアシタカみたいにぐったりとしてね」「そうでもない。でもそういう時は、からだで癒されるしかないの?」「そう。さゆりさんのからだの中で回復して行く」「ふーん、私はつまり五室さんの回復装置なんだ」「いや、神、観音様のような力を感じる」「そう、そうならいいですけど」 五室はさゆりのなだらかな曲線を手のひらで確かめ、ふたたび太腿のあいだの闇の中に滑り込ませた。さゆりは足をよじるように閉じる。 「でも、すぐに五室さんとは別れるわけではないわ。この先どうなるかわからないけど。ずるいですか、こういうの?」「いや、とても現実的だと思うし、私も助かる。というか、さゆりさんをほんと愛しているから、このままであればと」「ありがとう、このままかどうかはわからないけど。そんなこと言ってくれるの、五室さんだけです」 さゆりは蒲団に潜り込み、大きくなった五室の陰茎をくわえ、陰嚢を強く揉み出した。五室はさゆりの頭が蒲団から出るようにずらし、さゆりの背中をゆっくりと撫でる。恍惚という言葉があるとしたら、きっとこういうことなのだろう。 腿の淵の闇紅ければ兎哭く その頃、ガルデンカフェには庭博士が一人到着していた。遅い朝のコーヒーとスコーンを頼み、持って来た本を広げる。しかし庭博士はまったく活字を追うことが出来なかった。同じページを開いたままだった。庭博士は燃えつきた炭のように沈黙していた。ガルデンカフェの庭には、消えるために落ちてきたようなあわ雪が、舞い始めている。ガルデンカフェの庭が、ゆっくりと湿り出していた。 とまどいのとどまらぬ雪とける庭 (つづく) |
|
16 一行の冗談でよし骨砕く 「先日久し振りにフォーラムなんていうものに出かけてね、いや、友人が出ていたんでね。その時の話が面白かった、というかちょっと、ショックだったね」 「どうしたっていうんですか、ずるるさんに限って、そんな」 「それがさ、花鳥さん、『死のデザイン』ていうタイトルでさ、こんなしょうもないフォーラム誰が聞くのって思っていたけど、結構人が集まってるのよ」 「それって、葬儀屋、焼き場、墓石屋、墓地屋なんかが結託した、企業陰謀なんじゃないですか」 「ボチ屋ねー、今はお墓をつくるのも大変だものな。いやそれがれっきとしたデザインフォーラムで、デザイナーや、プロデューサーが話してるんだよ」 「あー、そっち系でずるるさんとつながっている訳だ。すみません、お酒」 「あいよ、李白ね。それでね、その著名なディレクターが、友人の通夜に駆けつける。でね、お棺のなかを見てビックリよ」 「自分が入っていたとか? それじゃあ『らくだの馬さん』ですよね」 「うん、その人はね、六十くらいなんだそうけど、オシャレな人でね、藤田嗣治みたいなボブカットで決めていたそうだよ。それがさ、お棺のぞいたら、なんとオールバックなんだってさ。そのディレクターは相当ショックを受けたそうだよ。人の死を勝手に葬儀屋がいじってしまうってことにね」 「どうしようもないことだと思っているけど、そういうのはいやですね、やっぱり。なんとかなるんだったら、なんとかしたいですね」 「きっと、闘病で髪や髭が伸び放題なんて現実はあったんだろうけど。それにしてもね、処理がイージーだよな。まあ、映画の『おくりびと』みたいに徹底してやられてもね、と思うけど」 「そうだそうですよ。あんなにしつこく入棺の儀式をやられると、実は家族が参っちゃうらしいです。ささっとやらないとやっぱ、気色が悪いというか」 「なるほどね、そうかも知れない。あれもまあ、葬儀屋のマニュアルというか、営業だからね」 ボブカットほどのオシャレも出来ず通夜の棺
「わたしさ、十五年ほど前に韓国の民俗村で、占いのお婆ちゃんに見てもらったんだけど、七十九歳まで生きるっていわれてね。その頃はまだ三十年生きるんだなんて思っていたけど、いまじゃあ十五年チョボチョボで死ぬのかって。ちょっと考え始めたね」 「どんなふうに考えてるんですか?」 「最近さ、遺言預かるのあるじゃない。銀行とか、生命保険会社なんかがさ。あれって、財産とか借金があればってことで。わたしはさ、死んで家族親類にツベコべ差配するほどのこともないしね。どういう死に方するかわからないけど、でも、葬儀という自分の最後のイベントには、少々興味を持ち出したというか」 「ははー、そんなもんですか」 「結局さ、誕生の時も、葬儀の時も、本人の意志がまったく通用しない。まあそういうもんだと思えば、そんなもんなのだろうけど。いい葬式っていうのは結構ないでしょ」 「先日、あたしのお世話になった税理士のエライ先生のお別れの会がTホテルでありましてね、相当な人が集まってました。で、献花の時になっていきなり会場のコンチェルトが『長崎は今日も雨だった』をしめやかに演奏し始めて、それからずっと演歌。先生、カラオケが好きだったんですよ。おかしいやら、かなしいやら、変なもんでした」 「それ、六〇点。ホテルの葬儀担当のやりそうなことだね。でもさ、いかにもじゃない。遺族にリサーチして、演歌をコンチェルトで、なんてね。ホテルのバンケット課というのは毎日、新聞の死亡欄、企業の人事欄見ていて、すぐに連絡がはいるそうだよ。それこそ叙勲なんていったら、ホテル間で宴会の大争奪戦になるらしいからね」 「まあ、お別れ会やるような人はそれとして、あたしたちは一回きりの葬式ですか」 「そりゃあ、みんな忙しいから、通夜、告別式に間に合わないということが多くて、それであらためてのお別れ会となる訳だけど、私は一回こっきり、通夜と告別式に全力投球だね。来れなかった人が悔しがるみたいなことやりたいね」 「あたしもそっち、賛成!」 焼き場まであと半日の宴かな 「いい葬式といったら、寺山修司の葬式は秀逸だったね、葬儀委員長が谷川俊太郎、司会が篠田正浩、山口昌男、山田太一、唐十郎と弔辞。祭壇は今のかいぶつ句会のエノモトがやってたね。最後にさ、劇団員全員で『レミング』のテーマソング『世界の果てまで連れてって』の大合唱。わたし声出して泣いちゃった。それから、アラーキー(荒木経惟)の奥さんの陽子さんの葬式ね。通夜は、中上健次なんかと大カラオケ大会になったそうだけど、寒い日の告別式、寺の前廊下に立ってね、陽子さんの真っ赤な長ーいマフラー首に巻いたアラーキーが、延々としゃべった。これも嗚咽したよ。イラストレーターのペーター佐藤の通夜は、ペーターの歌う歌が流れていた。これは都はるみの演歌から、流行歌ばっか。もともと東京キッドブラザースだからさ、歌うまいんだ。イラストレーターのナベゾ(渡辺和博)は、お棺の中でもちゃんとメガネかけて、アイビーカットだった。変わったところでいえば、萩原葉子さん。二、三十人の近親者だけの密葬でね、お棺に入った葉子さんを囲んで座っているだけ。無宗教の葉子さんの好きだった、古賀政男のマンドリン曲が流れてるの。父親の朔太郎はマンドリンの名手だったそうだけど」 「すごいですね、ずるるさん、ちょっとした葬儀評論家ですよ」 「いやいや、そんな経験があのフォーラムで火がついたってのかな」 ご遺体という名残にかける言葉もなし 「絶句ってあるじゃない。 旅に病んで夢は枯野をかけめぐる 芭蕉 しら梅に明くる夜ばかりとなりにけり 蕪村 みたいなさ。芭蕉はもう精霊化しているね。空飛んじゃってるから。蕪村といえばさ、夜が明ければ庭先の白梅が咲いているのが見えるばかりです。紅梅が咲くまで庭を見ていることができるだろうかとね、末期を悟ったような心境だね。絶句じゃないけど小林一茶の、 是がまあつひの栖か雪五尺 一茶 なんかは、諦念というか、死んでいくライフスタイルを決定しているよね。 糸瓜咲いて痰のつまりし仏かな 子規 をとといの糸瓜の水も取らざき 痰一斗糸瓜の水も間にあはず 正岡子規は三句残っているけど、「痰のつまりし」については書いている様子がリアルに記録されているね。死ぬ間際の息絶え絶えの状態で、子規は筆を取っているのがすごいけど。これは香川照之が『坂の上の雲』でどう演じるか見ものだね。これだけ糸瓜でせめれば、「糸瓜忌」になるでしょ。ほかの人の絶句は、最晩年の作から選んだりしているのも多いようだけど。 独り句を推敲をして遅き日を 虚子 もりもりもりあがる雲へ歩む 山頭火 高浜虚子は最後、俳句を丹念に書いているさまを残しているけど、虚子は多作だし苦しんで作品を書いてる感じないよね。どこにもネガティブな印象がない、堂々としている。そこが偉すぎて、強すぎて、いやみでもあるけど。反対にネガティブな種田山頭火の絶句は、なんか希望に満ちてるんだよね。しかしゆっくりと積乱雲の向こうに昇天していくふうにも読める」 絶句ほどに気張る間もなく息の絶え 「俳人は、絶句を残して人生を総括するけれど、死ってさ、ほとんどの人が人生を急激な右肩下がりで終わらせるじゃない。で、結局、自分の死を悔やんだり、怖がったりするんだね。しかしそれを楽しみにする唯一の対応策が『死のデザイン』ってわけよ。みんなビックリするだろうなーと思うと、わくわくするじゃない、死ぬのが」 「で、ずるるさん、なに企んでいるの?」 「それは内緒さ、じゃないと面白くないでしょ。わたしの死んだ時のお楽しみ」 「そんなこといって、十五年も前から準備しても、プランが時代遅れになりはしませんか」 「そう、だからこれから『死のデザイン』をどんどん更新していくの。忙しくなるなー」 一行の冗談でよし骨砕く (つづく) |
|
15 ひとりでいる 黙っている デザイン専門学校の後期の授業が始まって気ぜわしい一ト月が終わり、ふっと一息ついた清瀬春夏と綾小路さゆりは、研究室の片隅にある会議用のテーブルでランチしている。二人の間には『よむ花椿 no.724』が置かれている。穂村弘の連載ページ『穂村の文(あや)』が開いてあった。『「あるある」の源』という一文で、せきひろ・又吉直樹著の『カキフライが無いから来なかった』(幻冬舍刊)の新しい自由律俳句を評している。 「穂村弘ってセンスいいでしょ。 「酔ってるの?あたしが誰かわかってる?」「ブーフーウーのウーじゃないかな」 卵産む海亀の背に飛び乗って手榴弾のピン抜けば朝焼け ハーブティーにハーブ煮えつつ春の夜の嘘つきはどらえもんのはじまり サバンナの象のうんこよ聞いてくれだるいせつないこわいさみしい 終バスにふたりは眠る紫の〈降りますランプ〉に取り囲まれて 眼をとじて耳をふさいで金星がどれだかわかったら舌で指せ ハロー 夜。ハロー 静かな霜柱。ハロー カップヌードルの海老たち このばかのかわりにあたしがあやまりますって叫んだ森の動物会議 みたいのが、穂村さんの代表作だって、ウェブには出ていたけど」 「それなら、俵万智の、 「嫁さんになれよ」だなんてカンチュウハイ二本で言ってしまっていいの みたいだし、笹公人の、 「ドラえもんがどこかにいる!」と子供らのさざめく車内に大山のぶ代 なんかと近いね」 「いえてる。一九八六年の角川短歌賞を俵万智が『サラダ記念日』で獲った時に、穂村さんは残念、次席だった。まあその頃から口語短歌の騎手でもあるわけね」 「さゆりさん詳しんだ、短歌に。驚いた!」 「短歌って、俳句のお兄さんみたいなものでしょ」 「さすが、五室剛さんは教育者だね。さゆりさん変わったもんね」 「うれしい、ほんとにそう思う?」 「ほんとだよ、それにきれいになった」 などと話しながら、二人はテーブルの上の『よむ花椿』を覗き込む。 せきしろの作品 素振りをしている人がいるから回り道をする またカット世界チャンピオンの店だ あの猫は撥ねられるかもしれない 落ちた歯磨き粉ここで一番白い 手羽先をそこまでしか食べないのか 喧嘩しながら二人乗りしている 又吉直樹の作品 座席を倒すタイミングを失った 登山服の老夫婦に席を譲っても良いか迷う へんなとこに米が入って取れない このカルビは少し僕よりにある 坊さんが大量にアイスを買っていた 独りなのに天狗の面をつけてしまった 「なるほどね、でも、何となく物足りなくない? オシャレで、シャイな観察眼って感じだけど。ちょっと草食系だよねやっぱ、感性が」 「穂村さんはね、こう言ってるの。——一行一行が「自由律俳句」、と云われなければ気づかないだろう。多くはいわゆる「あるある」的ネタにみえる。「あるある」なら誰にでも書けるかというと、そうはいかない。誰でもが納得するような「あるある」を、巨大な世界の中から浮かび上がらせることが出来るのは、限られた人間の眼差しだけだ。二人の作家の視線はサーチライトのように鋭い―—ってね」 「ふーむ、自由律俳句ですか。こんなんなっちゃったんですか」 「穂村さんは、『あるある』は、ネガティブで小さな出来事のなかにあるって言っている。ではなぜそれが『あるある』感を浮上させるのかというと、みんなも自分と同じように一瞬一瞬を戦っている、という実感をもたらすからだと思うって。そうじゃない?」 「わたしは一瞬一瞬戦っているなんで実感まったくないけど。というよりも、穂村弘は、この二人の自由律俳人に、あるいは版元の幻冬舍に、友情、ないしは義理でもあったんじゃないの。それとも穂村弘、原稿のネタに困ったとか」 「そんなことないでしょ、春夏ちゃん。これは穂村さんの短歌にも共通する、現代の言葉の信号みたいなものを私は感じるわ」 「そう、私には、ちょっと小ジャレたコピーみたいにみえる。だいたい穂村弘が言う『誰でもが納得するような「あるある」』って言うのはさ、ポピュリズムだよね、大衆迎合主義。まあそんな文芸があってもちっともかまわないけど。自由律俳句って、俳諧から俳句へと改革した正岡子規の弟子の、河東碧梧桐あたりから始まる、新傾向の俳句革命でしょ。山頭火や放哉が泣くよ」 「それが今、よみがえり出しているのよ」 河東碧梧桐は、明治三十八年、正岡子規が勤めていた新聞『日本』の俳句の選者となる。子規の俳句改革をさらに進めるべく、新傾向俳句へと展開を始めるのもこの頃からだ。しかしすぐに自由律俳句に入ったわけではなかった。五七五の定型から、五五三五、五五五三の形式を打ち立て、実感を主とし、印象を重んずる、個性と主観を基調とした俳句を提唱する。つまりこれは、子規の言う客観写生の精神とはずいぶん違う、俳句における印象派の始まりのようなものだった。一方、同じく子規の門下で、明治三十一年に『ほとゝぎす』を東京に移して発行する高浜虚子は、しかし自身の活動は小説中心に転じていた。 碧梧桐は、明治三十九年から「三千里」と銘打って全国俳行脚に出る計画を立てる。新傾向俳句の一大デモンストレーションである。これには反響が大きかった。京都東本願寺の法主、大谷句仏の援助を得て、いよいよ全国周遊が始まる。短詩系文芸の基本は旅なのか。碧梧桐もまた、西行、芭蕉、子規に導かれるように旅に出る。この俳行脚は四十四年まで続く。その思想は、海南新聞の俳句選者、森田雷死久を中心に愛媛県下に広がり、全国的には大須賀乙字、中塚一碧楼、荻原井泉水らの新傾向作家を輩出することになる。なかでも、東京生まれの井泉水は、麻布中学時代から俳句を始めていたが、東京帝国大学文学部言語学科卒業後、碧梧桐の協力を得て四十四年に『層雲』を創刊し、ここに新傾向俳句の拠点が確立、ここから本格的な自由律俳句の運動が始まるのだ。 井泉水は、極めて論理的な頭脳で、「俳句の全数はパーミテーションの式による四十八字の十七乗という限られた一定の数になる」として、その量的限界を明解にする。コンピュータリゼーションの現在であれば、そのすべての俳句をいち早く言語化してしまい、俳句を終わらせていたかも知れない。しかしどうだろう、例えばスカイツリーをコンピュータで計算して建築するのと、百年かかってもあくまでもハンドメイドで、建て続けるバルセロナのサクラダファミリア大聖堂では、俳句という文芸は、圧倒的に後者の世界に近い。数理の定理で完結するのではなく、億の単位の人の創造力で築き上げるそんなものなのだろう。事実、四百年かかった今も、まったく完成していない。あるいは、「俳句の塔」はすでにとっくに築かれて、われわれはその補修修復作業をしているだけなのかも知れないが。 河東碧梧桐の作品 芒(すすき)枯れし池に出づ工場(こうば)さかる音(ね)を 曳かれる牛が辻でずっと見廻した秋空だ 榾(ほだ)をおろせし雪沓(ゆきぐつ)の雪君に白くて 荻原井泉水の作品 力一ぱいの泣く児(こ)と啼く鶏(とり)との朝 空をあゆむ朗朗と月ひとり 遠くたしかに台風のきている竹薮の竹の葉 この頃、こうした動きを牽制して、高浜虚子は俳句に復帰専念、季語を入れて五七五でまとめる伝統的な有季定型俳句を守ろうと動き出した。大正二年の三田俳句会での一句。 春風や闘志いだきて丘に立つ これは、新傾向俳句に立ち向かう決意表明の作品とされているが、世界に並ぼうとしてモダニズムに湧き立つ当時の日本で、守旧派を任としたのは、同胞だった碧梧桐への反発、あるいはモダニズムへの抵抗であったのだろうか。しかし結果、虚子は圧倒的に現代俳句の巨星になっていく。 それには幸いなことに、碧梧桐も、井泉水も、その抱えた近代思想に作品が追いついて行かなかったことがある。近代の印象派どころか、俳句のヘドロに足を引きずり込まれたまま、あがいているようにすらみえる。この運動にもし、井泉水の一高時代の同窓の尾崎放哉や、さらには種田山頭火の参加を得られなければ、ここで無惨にも新傾向俳句は終焉していただろう。それでなくても、この事実は、この後に起こる何度かの俳句改革の、「挫折」のトラウマにすらなってしまったのではないだろうか。
「さゆりさんに言い過ぎちゃったかな。でもやっぱり、自由律俳句は、放哉と、山頭火ってことになるでしょ。二人とも、そんなに好きではないけど」 家に帰って春夏はぽつりと思った。二人が好きだった酒をテーブルの上に出した。俳句の本を広げた。それにしても、現代俳句のアンソロジーにも、二人の作品はしばしば取り上げられないことがある。俳句の世界からゆるやかに排斥されているのだ。それは、排斥するだけの価値があるからだろう。俳人に放哉や山頭火の支持する者は少ない。これは禁書に近い扱いでもある。 尾崎放哉の作品 咳(せき)をしても一人 なんにもない机の抽斗(ひきだし)をあけて見る すばらしい乳房だ蚊が居る 墓のうらに廻る 肉がやせて来る太い骨である 入れものが無い両手で受ける 種田山頭火の作品 分け入つても分け入つても青い山 鴉啼いてわたしも一人 どうしようもないわたしが歩いてゐる 雨ふるふるさとははだしであるく あるけばかつこういそげばかつこう うしろすがたがしぐれてゆくか 清瀬春夏には、この夏ちょっとした異変があった。授業の新しい試みとして、NHKの番組『ようこそ先輩』を真似て、卒業生を招くイベントをした。その一回目にやってきたのが、人気アートディレクターのスタジオで働くノダ君だった。卒業して七年、二十七歳になっていた。授業が好評のうちに終わり、学生と先生数人で呑みに出た。学校の近くにある焼き鳥屋だった。ノダ君は懐かしそうにビールをお替わりした。焼酎もロックでぐいぐい呑んだ。話しも盛り上がり、二軒目の店を出た時には、十一時近くになっていた。店を出るとノダ君が、「春夏先生、もう一杯付き合ってください」と切り出した。まわりの先生や学生が冷やかしたが、春夏は堂々と誘うノダ君に好感を感じた。少し自慢でもあった。「よし、つき合ってやる!」うなずいて笑った.二人きりになった。 それから、目黒の小ジャレたバーに入った。暗くて落ち着けた。「ノダ君、君、草食系だと思っていたけど、結構、肉食系になったんだね」「誘うだけじゃあ、肉食系じゃないですよ。ちゃんと食べないとね」「そうか、そういうことか。で、ノダ君、ちゃんと食べてるの?」「全然食べてませんよ。忙しくて」「可愛そうね、それは」「夜中になってから、会ってくれる人なんていませんから」「そうかな、好きなら待っていてくれるんじゃない」「そうですかね。先生だったら待っててくれますか?」「好きだったら、待つかな」「オレのことをですよ」「ノダ君を? ちょっと待ってよ」「いいですよ、待ちますよ。でも、ちゃんと答えてください」「なに言っての!」春夏は声を立てて笑った。しかし、ノダ君が結構本気らしいことに、春夏は驚き、少しうれしくうろたえた。 その夜にあった出来事を、その後に続くノダ君とのことを、春夏は思い出しながら、テーブルの端においてあったパソコンを開いた。 なにが邪魔しているのか 十分に彼が好きかも知れない 元教師元学生という愛人たちになるのか 七歳という年の差が好奇心で曖昧化しはじめる 性欲のためにタクシーに乗った 逡巡しているのに止められないものがあふれる キスをするとわたしのどこかが牝になっている 服は自分で脱ぐ 決意表明のように 下着は脱がない 最後の関門を用意してやる ベッドがでかい レスリングも出来そう すぐに風呂に入るのは醒める 年上のしなくてはいけないことをさがしている 裸のからだをほめてくれる 熱くなる 体の匂いをかぐ 匂いをほおばる 自分でも乳房が大きくなっているとおどろく ゴムの木のようにしなやかに 樹液があふれる なめられながら 君やさしいんだねと思う 集中したいのにいろんなことを考えてしまう 君のからだは男のからだどおりにできている こんなにきもちのよいものだったっけ こんなにひらききってしまうものだったの こんなにこすれあったりしたかな かんがえがどんどんひらがなになる 感謝していた わかれる頃には空が真っ青 断れないことが 自分の欲求ということか でもなんとなく 時々断っている みらいのこと いま見えないでいる 見ないでいる ひとりでいる 黙っている 膣をひとりで絞めてみる 清瀬春夏はそこまでパソコンにたたいて、何度か読み返し、やっぱり自由律俳句には未来はないなと考えた。いや、そうじゃないか。わたしは結構ぱつんぱつんに精一杯なのに、それがどうしてこんなにヘボい叙事詩になってしまうのかっていう問題かな。春夏は、ひとりで笑った。グラスに残った酒を飲み干して、それからすべての文章を削除した。 (つづく) |
|
14 竹売りの竹に絡まる天の川 「このしょぼい商店街も、六月の中旬から七夕。ピンクやブルーのビニールの飾り下げて、一瞬お下品な、北朝鮮みたいになるでしょ。東京は七月七日、七がふたつ並ぶから、スロットマシンの777の兄弟みたいに、ちょっとラッキーみたいな感じがあるけど、やっぱり旧暦で体感しないとなあ。七夕のよさって感じないよね。旧暦だと今頃の八月七日、正確にはもっとあとになるはずだけど、夏の終わり、秋の始まり。笹の葉が風に揺れて乾いた音を立てはじめる」 陳蕎麦(ひねそば)ずるるは、店の窓の外の湿気を含んだ夕闇をみながらつぶやく。 「それにしても、ななゆうって書いて、どうしてたなばたって読むんでしょうね」と、金谷ケリー。 「機織り機の棚機(たなばた)から来ているのは間違いないけど、七月七日の夕方くらいの意味じゃないの。棚機を七夕って書いて、たなばたって読ませるところなんか、ちょっと江戸時代っぽいシャレだよね。中国で始まったお祭りなのにね」 「となると、中国では七夕とは書かない」 「ちょっと待ってよ」といって、ずるるは店の奥に引っ込むと、文庫本サイズの紫の箱に入った季寄せを持って出て来た。 「いやいや、さっきのは私の勝手な推論。ツイッターに書き込めば、新しもの好きの中国文学者が書き込んでくれるかもね。あるいは村上春樹がみていて、やれやれ、なんてつぶやいてくれるかも知れないけど」 山本健吉篇の季寄せ二分冊、濃緑のカバーの春夏篇を開いた。 「季寄せなんか見るんですか」 「もちろん、これでもトホホギス同人だからね。季寄せと言えば、清瀬春夏ちゃんどうしてる?」 「さあ、最近あってませんから」 「ふーん、七夕みたいにか。あれない。やっぱり秋なんだ」と言いながらえび茶色の秋冬新年篇を開く。 「あったあった。七夕、陰暦七月七日(東京では陽暦、地方によっては八月七日)、あるいはその行事。夏と秋の交叉(ゆきあい)の祭りで、棚機つ女(たなばたつめ)が神のために機を織った。奈良時代に漢土の乞巧奠(きこうでん)がこの行事に習合し、星祭が行われた—やっぱり、中国では七夕じゃない。それに晩夏の祭りかと思ったけど、秋祭りなんだね」 「でも夜の星祭りなのになんで夕なんでしょうね」 「確かに夕べは夜の始まる時間だけど、夜という意味もあるんじゃない。まあ夜が待ちきれなくて、薄暗くなり始めた頃から天の川の輝き出すのも待っている。待ちどおしくお迎えするって気持ちじゃないだろうか」 「待ちどおしいって気持ち、いいですよね」 七夕や星見えぬ夜の秘めしこと ずるる 近づくも交りもなき夜川の端 ケリー 「続きを読む。七夕のころ、鷲座のアルタイル、すなわち、牽牛星(けんぎゅうせい)・彦星(ひこぼし)・犬飼星(いぬかいほし)・男星(おぼし)・男七夕などと言われる星と、琴座の主星ヴェガ、すなわち織女星(しょくじょせい)・妻星(つまぼし)・女星(めぼし)・機織姫・棚機姫・女七夕(めたなばた)などと言われる星が、天の川をへだてて接するので、年に一度の会う瀬にたとえた—とあるね。それぞれ対になった呼び名があるけど、すこしづつドラマが違ってくるよね。私なんか、ヴェガといわれちゃうと、女ばっかの現代詩の同人誌『ゔぇが』を主宰していた吉原幸子を思い出すね。大人の女に憧れてたのよ」 「歴程賞、室生犀星詩人賞、高見順賞、萩原朔太郎賞受賞者。『幼年連』持ってますよ」 「うれしいね、ケリーちゃん。さすが少年詩人崩れのコピーライター!」 「少しも褒められた気持ちになれないね」 「二星(じせい)・星合・星迎・星の契(ちぎり)・星の恋・星の別。笹につけた人形を祓え流すという考えから、七夕竹を立てて、七夕送り・七夕流しと言った。七夕竹売。竹には短冊などに歌などを書き、芋の葉の露で墨をすって字を書く風がある。七夕棚・七夕雨・鵲(かささぎ)の橋・七夕紙・七夕色紙・短冊竹—」 短冊の笹音天の川の音 ケリー 竹売りの竹に絡まる天の川 ずるる 「芋の葉の露と言えば、やっぱり飯田蛇笏の『芋の露連山影を正しうす』でしょ。これって七夕の句だったんだね。芋の葉といっても、里芋みたいに広い葉っぱなんだろうけど、表面張力でまん丸になっている朝露で、七夕の短冊を書こうかという」と、ずるる。 「周りの青い山影が、一粒の芋の露に映り込んでいるというそんなヴィジュアルがともかく強烈だけどね。これ、川端茅舎の『金剛の露ひとつぶや石の上』を連想させますね。蛇笏の句の方が先なんだろうけど」 「茅舎は浄土を見ているけど、蛇笏は現世的じゃない。生活感がある。芋だってちゃんと掘って食うだろうし。茅舎はダイアモンドの水、もう末期の水って感じでしょ。露ののっている石も墓石って感じがしてならない。もう半分あっちに行きかけてる。いい句が揚げてあるよ。さすが、山本健吉!」 七夕や髪ぬれしまゝ人に逢ふ 多佳子 七夕竹惜命(しゃくみょう)の文字隠れなし 波郷 「多佳子らしいエロだね。もう、やる!って意志感じるね。これも桂信子の『ゆるやかに着て人と逢ふ蛍の夜』を思い出させる。人と逢う時の女性の特別な感覚かな」と、ケリー。 「いや、多佳子自身は取り急いでいて、髪の乾かないということが気になっている情況なのだろうけど、結果的には誘うんだね。信子は確信犯。心はもう決めている」 「それに引き換え。波郷は病気に悩まされている。もう少し生かしてください、なんて書いた短冊が見えて、自己嫌悪にもなる」 「悩ましい情況ですな、俺ぐらいの年になると、病気でなくても生きていることのうっとうしさは感じる」 「ほんとですか。ヤバくないですか」 「ヤバいよ。ははは」 「そういえば、天の川のことをミルキーウエイって言いますよね。欧米人はミルクの流れるように見えたわけだけど、やっぱり肉食系ですね」 「ミルキーウエイに対してシルクロードとくれば、これは中央アジアの大草原のイメージもあるね。こうなるとミルクも羊の乳」 「銀河になると、とたんに宮澤賢治になるからすごい。銀漢もある。漢は、川の意味があるけど、俳句でしかもう使わないでしょう。言語の絶滅種ですよ」 乳かけし氷の乳房匙掬う ずるる シャリシャリと練乳の垂れ銀河系 ケリー 「願の絲(ねがいのいと)という季語もあるね。七夕竹の先に五色の糸をつるし、願い事を祈ると、三年のうちにかなうという—ははー、松山で食べた五色そうめんがこれだな。子規もそうめんが好きだったみたいだね」 「機織りの糸がそのまま願いを結ぶ素材になる。それが七夕竹のあの飾りにもなったんですね。幼稚園でやる色紙の輪っかみたいなのとか」 「それから、わが商店街のサイケデリック・クラゲ・オブ・ノースコリアになった。進化というべきか、誤解の増長というべきか、ラディカリズムというべきか。眠流し(ねむりながし)と言う季語もあるな。七夕の灯籠送り(とうろうおくり)。秋田の竿灯(かんとう)、能代の七夕灯籠、青森市や弘前市の侫武多(ねぶた)。青森は金魚ねぶた、弘前は扇灯籠(おぎどろ)とか、喧嘩ねぶた—なるほどねえ、ねぶたも七夕系の祭りなんだ。というより、盆祭りと七夕は長い時間をかけて合体してしまったんだね」 「確かにね、青森ではねぶたが終わると秋といいますね」 「いやほんとに寒くなるんだね。だからねぶたは切ない。七日盆(なぬかぼん)というのは、七月七日が盆行事の始めとして、南大和や紀州では盆始めと言い、井戸浚え・虫払い・墓掃除・金物磨きなどをやる。磨き盆・池替え盆あるいは墓薙ぎ・墓の草薙ぎなどと言う。盆路、精霊路とも言い、精霊が出て来やすいように、山から里へおりる路の草を刈り払う—」 「なるほどね、年の瀬の大掃除は今でも風習として残っているけど、盆も掃除大変だったんだな。井戸から池まできれいにして、鍋釜磨いて、草むしって」 「うちは商売だから、毎日鍋釜はよく磨くよ」 なべおかま磨きて新宿二丁目に ずるる 草薙ぎて裸踊りや赤き坂 ケリー 「草君も赤坂の路を草なぎして、一人盆踊りしたんだね。精霊が降りて来たんだよ、あの晩はきっと」 「降りて来てるね、間違いないね」 「俺たちまだ、精霊降りて来てない。もう一杯飲まない?」 「よろこんで。じゃあ、李白酒造の月下独酌にしようかな。これ造った田中竹翁(竹次郎)さん亡くなってね、今日は独酌したい気持ちね」 「あるよ、でも、月下じゃない、雨が降り出したよ。雨の七夕さ、よくある」 「いや、月はある。あの雨雲の上にね、煌々と。でも月は、七夕には邪魔者だね、明るすぎて天の川が見えにくくなる」 「独酌もいいけどさ、久々の人に逢うのもいいよ、今晩あたり」 ずるるの言葉には応えず、ケリーは窓の外をうかがった。 星合コンバースの靴履いて出る ケリー 七夕やぼた餅やき餅きなこ餅 ずるる (つづく) |
|
13 迷宮は迷うためにあり春の渦 ◯月◯日 わたしの精神状態は最悪です。いつかケリーが電話でのコミュニケーションは嫌と言っていたのが、今ではとても良く分かります。以前は全く理解できなかったけど。かかって来た電話にもほとんど出なくなりました。メールは、現在のところわたしの唯一の支えです。かならず、すぐ、お返事ください。返事が無いと死にそうになります。うさぎはさびしいと死んじゃうんでしょ。今ではうさぎの気持ちも分かるようになりました。ではまた。ハト ―ハトは年下の男に熱愛中で、しかもそれがむくわれていない。わかっているのに無視されている。そんな状態の中、それがきっかけで、私のところにメールを送ってくるようになった。数年振り、突然のことだった。すこし励ましのメールを書いた。 うさぎ哭く声のさむさやさびしさや ◯月◯日 今帰ってきた。きょうも孤独だった。こんなことで自分が死ぬわけないってわかってるけどやっぱりつらい。こんなのはじめて。寂しいの。かれだってせかいじゅうでいちばんじぶんをあいしてるこころやさしいおんなをうしなったのよ。かわいそうだとおもう。どうしてそんなにげんきでいられるの?どうして?どうしてわたしをいらなくなったの?わからない。わかりたくない。でも心のどこかできっとハトは躊躇、もしくは迷い、あるいは尻込みをしたのかもしれない。その間隙に悪魔が宿ってしまった。いつでも躊躇って、迷ってる。知ってるでしょ。それを肌で感じ取る人間もいるのよね。その人にとって「絶対に忘れられない人間になってやること」だと思う。いま、ハトはそれを相手にしかけられていて劣勢になっている。「絶対に忘れられない人間になれない」ってわかってしまったからこんなにつらいんだと思う。傷つけていればこんなにつらくない。相手が傷ついた分、すくなくとも傷ついている間だけでも、忘れないって知ってるの。でもそんな力もない。なんて情けないの。再生より、破壊を!談交より、断交を!以前だったら「破壊しに」と言ったかもしれない。でもいまはもうこれ以上破壊するのは嫌。壊れるのは自分なの。そこから、新しい関係は生まれるかもしれない。「新しい関係」いまいちばん絶望してて、いちばん切望してるもの。ということで、まあ、悩むほど、相手のドツボにはまるから気をつけて。いいの。なやむのすきなの。たぶん。ないたらすこしきもちよくなった。泣けなかったの。それもつらいから。ハト ―ハトは中国語の勉強をしている。若いボーイフレンドは、中国人と日本人のハーフで、中国語がとても出来るらしい。その理由からではなく、高慢な子どもっぽい態度が、ハトの心を揺さぶったのだ。その激情がメールを打つ手にも反映している。漢字に変換しないで、自動記述のように叩き込んでくる。ハトには亭主がいる。長い返事を書いた。 絶望してて切望しててこころ壊れてて ◯月◯日 きょうもメールを開いたら文字の洪水。うれしかった。ハトの場合は、自分がどのくらい悩んだか、泣いたか、苦しんだか、そんな時間と思いの量を掛け算して、ある数量に達するまでは、治癒することが出来ないのだと思う。わたしもそうおもう。気が済むまで落ちていくしかないのかも。 あるいはもっと根源的な目的をある時期からすりかえている、そんな感じもするのだけど。それは最初からハトが悲劇的なものに向かって動き出した。ところがそれが愉楽的なものに進展し出してしまった。そこで慌ててきびすを返す。ことはやや悲劇的な進路を取った。しかしよく見たら自分だけが悲劇的であって、相手は一向に悲劇的な様相を帯びないでいる。それどころか、晴天の霹靂、いや台風一過の快晴状態にも見える。そこが誤算だった。一緒に悲劇的にならなかったら意味がない。この予測が真実にやや近いのであれば、ハトの一人芝居が台本の行方を見失ってしまっているところと推測できるのだがね。たしかに、これは終わらせなければいけないことだ、とずっと思っていたと思う。悲劇的なこと、というのも無意識のうちにいつも求めていると思う。ただ、一緒に悲劇的になるよりは、もうすこし壊したり繕ったりしながら一緒にいたかったということじゃないかな。やめよう、といえばいやだ、と言ってくれるんじゃないかという期待があったと思う。そのときは気付かなかったけど。どうせ終わる関係なんだから、一日二日早くなったって平気、なんて。 しかし、もともとハトは臆病者だから、今回のことでは凄く決意した行動だったのかもしれないね。そのとおり。凄く迷ったの。でもかれがわたしのじんせいをどうするのか見たかった。 なんかもう青春の残光に焼きつけられたような憔悴感みたいな。またとないチャンスみたいな劇的瞬間だったのかもしれない。そういわれるとお見通しみたい。よくあること、ってこと?でも、そんなことて数は減るかもしれないけど、まだ当分あるよ!誤解しないでね。わたしは恋をしたいと思っていたわけじゃなかった。ただ、かれにひかれたの。おもっているだけで十分だった。いままで、わたしは人を好きになったことがあったのかどうかただ、あいての情熱を見るのはすきだった。だからその、情熱を目のあたりにしていたいと思う感情を恋だと思っていたのかもしれない。でも今度は違っていた。好きだと思うのをやめたいと願うくらい、窒息するような感覚にいつもとらわれてた。あんまり厄介だといやになっちゃうこともある。特に、若かったり、老けて来たりするとね。まあ、これは勝手な想像だから気にしないでね。かれとも「積極的」だったとは思わない。むしろ苦痛だったかな…。 「泪が乾くまで」って歌があったけど、それかな、結局。さいごに電話で話した時かれがいったの。そんなにいいおんななのに、おれのせいで惨めになっちまって。惨めなおんなだとおもわれてる自分がいや。新しい関係を築くこともできない。いまは、敵前逃亡みたいにかれをさけてる。かれもそれに気付いてる。ほんものの惨めな女って感じ。ハト ―心理学的なのか、哲学的なのかわからないけれど、ハトの言動はどこか衒学的な表情を帯びている。自己解析と自己否定と、自己撞着が混在する奇妙な、臨場感のある文面だと思う。私の勤務する会社に学生時代バイトで通うようになり、二年ほどだろうか付き合った。ナイーヴで、すぐにナーヴァスになり、突如として攻撃性のあらわれる奇妙な女の子だった。それが可愛かった。 悲劇という道迷い込み鳩の森 ◯月◯日 薬が切れてきたみたい。なんでもいい、何か言って。ときどき本当にそう思う。没頭したい。ひたすら集中して頭が空っぽになるまで。何も考えない瞬間が欲しい。疲れて眠りたい。満足させて欲しい。ハト ―会って、セックスしよう、とメールを書いた。しばらくメールが来なかった。きっと考えていたのだろう。メールが来た。 ◯月◯日 この何年、ずっとそう思ってた。でも、会ってはいけない気がして会わなかった。会って、SEXして、っていうのは「違う」って、いつも思ってた。わたしがほしいのはこういうことじゃない。でも、それを伝えることはできなかった。だから、会ったあとはいつも自己嫌悪に陥った。必要としていた。会わない時も、もちろん今だって。あなただけが、わたしが欲しがっている言葉が何なのかを気付かせてくれる。あなたに救われたい。こころから、そう思う。会いたい。でも、わからない。ハト ―ハトのセックスは、幼女のように用心深く、わがままで、甘えた。つねに二人の関係は、自分本位でいられることを第一とした。じゃなかったら、絶対いや、なのだ。この面倒臭さは、奇妙に私のこころをとりとめもなく拘束した。愛してしまった。もう一度、セックスしたいと思った。 ◯月◯日 今回ははっきりさせます。でも、メール見て凄く会いたくなった。なぐさめてくれる?大人でいなくちゃってずっと思ってたからつかれちゃった。大人と話したいの。子供扱いされたり甘やかされたりしたい。待ってる。痛いからふきげん。寒いのと、痛いのと、どきどきしておちつかない感じこういう記憶とあなたが結びついているから、意識してなくても、会うのはやめようとおもってしまうってこと、あるかも。やっぱりあったかくてあんしんできる所じゃなきゃ絶対いやだ。もう会わない。ハト ―拒絶しながら、誘惑している。そういう性癖を、私が好んでいることもハトにはわかっているのだ。条件だらけにして、そんな約束はとっても出来ないという状態にして、誘う。そして拒否する。これは内発的な言動なのだが、私にとっては極めて戦略的に効く。やっぱり、セックスしたいと考えた。しかし、こちらも耐える。戦略的に耐える。対抗する。 月割れて虐め神笑う風の音 ◯月◯日 無視も放置も大きらい。喜んでない。「痛めつける」も「虐め」もいや。そんな事言うならいなくなってやる。 あなたに会って以前の「あの感じ」を思い出したの。わたしを苛々させる「あの感じ」。また「いっしょくたにしてる」って思った。あなたのつまらない女の子達とどうしてわたしをいっしょに並ベるの。いつも比較されている気がした。誰がいちばん奇麗、誰がいちばんECCENTRIC、誰がいちばんEROTIC…。あなたはべつにわたしを愛しているわけじゃない。こんなの、いつものことなんだろうって思った。だったら、全然ROMANTICじゃない。運命も、決意も、そこには存在していないじゃない。そんなのつまらない。たとえその時だけでも、自分がこの人の「唯一」の存在だって信じることができなかったら。恋におちるなんてこと、できない。ずっと憎んでた。あなたはわたしの自尊心を傷つける。わたしをあなたのコレクションに加えることなんか、許さない。造反有理。我開始復讐了。SEXしないことであなたを否定しわたしが他とは違うことを証明してやる。真実、わたしはあなたに理解され、救われることを望んでもいた。そうしているうちに疲れ、こんな関係に飽きてきた。あなたの前から消えることにした。あなたはそれを認識してた?一度目は偶然によって、今度は彼によって。わたしはあなたに再び会うことになった。そしてまた「あの感じ」今までのわたしは何でも否定して、壊して、捨ててきたでも、いつまでも同じ方法で物事を処理していては、つまらないってことにも気がついた。長い間、煩悩だった「あの感じ」を、幸福感に昇華させる方法がある、かも知れない。あなたに会ってそう思った。それを実行してみたいの。わたしがあなたにして欲しいのは何だと思う?ハト ―ハトと会った。セックスはしなかった。けれどもすぐに来たメールは、まるで海辺の波のように、ハトのこころは行きつ戻りつしていた。誘惑し、拒絶し、絶望し、また、希求し、口説きながら逃げ出す準備もしているのに、そこにいる。逃げ出すよ、といいながら、人恋しくたたずんでいる。この躊躇こそ、何かを欲してあきらめきれないでいる証しだ。いたいたしい、いとしいことばの津波。 花占いの花さらい去る春津波 ◯月◯日 あなたがこのメールを読むかどうかわからないけど、読んでくれることを祈ってる誤解しないで、わたしがあなたにして欲しいことはそんなことじゃない。わたしはあなたに会って思ったの。ずっと誤解していたのかもしれない。だったらどんなに幸せだろう。あなたにそれは誤解だと言って欲しい。わたしを長い間の煩悩から解放して欲しい。そうすれば、この苦しみを幸福感に変えることができる そして、新しく始めることができたら、わたしももう十分に長い時間生きた。壊して捨てるだけなんてもうしたくない。わたしも癒されることを願っているの。そして、それはあなたにしかできない。あのメールを送る時はとても迷った。どんな風に解釈されても仕方ないし、きっと傷つけるだろう。もちろんこれで終わってしまうことも考えた。なんどもなんども読み返した。でもやっぱり送ったのはあなたに理解して欲しかったからなの。でも、あなたを傷だつけるだけに終わったなら、ただわたしが愚かだったということになる。こんどは新たな喪失感に苦しむことになるそんな事は望んでいない。わたしはあなたに救われることを願ってる。ハト ―若いボーイフレンドの影が文面から消えていた。ハトは、私に呼びかけることで、ボーイフレンドの影を消そうとしている。私はひとつの愛の消しゴムであり、もうひとつの愛のえんぴつを、演じてさせられている。たぶん。そして小さな愛の筆箱の中で煩悶する。幼い学校の窓の向こうには早春賦が溢れている。ハトに、電話した。筆箱をガタガタゆするような会話だった。 ◯月◯日 さっき電話の声を聞いてもう死んじゃおうかと思った。死ぬ前にメールを見ることを思いついて良かった。でも、ハトが望んでくれるなら、 いくらでも、私はふたつの「希求」を、膨らめ続けます。 今からあなたの言葉を全部信じるわ。ハト ―ハトのこころがうごく。おさまる。すこし、じっとし始める。やさしいことばをたぐり寄せようとしている。やさしいことばを送る。 ◯月◯日 いま泣いてたの。寂しくて。 学校が終わった後、電話して声を聞こうと思った。でもなんだか恐くてできなかった。 顔が見えないと、不安。話し方や声の調子で不機嫌なのかと思ったりするし、そうするとますます気分が落ちてく。 どうしてあなたがそばにいないのかと思う。 でもそれはお互いに望んだ事が無いからよね。 そんな事を考えていたらもっと「悶」と言う感じになってきて。でもメールを開いたら凄く嬉しい事が待ってた。今すぐはあえないけど。すごくあいたい。ハト ―また、ボーイフレンドの影の中に入ってしまったハト。影の中からはい出そうとして、もがきながら、影の中に沈んでいく。もがけばもがくほど、深みにはまる。ほら、息を止めて、動きも止めて、目を閉じて、ゆっくりと、ねむるように、静かにしていると、ハトは浮き上がってくる。 迷宮は迷うためにあり春の渦 ◯月◯日 こんなにひたすら待っているのに、もう、返事くださいって言わない。いつかみたいに爆弾を送り付けたりもしないから安心して。ハトのメールを受信する度あなたが憂鬱になるのはうれしくない。あなたのメールを見ていて、泪がこぼれた。会った時に感じたことが正しかったから。ハトはあなたの「瞬間の慰安」でしかないのかと思うと悲しい。「わたしはハトにそれしか求めていない。だからハトも過分な要求をしちゃいけない。」そう言われているようでもあった。あなたという怪物みたいな大人の前では、ハトはいつまでも非力な子供で、ハトがあなたを愛しても、あなたは誰かを希求する事をやめないのだろうとも思う。そうじゃないって思いたかったのに、また絶望や孤独や虚無やもっとおぞましい感情がハトを呑み込もうとする。でもハトは過分な要求をしたい。ハトはあなたの「瞬間の慰安」なんかでは満足しない。いつかすべてを破壊する。あなたの欠落感も、わたしの孤独も。あなたをもっともっと理解する。あなたを満たす、唯一の存在になる。「ハトだけがわたしを理解した。ハトだけを愛してる。」この言葉をあなたの口から聞くまで、あなたを想いつづける。はじめにあんなふうに言ったけど、またいつかハトに話しかけて。この画面の向こうにあなたがいて、わたしと繋がっているって信じていたい。ほんとうは、いつもそばにいて、だきしめて、愛してるって言っていたい。ハト ―強要こそは、愛である。寛容こそは愛である。ハトの強要、私の寛容。しかしそれはしばしば入れ替わる。強要者が寛容者に変わる時の絶対愛。そのためにも、強要はその愛の入口で、極めて有効なのだ。そして、強要が寛容に変容するとき、ささやかながら、愛の達成感を享受する。ハトは、強要し続け、寛容になれと、強要し続ける。出口のない場所を確保する。愛には、出口がない。 出口あれば逃げ出す愛の茨垣 ◯月◯日 wordで書いてたら長くなっちゃったので、ここに貼り付けないで添付しました。セラピストに話してるみたいな手紙だから、読むとちょっと疲れると思う。読みたくなかったら、添付を開かないって選択肢もあるからとりあえず送信します。メールって、こういう所がやさしい。電話みたいに暴力的じゃないから、大好き。こんなことばかりしていて、勉強していません。ハト ―長い文章だった。告白と告発。倒潰してしまった内蔵の甘い液状化をかろうじて、絹のような羅が覆っている。どんな形をしているのか、ここからは見えないけれど、のっぺりとしたなめらかな曲線の微熱。触れれば裂けて、形を失ってしまう。あぶない、やわらかい、こころそのもののような形状をしたまま生きるのはむずかしい。だから、コトバの鎧を重ね着する。ガチガチにして、冷やし、液状化した内部をゆっくりとニコゴリにしていく。それには熱、やっぱり熱が必要なのだ。ハトの微熱を遠くから感受する。 ◯月◯日 ハトも、どうしていいかわからない。すごく不安です。何通も返事を書いた。でも、どれも納得行かなかった。 ハト ―理解したのかな。パーフェクトな答えを出そうとしているのかな。そんなこと、出来るはずもないのに。 ◯月◯日 会いたい。話したい。すぐ。無理だってわかってはいるけど、それしか言いたくない。 ハトが望んでいるのはすごく単純なこと。それをどうしてもわかって欲しい。 焦らないで、わかってくれるまで待とうって思ってたけど、望んでいるようには展開していかない。どうしたらいいのか、わからない。もう、メールは、限界。誤解は、絶対いや。 これは「つながり幻想」なんかじゃない。ハトは否定する。あなたにも、否定して欲しい。ハト ―すべては、限界の中にある。限界があるから、諦めも出来る。終わりもある。コミュニケーションはひとつの幻想でもある、と書いたことにハトは反問する。否定する。共通認識を欲してくる。わかってるよ、私だって、ほとんど同じだけど。 あえば花話せば遠き雲に似て ◯月◯日 HATOに日常が、戻ってきました。「不安な晴天」を読んだ時は、すぐにでも誤解を解きたいと思った。あなたの真意を、知りたいと思った。でも、ハトはその考えを捨てた。本当に望んでいるのは、この方向で結論を出すことじゃないと思ったから。そして、「どしゃぶり」が送られてきた。今回の、ものすごく婉曲な拒絶のおかげで、すべてがリセットされた。あなたの記憶からメールも何もかも削除して、再起動できたらいいのにと思ってた。構築してるつもりが、また破壊してた。なぜかはわからないけど、なんでも壊そうとしてしまう。どこかで間違えてしまったことは、自覚してた。でも、あなたがこうしてくれて、よかった。これでまた、始められる。あなたには、ずっと、そこにいて欲しい。ずっとずっとそこにいてくれるってわかってれば、会わなくても、大丈夫。もう、どこへでも行ける。なんでも、できる。不安が消えて、ハトに日常が戻ってきました。ハト ―どういうメールをしたかはここでは記さない。あまりに晴天であることの不安のようなこと。ハトは決して壊そうとして生きているわけではないのに、結果として自分をぼろぼろに痛めつけてしまう内向的な攻撃力を秘めている。それを和らげるのは、外側に向けての反作用で減少させること。振り子が静かに真下を指すような、静かな、自然な重力に身を委ねること。垂直の磁力にゆっくりと埋葬されること。 垂直に埋葬する六月の花嫁 ◯月◯日(ケリーからのメール) 最新のハトメールでこちらも心が穏やかになりました。そうそう、ハトメールっていうボキャブラリーを発見してから、それも原因で少し元気です。最近はひとつのルールを決めて生活しています。まず朝起きたら「ハト、おはよう!」って、こころの中でつぶやきます。確かに、うちの近くの公園には、鳩が沢山生息しているけど、そんなこと大声で言ったら、気が狂ったと思われるからね。でもそうつぶやくと、からだがボーっとあつくなります。イメージとしては、ハトをしっかりと抱きしめてる感じね。それからちょっとしたとき、ハトのこと思って、「ハト、元気?」って、声をかけます。この場合は、椅子に座っていたり、立っているハトを後ろから抱きしめながら言う感じ。そうすると、やっぱりからだがボーっとあつくなってくる。夜も同じネ。今度は暗い中でささやきます。「もうねちゃうの?おやすみ」今度は横になってしっかり抱き合ってるイメージ。これは相当効きます。妄想癖のバカみたいだと思うけど、効くからしょうがありません。というわけで、最近は、結構一日ハトと一緒してます。ではまた、ハトを抱きしめながら・・・ 会えるといいね。ケリー ◯月◯日 今度ハトがあなたに会いたいと思うとき あなたもハトに会いたいと思ってくれたら嬉しい。 それまで元気でいて。ハト ―元気でいたいと思った。それ以上にハトが、元気でいることを願った。ハトは、会いたいと思っても、きっとメールしてこないだろうと思った。 (つづく) |
|
12 桜か雲か胸腹の上で汗ばむ ひらかれた窓の向こうには、暗闇を抱え込んだ薬玉のように、たわわに花ひらいた桜の樹々が見える。それは堀端に点在する街灯に照らされて、おおきな雪洞のようにいくつも浮かび上がっていた。Kホテルのレストランで食事をしたあと、そのままふたりは部屋に戻り、じゃれるように服を脱がし合い、絡みつくようにして風呂に入り、ボディーソープで泡だらけになったお互いの体を撫で合い、滑りながら、つながり、離れ、また向きを変えて、つながり、シャワーで毛を剥かれた羊たちのようにつるつるになって、髪だけが濡れたまま、浴衣をゆるく着て、またビールを飲み出した。 「あーっ、東京でこんなお花見が出来るなんて、サイッコー! うれしいです。ありがとうございまーす」「桜を見るとね、黒田杏子(ももこ)だなーって思うんですよ。ともかく桜狂いの人で、二十七年かけて日本中の名桜を訪ねる「桜花巡礼」を満行してしまった。こうした執念は俳人としては重要です。桜といえば杏子と、専売特許化しましたから。『なほ残る花浴びて座す草の上』みたいにね。今また「残花巡礼」を続けている。変な桜の俳句といえば、芭蕉の句で、團十郎が見栄切ってるみたいなの、『花の雲鐘は上野か浅草か』。でも、江戸中が桜で沸き返っている情景を感じますよね。一茶も『世の中は地獄の上の花見かな』って、元禄の世のやけっぱちに騒ぐ民衆を詠っています。ちょっと今の社会に似てますよね。一方、『淋しさに花咲きぬめり山桜』は、蕪村の句ですけど、こんなさみしい山里だからせめて、豪華に花を咲かせましょう、といった感じかな。現代俳句のヒット作はやっぱり金子兜太の『人体冷えて東北白い花盛り』でしょう。いずれにしても、みんな桜を見ると、ひとまずは句にしたくなる、そんな衝動を感じる。まあ、桜に欲情するんですね」「わたしも、少し冷えてきましたけど、はっきりいって欲情してます。原因は桜、ということにしておきますけど、はははは」 さくら死ぬさくら錯乱さくら死ぬ 女さくらの逆さにさわぐ堀の水 千の視線に億の花弁が微動する ひと弁は爪ほどの紅山覆う 「さっきレストランでお話しになっていた草田男の話しですけど」「寺山修司が書いている草田男の話し」「そうそう、それ、もう少しお話ししてください」綾小路さゆりは甘えるようにいうと、五室剛は立上がり鞄から一冊の文庫本を取り出して、ソファにドッと座った。「変なもんですよね、これ。『寺山修司の俳句入門』(光文社文庫)だなんて、寺山がまるで「俳句入門書」を書いているみたいだけど、「寺山修司の俳句世界を知る入門書」なんですね。編集は、きちんと立てていないけど、寺山の第一句集『花粉航海』(一九七五年刊)を編集した俳人の齋藤愼爾がやっています。まあ、寺山が書いた俳句関係の文章を編集したものなんだけど、35ページの『林檎のために開いた窓——現代の紀行ノート』。昭和二九年二月ですから、十八歳の時の評論文です。たまげますね、高校生ですか、まだ」どれどれというように、さゆりは五室に体を寄せるように座り、股間に手を滑らし、下着をつけていない五室の陰茎を握る。少し冷たくねっとりとしたそこはほどなく熱を帯び、工事現場のクレーンのように立ち上がり出した。さゆりの指がゆっくりと動く。 「まず、寺山青年の机の上には二冊の紀行本が置いてあります。芭蕉の『奥の細道』と、中村草田男の『津軽』です。この二つの本は極めて対照的だと寺山はいいます。まあそのために並べているわけですが。芭蕉は、『その日その日がある意味で臨終に近く、いつ死んでもその時の句が辞世』といった生き方に対し、草田男は『私は二百年生きるつもりなのだ』といっている。まあ死生観がまったく違うわけです」さゆりの指に力が入る。 「で、『赤児さめし右車窓より夏暁くる』ではじまる草田男の『津軽』は、車内の赤ん坊の泣き声がまるで太陽を目覚めさすように夏の暁がきたという、生命感に溢れている。この句に寺山青年はすっかり惚れ込んでいます。それもそうでしょう。寺山は、当時『蛍雪時代』で投稿句の選者をやっていた草田男に評価されていた。『便所より青空見えて啄木忌』も草田男の選です。ただし器用にまかせた多作を戒めていますが。寺山の『母は息もて竃火創るチエホフ忌』が、自作の『燭の灯を煙草火としつチエホフ忌』の改竄と、草田男は知っていたのかも知れない。恐るべき少年としてね。しかしいずれにしても、秋元不死男や、橋本多佳子、加藤楸邨、石田波郷、成田千空といった俳人たちの中でも、寺山修司はすでに有名な高校生俳人だったわけです」「すごい。五室さんの高校時代は?」「わたしは医大受験でそれっきや考えていませんでしたよ」「ふーん、でもいいわ」すっかり熱くなっている五室の陰茎を、さゆりの手が素早く滑る。 「草田男の旅は、石川啄木の故郷、岩手の渋民村にさしかかる。そこで草田男が引く啄木の歌『霧ふかき好摩ケ原の 停車場の 朝の虫こそすずろなりけり』は、『朝のやや長い停車の間に小便をしている』啄木青年の姿と寺山は解説する。これこそ『便所より―』の句の原型じゃないですか。だから草田男は寺山のこの句を評価したのかも知れないし」「ふーむ」「で、草田男は『晩夏シグナル高し渋民村低し』『野に咲けど渋民村辺真赤な百合』など三句を残している。そして寺山はその即興性を評価するんだね」「即興がそんなに凄いんですか」「まあ、創作力がある一つの証かな」「なるほど」さゆりの乳房が、五室の脇腹あたりで熱く硬くなりだしている。「そのあと、芭蕉と草田男が重なるんだ」「エッ、時代を超えたホモ行為ですか」「そうくるか」 「草田男は、青森の大鰐に住む増田手古奈という人の邸に一泊するのだけど、『みちのくの一宿晩夏の合歓の辺に』『象潟のはせおの合歓も晩夏の合歓』を詠む。これは明らかに芭蕉の『象潟や雨に西施がねぶの花』を意識して作っています。寺山はこれをオムニバス映画のように面白いと激賞します。きっとその後の寺山の『田園に死す』や、『地獄篇』の原基になったんでしょうね。だけど『津軽』といって、芭蕉と草田男ではなにかが欠けている気がしますよね」「する。それはわたしも感じてた、ずーっと」さゆりは激しく手を動かした。 シグナルほどの高さも越えぬ晩夏の村 夏暁の車窓は蟬の声を殺し 草田男の旅に恋しき合歓の花は盛り 芭蕉ほどの辞世もありや夏の途なか 「そう、ここでやっと、太宰が登場するんです。でもその前に、わたしの右の四句、ちょっと変でしょう」「字、あまり」「そう、破調の問題は、寺山のいう『老俳人連中(無論アルチザンにすぎない)』の頑迷な定型支持を批判して、五・七・六、五・七・七、という「六音止め」「七音止め」こそ、近代的なリズムだと主張している。確かに寺山の俳句には、それが相当に多いので気になっていたのだけど。昭和二十年代後半のいわば流行だったと考えてもいい。草田男の『みちのくの晩夏描くを旅人見る』や、『灸据ゑられ泣きわめく声津軽は秋』なんかがそうだって指摘している。さあ、いよいよ太宰の登場です」「うわーお!」さゆりは五室の浴衣をめくって、マングースのように五室のいきり立つハブを咬えた。 「それもそれ、寺山修司にとっては、『津軽』は故郷、そして同郷人の太宰治は青森高校の先輩だし、この文章を書いてる時点でも太宰が自殺してから六年とたっていないから、そのスキャンダルはまだ余韻の中にあったと思う。名前だって、太宰は津島修治だしね」さゆりは顔を上げて、「二人の『津軽』のシュージ」「そう、一九八一年、仙台で開かれた「日本文化デザイン会議」で寺山は、太宰の『津軽』を論じたという話しを『東京モンスターランド』って本は紹介しているけど」「へー、誰の本?」「誰の本だっけ。草田男はともかく『薊と小店太宰の故郷へ別れ道』『秤林檎太宰の故郷この奥二里』『太宰の通ひ路稲田の遠さ雲の丈』など作った。寺山は『少年太宰治のその野心じみた空想』の向こうに見た雲の峰の遠さと、『草田男の立つ果てにある』雲が、昔のような遠さで湧き立っていると解く。しかしこの草田男と太宰の間にはどのような共通点があったのだろうかってことです。ページを少し戻すと、山口誓子や秋元不死男の『俳句』誌での座談の中で、草田男の悲劇性が話題になっている。二百年生きるといった草田男が松山で『ヒョイヒョイと二、三間づつ跳ぶようにしてやがて見えなくなった』という誓子が語ったエピソードを寺山は取り上げている。これは何とも、太宰に重なるイメージじゃないですか。寺山はそれをいいたかった。そして『Sleep, no more』という草田男の『開きすぎた眼』に言及するんだ。で、寺山はそれを、どう開閉したらよいか思案するところで文章は終わっている。『開きすぎた眼』というのは、すでに死に至ったイメージじゃないだろうか」「草田男が死んでいるってことですか」「さー、じゃなくても、この評論は結局『死』を巡る文章だね。紀行そのものが、死を覚醒するもなのだと思う。寺山修司は、『ぼくは不完全な死体として生まれ、何十年かかって完全な死体になるのである』と書いて死んだ人だから」 「太宰といえば、一緒に死んだ人、山崎富栄っていいましたよね」「そう」「わたし、本名、山崎富美恵っていうんです」「えっ、凄いね」「子どもの頃何度かからかわれましたよ」「そうだろうね」「男を殺す女だって」「それに雨もよく降らす」といいながら、五室は少し真面目な顔になって、「こうなって、こんなこというのもなんだけど、わたしも実は、シュウジが本名なんです。周二って書くんですけどね」するとさゆりは、ガバリと五室の膝にまたがって、五室の少しやわらかくなった陰茎を握ったまま、花にたとえられる赤い割れ目に招じ入れ、性急に体を上下しだした。「怖い! とっても怖い!」五室はゆっくりとさゆりの背中に手をまわして、抱きしめた。桜の花は煌煌と春の闇に群光している。 死に場所を探して桜の信号群 肉魂に押しつぶされ不完全な死体 桜か雲か胸腹の上で汗ばむ 股間のトンネルに桜が爆発する (つづく) |
「石神井公園の池の近くに、カネ子叔母さんという人が住んでいてね、おふくろのことをねえさんと呼んでいたから、親戚の人だとは思っていたけど、どんな関係の人か、子どもの頃の私にはわからなかった。時々吉祥寺の私の家に来てね、親はあれこれ仕事があるから、カネ子叔母さん私を連れて映画によく連れて行ってくれた。すらっと背の高い美人でね、いつもきれいな着物を着ていた。カネ子叔母さんのおしろいの匂いが、私の最初の性の目覚めだったかも知れないね。でもさ、カネ子叔母さんと話しをした記憶がほとんどないんだね。無口な人で、二人で黙って映画を見て、アイスクリームかなにか食べさせてもらって、黙って帰って来た。あとでわかったんだけど、カネ子叔母さんはおふくろの弟の嫁で、弟が結核かなにかで早死にしちゃって、若くして後家さんになった。それから再婚するんだけど、子どもが出来ない。そんな頃、うちによく遊びに来ていたみたいなんだ。その人が字がうまくて、年賀状見るたびカネ子叔母さんを思い出していたね。不思議なもので、今度自分が書をはじめて個展をするなんてことになって、ふと、カネ子叔母さんを思い出した。石神井公園の池の周りも歩いたよ。でも五十年も前のことだもの、わかるわけもないよね。池を巡る俳句を書いたのも、そんな潜在意識があったのかも知れない」 陳蕎麦ずるるは、個展の会場で呑みながら目を細めて言った。 「なにか、谷崎の『母を恋うる記』みたいですね」と、清瀬春夏。 「そうなのよ、私は自分がカネ子叔母さんの子なんじゃないかって、疑ってた時期もあったくらいでね。そんな悲劇性が、カネ子叔母さんにはいつもまとわりついていた。不幸せ感というのはときどき鋭く人の心をつかむんだね」 「でもさ、ずるるさんは背も低いし、おしゃべりだから、遺伝子的にもカネ子叔母さんとは無縁だと思う。それに『池を巡る』は、ぜんぜん悲劇的な俳句じゃあないですよ」と、金谷ケリー。 「まあ私の人生は、不幸のトリプルサルコみたいなものだから、着地点では幸せになっていたりする。いまさら「とびはね」だしね」 「吟行したんですか」と、春夏がたずねると、 「吟行なんてしないよ。なんか小さなスケッチブック広げて、風景写すみたいなそんなの、好きじゃないの。そんな現場見られたら、恥ずかしくない?」 「だって、吟行は俳句の基本ですよ」 「私には基本と資本がないの。この書にしてもね。学ばないということで、自己流を貫く。まあ、少しは学んだけど、独学。でも、池巡りはしたよ。東京周辺には池が多いのよ。湧水の池、灌漑用の溜池、大名庭園、それに寺社に属したもの。一番は公園かな。あるいは池のまわりを公園に整備したと言った方がいいね。だから『なになに公園の池』みたいに、名前がない池がいっぱいある。これ寂しくない? でもあとから名前付けると、区立あやめ池とか、みんなのいこい池みたいになるじゃない。これも問題だよね」と、ずるる。 「池って、でも何となく暗いですよね。それにあまりいい説話が残っていない。娘が身を投げると、蛇に捲かれて現れるとかさ」とケリー。 「それはSOVASOVAのある井の頭池だね。他にも同じような話しはいっぱいあるけど。ちょっと一巡り出来るくらいの池というのは、渦巻き状の一つの小宇宙を形成しているみたいな、地域の窪みの極のような求心力を感じるんだよね。『名月や池をめぐりて夜もすがら』、芭蕉の『孤松』に出てくる有名な句だけど、あれだって、池じゃないと一晩中月を楽しむなんてことはないね」 「なるほど、いまでは池のほとりに街灯が並んでいるけど、夜の池はボッカリと大きな暗闇を抱え込んでいた。そこに名月ですからね、それは映える」と、ケリー。 幼年期嗅ぐカネ子叔母白粉花 練馬 石神井公園 釣鐘を沈めて燃えし縄文器 祖師谷 釣鐘池 衣叩く砧の水の来ぬ人ぞ 世田谷 砧公園池 功名も行基空海塀の陰 鵜の木 光明寺池 弁天堂三回り目には蛇の中 三鷹 井の頭池 「でも、この書はなかなかですよ。あんまり書っぽくないっていうか」と、ケリー。 「そうね、書家の書とはやっぱり違うって感じ」と、春夏。 「ありがと、やっぱりデザイン勉強したお二人ですね。私は書に自信があったわけではないのね。左利きなので、筆で文字を書くということには独特のストレスが生じる。筆を左から右へ「引く」のではなく「押す」ことで運筆するからね。正統な書は絶対に書くことができない。そのことがかえって私のアマチュアリズムを刺激し、だからいいだろうという居直りを持たせてくれたけど。色紙サイズの水墨画帳を買ってきて、俳句を三行に分けて書き出した。石川九楊の『一日一書』三巻も読んだ。『書に通ず』はすでに読んでいたけど。 私もデザインを学んだせいか、中村不折や、河東碧梧桐のようなヘタうま書に親近感を感じていた。そのトピックとして、副島種臣の造形的な書にもっとも惹かれるものがあったね。けれどもいざ書き始めると、自分がいかに書を出来ないかが判然とする。運筆がわからない、崩せない、ひらがなが書けない。しかし不思議なもので、習字すると少しずつうまくなってくるのよ。少し前に書いたものがとんでもなくヘタであることに愕然とする。けれどもそうなると、今書いている書が、なにやら三流の書家の作品のように、平凡なものに見えてくる。ふた月もすると、すっかりスランプに陥ってしまったね」 「どうしたんですか?」と、春夏。 「九楊さんの『書に通ず』を読み直した。例えば、明治十五年(一八八二年)洋画家の小山正太郎は「書は美術ならず」という論文を発表していると書いてある。「読めない字は書ではない」つまりいくら書でも、造形の遊びになっているようなものが、美術の領域にはみ出してこようが、それはしょせん美術ではないのだから、意味がないと言っているんだろうね」 「桑原武夫の『第二芸術』みたいですね。表現領域を仕切りたがる人が必ず出てくる」と、ケリー。 「これは国際紛争に似ているね。にじんでいる部分に無理矢理線を引こうとする。中間領域というか、共有領域というのは、ほんとは必ずあるんだよね。恐らく洋画家の中村不折もこの論文は知っているはずで、明治四十一年(一九〇八年)河東碧梧桐に薦められていやいや『龍眠帖』を出す。画家として自分の書を美術と見てなかったのだろうね。反対に碧悟桐は絵描きじゃないから、不折の書に単純に共感があった」 「でも間違いなく、不折には、文字のすがたひとつひとつに独特の情景を読み取っていたことだけは事実でしょう。それが美術と言わないまでも。そしてその思考は、限りなく美術に近いですよね」 「ケリーさんも勉強してるね。私もそう思う。絵を描く楽しさと、字を書く楽しさがまったく重なっている。しかしね、九楊さんは「書は文学」だと言ってるんだ。王羲之や、顔真卿、黄庭堅は、政治家や詩人だし、空海や、嵯峨天皇、小野道風、藤原行成は、高名な僧や天皇や歌人であるわけで、「書は人なり」なんて解釈するけど、やっぱり「書は文学」だと。つまり、筆法、筆意、筆勢、筆力、筆触、筆鋒などという書を評する言葉は同時に、文学・文体を論評する時に使う言葉だと言うんだね。そして結局、「筆触」という一語に行き着くんだ」 「ヒッショク」 「そう、春夏ちゃん、ヒッショク。九楊さんはこう劇的に描写している。『筆尖が紙に触れ、両者間に、接触と摩擦と離脱のチカラの劇である筆触と言う出来事が始まります。書きながら考え、書く―この姿は筆触が思考している姿です。(だから)文学は筆触の巨大な抜殻(カス)』でもあると言うんだね。何てったって九楊さんは書の人だから、筆触こそが文学を生み出していると。で、ワープロは本当の文学を生み出せないともね」 「書にとっては、最大級の援護射撃というか、相当マニヤックなテポドン級の攻撃力ですね」と、ケリー。 「確かに。しかしずいぶん以前、谷崎潤一郎の展覧会に行って、一メートルもある『源氏物語』の筆の生原稿の束を見た時は驚嘆した。筆触の抜殻のてんこ盛りだものね。筆触には確かに文学を誘発する力があることは事実でしょう。でも、変に文字フェチになっても、文学は起こらない。書は「美術」というより「書く芸術」だと。書きながら創造していくライヴ感のある行為なんだね。それは実感したよ」 「でも、最近、そんなジャポニズムで整形した若手書家が多くて、ちょっと変じゃないですか」と、春夏。 「それはそれ、私はときどき京都に行くんですよ、大学の非常勤講師としてね。で、新幹線の時間待ちで、八条口にある「武蔵」という回転寿司に入るんだけど、そこの壁という壁、間という間が、相田みつをの書なんだよね。私はあれが大嫌いでね。だって「人間だもの」だよ。「人間、けだもの」だったらうれしいけど、めちゃくちゃメメシボクーでしょ。でもね、書をやって少し相田みつをが解った気がした。だってさ、書家というのはほとんど人の文章を書いているんだよね。『方丈記』写したり、『般若心経』だったり。自分の言葉を書いているわけではない。ところが相田みつをはメメシボクーだけど、自分の言葉を書いている。自分の筆触に誘発されて、居酒屋のメニューみたいな書体でね。まあ好き嫌いは別として、ともかく書にして、文学をやった人なんだ。書に未来があるとすれば、やはり、筆触とかはどうであれ、自分の言葉を書く。で、私は自分の『池を巡る』を書いたってわけ。これが基本だね」 「やっぱり、基本じゃないですか」と、春夏。 「そうだよ。基本。個展の基本はオープニングに呑む。ケリーさん、ワインもっと呑んでよ。春夏ちゃん、このチーズいけるよ。ゆっくりしてって、今日は池をめぐりて夜もすがらだよ」 池二つ心字雲形菜の花忌 日比谷 心字池・雲形池 辛夷咲いて行者も転ぶ下り坂 下目黒 蟠龍寺池 こち亀よりコチコチ硬し甲羅干し 江東 亀戸天神池 足洗う海舟の夢水の泡 南千束 洗足池 初虹に秘文刻みし厳島 目黒 碑文谷池 (つづく) |
窓の外は、元気のない秋の梢を濡らす夕雨が降り出している。五室剛のパソコンに綾小路さゆりからのメールが届いていた。医局にある私室は静謐な空気が充溢している。さゆりは五室に時々メールをよこしてきた。それを読みながら、五室は必ずさゆりのからだのことを思い出した。そう反応するようにという、さゆりからの特殊な信号のようなものが仕掛けられていて、強制力すらあった。 しっとりと湿度のある吸いつくような肌が、柔らかくもはね返えしてくる弾力と、そのなめらかな肉のかたまりが、絶妙に反応するその動きとを、五室は思い返していた。まるで夏の終わりの交情の貌が、ガラスの器にもられた寒天のなかに埋め込まれているように覗き込めた。スプーンをさし込めば、さゆりを掬えるような幻想を見た。五室はそれを、スノーボールを撹拌するように消そうとしたが、その瞬間にもさゆりの子宮に続く口径のみごとな薄紅色が羅のように閃いた。 —さっきから、雨が降りだしましたでしょう。私、雨女だから、どんな雨も好きなんです。こんなみみっちい、街がビンボッぽく見えるようなじゅくじゅくした雨でも、結構好きです。だからかしら、最近見た夢を思いだしたので、ちょっとメールさせてください。お邪魔でしたらあとでゆっくり読んでいただけば結構です。 そこは、ハンガリーなんです。もちろんブタペストとか、行ったことないからどこの街かはわかりません。きっとテレビの紀行番組かなんかの記憶が変形したものなんでしょうけど。ぶらぶらと石畳の狭い路地歩いているうち夕暮れになって、雨降ってきて、灯もりだした街のあかりがにじんで、私はすごくうれしくなって、どこでもいいからと思って飛び込んだのが、ネバーエンディング・ストーリーの四分の一ぐらいの小さな古書店でした。 「いらっしゃい」「ようこそ」「どちらから」何も言ってくれません。私がその店に入ったことすら、不確かなくらい反応がありません。だからかえって私はほっとして、ほんのり黴臭い書棚を見上げます。気がつくとずいぶんと天井が高くて、分厚い本がぎっしり詰まっています。図書館みたいと思って、その狭い通路をぐるりと回転すると、私の後ろに小さな女性が本を持って立っています。ほんとに小さな女性です。「これでしたね、あなたが探していた本は。やっと手に入りました。ちょっと高いですけど大丈夫ですか。三千フォリントですよ」会話は不思議とスムーズに進行します。もちろん夢だからですよね。 私、じつは世界の通貨マニアで、変な趣味でしょ。中学生の頃からほとんど使ったことのない通貨を覚えました。ハンガリーはその前のペングーがめちゃくちゃなインフレになって、フォリントに切り替わるわけです。これでここがハンガリーなんだって判ったのかもしれません。小さな彼女の手にある本は『原色人軀解剖圖鑑』、十九世紀に復刻された本で、それが見事に美しいんです。「ほらほら、ここでしょ、ここでしょ」その小さい彼女は、陰嚢や陰茎、膣や子宮のページを開いて見せてくれます。「ありがとう、これです! これでした。探していた本は」まるで薔薇の絞り汁を精液で溶いて描いたような、ねっとりとした色彩です。私が本に顔を近づけると、膣から、子宮に向かって吸い込まれるように私は小さくなっていきます。 夢はそこで終わり。変な夢でしょ。まあ、夢は結構みんな変ですけどね。欲求不満があるわけではないのだけど、エロティックなことに少し過剰に反応してしまう性向はあるかもしれません。なんて、カミングアウトしちゃって。いや私はまったく自分が正常だと確信してます。五室さんは私をどう思われているのでしょうね。まあ、勝手に判断してますけど。うふふです。 そういえば岸田秀の本に変なことが書いてあったなあと思って、確かめてみたら、『岸田秀最終講義DVD本』という本で、「吸引色情」という項です。あ、今日は私自宅です。私は自分がしていることを一度も疑ったり、不安になったりしたことはないのだけど、それってどうして!って、素っ頓狂に(わ、出なくていい漢字でた!)驚どろいたりするので、それを学術的に検証してみたいと思ったりするわけです。まあ、浅薄なうわっ滑りの研究趣味なんですけどね。引用します。ちなみに香山リカの本は読みません。私は絶対、自分がうつ病にならないと思うからです。でもきっと、自覚のない病気である可能性はありますが。色情狂とか。五室さんもキス好きですよね。というか・・・ 「性交の前にカンニリングスやフェラチオをするのを好む人びとや、性交よりもカンニリングスやフェラチオのほうを好む人びとは、第一次思春期に、吸う行為の中にリビドーの最初の満足を見いだした人であるように思われる。(中略)フロイド(1905,b.p212)も、母親の乳房を吸う行為とペニスを吸う行為との関係を指摘した。彼はこう述べている。「このように、ペニスを吸うというこの極度に厭わしい倒錯的空想は、無邪気な起源から発している。それは母あるいは乳母の乳房を吸うという、いわば先史的な感覚の変化した物であり・・・」。一方、H・ドイッチュ(1945,p.92)は、口の機能と膣の機能との関連について次にように指摘している。「ペニスの能動的な刺激のもとで、乳を吸う口と完全に力動的に照応する膣は、無意識の深みの中で哺乳という受動的な機能を引き受け、それによって母親の乳房の象徴的な意味をペニスにあたえる」。 メールは気まぐれにここでぷつんと終わっている。五室剛は岸田秀の文章を二度読んで、さゆりに俳句で応えることにした。 雨姫の文濡らす雨牡の雨 雪球(スノーボール)に沈む羅(うすもの)閃けり 匈牙利(ハンガリー)小女のたたむ古書の黴 秋霖なお肉熱きまま解剖圖 人軀をバラバラにして参阡フォリント 哺乳とは母のペニスと欲望学 力動的に照応する膣乳を吸う 汝の膣は茎吾の口は房迎え秋 (つづく) |
|
09 遺体という物体に吹け夏の風 「最近さ、知人、友人がよく死ぬのよ」ずるるは小さな声で言った。「それはそれは」そば焼酎のお湯割りを作りながら花鳥は応える。夏の蕎麦寄席が終わったSOVASOVAの店のすみで、二人の男は向かい合っている。 「写真家のIさん肺癌、コピーライターのMさん心筋梗塞、デザイナーのFさんクモ膜下で階段落ち、役者のSさん癌、なに癌だったかなー、芝居終わってすぐ死んじゃった。ピナ・バウシュも、マース・カニングハムも死んだね。好きだったね、カッコよかったね」「ずるるさんは文化人ですからね、あたしは知らない人ばかりですけどね、いや、マースなんとかって人のダンスはむかーし見たかな」 「それがね、私の大学時代の先生、もうだいぶ前から認知症になっててね、亡くなった。それもね、死んじゃって、骨になってから知ったのよ。痛恨の極みだったね。晴天の霹靂」「何の先生?」「デザインの」「え、ずるるさん、デザイナーだったの!」「言わなかったっけ、四十五まで、デザイナーやってたよ。バブル崩壊してやめた。脱サラ蕎麦屋。まあ稼げなかったわけじゃないけど、蕎麦屋やりたくなったのね」「よくあるパターンね」「そう、よくあるバカ選択」「バカじゃないですけど、気持ちはわかりますよ」 「最近はさ、密葬とかやっちゃってさ、それで、そのあとで、忍ぶ会だの、お別れ会だのやるでしょ」「やるやる、はやりですかね」「ちょっとした知名人は、そうなる」「うん、関係者が急に駆けつけられないっていう事情もあるんでしょうけどね」「まあね。そうかも知れないど、やっぱりご遺体のない祭事って、駄目だよね。リアリティがない。ご遺体という圧倒的な物体がない。業績飾ったりしてさ、やだね、本人望んでないと思うよ。ひどいね、つまんない」 「ご遺体・・・」「男は死体(したい)!女は遺体(イタイ)!なんて、冗談ダメだよ」「ダメだよって、ずるるさん言っちゃってるよ」「先生は有名人だったからさ、紫綬褒章も受けてるし、文化功労賞もおかしくない人だったけど、組織に結局座らない人だったんだね。だから推薦も受けず、もらえなかった」「褒章なんてどうでもいいじゃあないですか」「もちろんだよ。でも、受けても当然の人が受けないというのも、やなのね」「そんなもんでしょう。噺家の世界だって、え、あの人がっていう人がもらったりしますから」「そりゃそうだけど、うん」 「それでね、先生の息子に電話した。お別れ会やるんだったらなんでも手伝うからって。ありがとうございますって、言ってくれた。しばらくしたら、『さよなら、A先生』って、案内状が来ました。ちょっとがっかりしたね」「ははー」「これは勝手な自負だったんだけど、私はね、大学時代から相当に先生に目をかけてもらっていた。これは確実に、自分を可愛がってくれているって感じたね。それは、私が蕎麦屋になっても、ノボル君、これ私の本名」「ほう、ノボル君」「そう、ノボル君、君はデザインを捨てたわけじゃないんだろって、言ってくれてました。でも、捨ててました、もうとっくにね。だからって、やっぱり先生のお別れ会の進行役は、私だと思っていたよ。こうして、蕎麦寄席をやってるみたいに、私は企画や進行なら、相当出来る」「出来ますよ、知ってますよ、そりゃあ」「先生につながる人間たちなら、今でもそう思っていると思うんだけど」「なるほど」「でもね、それが先生とはたいして関係もないのに、今はアートプロデューサーとして羽振りのいい男が司会してたよ。オヨヨ!だったよ。ヤダね、愚痴だね」「ふむ、まあいいでしょう」 「ご遺体というのはさ、死んでから焼かれるまでの、ほんの二、三日、時間でいえば、六、七〇時間でしょ。この世に生まれて八十年生きて、365×80だと」「29200日」「花鳥さん、公文式してた? 時間に直せば―」「700800時間」「スゴイね」「珠算教室に行ってたんですよ、親がうるさくてね」「つまり、70万時間のうちの70時間か、1万分の1の瞬間にね、遭遇しにくいってのは当然のことなんだろうけど、そこを逃さないのが、親密度というか、生きてる人間の勤めみたいなもんでしょう」「勤めがいやで、デザイン止めてもね」「そうそう」 「私はね、お別れ会の司会なんて勿論どうでもいいの。もうどうせ蕎麦屋だしね。でも、先生のご遺体だけには会いたかった。連絡がなかったのは、関係者に平等に、情報を出そうとしたんだろうけどね。それはわからないでもないけど。こんな思いは始めてだけど、ご遺体のそばで、十五分ぐらい声を出して泣きたかったの。それで、気が済んだと思う。先生、ありがとうとか、先生、苦しかったですかとか、なんか、応えてくれない人に、大声で話しかけてさ、泣けば気が済んだの。でも、知った時には先生は、もう骨だったのよ。晴天の霹靂、痛恨の極みね、悔しいね」「でも平気、ずるるさんが死んだら、SOVASOVAのこの店で葬式してあげるから。トホホギスのみんなで、遺体囲んでどんちゃん騒ぎしますから」「ほんとかよ、嬉しい、それだよ、派手にね! 私はしっかりご遺体やるからね!」「まかしてください! でもまだ当分死にそうにないけど」「わははは、そうでありますようにだね!」 ご遺体という物体に吹け夏の風 何事もなく青天の霹靂師の死の日 通夜葬儀会いたい遺体すでになし 雨激し痛恨の極み死に会わず 夏墓に刻め恍惚の人甲骨文字 「そうそう花鳥さん、今日の出し物は何だったっけ」「え、聞いてたでしょ。酔っぱらっちゃったの」「ごめん、ぼーっとしててさ」「らくだと、怪談もの」「あー、それでか、それであっちに行っちゃった人のこと、ずーっと考えてしまったんだ。ごめんごめん」花鳥はずるるにそば焼酎のお湯割りを作り足しながら、「いーえね、そんなこともあるもんですよ」「ありがと、花鳥さん。陳蕎麦(ひねそば)ずるる、痛恨の極みの一席でした」上を向いた瞼から、大粒の涙がこぼれた。 (つづく) |
08 立てたまま垂れたまままだ鯉のぼり
五月中旬、東京駅から午後一時の東北山形新幹線つばさ083号に乗り込んだのは、陳蕎麦ずるる、娘の池端蕎麦子、風月亭花鳥、金谷ケリー、清瀬春夏の五人。「世間は新型インフルエンザで大騒ぎだってのにさ、新幹線乗る頓狂もないけど、空いててよかった」と、ずるるは持参のワインを抜く。娘の蕎麦子が自家製のピクルスや、チーズ、だし巻き玉子などをタッパーから出す。「これで、向こう行ったら山形牛でグーでしょ」と、夜のメニューまで決めている。大宮を抜けるあたりから風景が変わりだして、福島を過ぎると山が迫り、トンネルに突っ込み、抜けたかと思うと水田が五月の空をまぶしく真っ平らに映している。ワインは二本目に入った。 豚風邪を恐々はずす超マスク 熊谷駅兜太先生八十九 立てたまま垂れたまままだ鯉のぼり マンションの全室節句ス五月かな ワイン揺れて緑滴る夏車窓 「車窓の風景って、みんな俳句っぽいってのがやだね。それに俳句にしてもダサくなる」「ずるるさん、俳句やる人は、なにかと俳句目で世界を見る癖が出来ているから、観念的になってダサくなるんですよ。でも時々凄いのが出てくるからなー、あなどれない」と、ケリー。「風景だってそうよね、時々ドキッとする。セメント工場の塔とか、壊れかけた森影の納屋とか、ピラミッドみたいな山とか」と、春夏。「壊れかけた森の納屋ってさ、農夫の濃厚で執拗なセックスを何時も連想してしまう」「それは、ケリーがやりたいってことでしょ、そこで」「うーん、深層心理でくるか。くたびれた農具とか、ぼろぼろのロープとか、蒸れたムシロとかが、暗闇にひそんでいるわけ」「私はさ、郊外のでかいマンションを見ると、その全室で昨日もいろんなセックスが繰り広げられたんだろうなーって、想像しちゃうんだ」「郊外のマンションじゃないとだめなの?」「ダメ、巨大で、新しくて、できれば若い夫婦が、超複数同時多発というダイナミズムがいいんだよねー」「花鳥さんはヘンタイです、単に」と、蕎麦子。 ああなんて凡庸な俳句的夏景色 トンネルを眩しく塞ぐ青葉空 水という摂理に畦を築きおり 遠い雲みず田に映す奥の道 森影の納屋から洩れる肉の音 午後四時、山形駅着。すぐに駅近くのKホテルにチェックインして、ロビーのカフェでコーヒー飲んで、タクシー二台に分乗して会場に行く。大学のファサードは、白亜のギリシャ神殿と飛騨高山の合掌造りを合体させたような奇妙なデザインで、その前を掘り込んだ人工池の中に能舞台が立ち上がっている。松葉目はなく、縦溝を深々と幾筋も彫り込んだ巨大な円柱が老松のイメージか。反りのいい屋根のうだちを跨ぐ巨大な鬼瓦は舌をべろりと出している。それに校舎から突き出た橋懸かりは恐ろしく長い。 「なるほどねー、これは教養ですよ。なんか分けわかんない取り合わせですねー」と、ずるる。「このミステリアスな関係を解くのが、教養なんです」と、花鳥。「お二人は教養がお好きなんですねー。まあいいことですが」と、春夏。出し物の解説が始まる。「これがないと、なにがなんだかわかりませんよ。とくにお能はね」と、一同。 『居杭』というのは、喰うだけの居候(山本則秀)、つまり「居喰い」のこと。それを面倒見る亭主=保護者(山本則重)が、このイグイ君に会うと必ず扇子で頭をぽかり。それがたまらぬイグイ君が姿隠しの頭巾を手に入れて大いたずら。たまらぬ亭主が算置=陰陽師のような占師(山本東次郎)を呼んで居杭を探させるうち、大騒ぎになって終わるというもの。(頭巾で姿を隠して透明人間になるなんて、SFファンタジー狂言である。) 『安達原』は、熊野の山伏一行(宝生欣哉・大日方寛・山本則重)が陸奥国安達原に着くと日没、山里離れた庵に一夜の宿を乞う。里女後の鬼女(観世銕之丞)は断るも、「どうか」という願いに請じ入れる。今宵は寒いので山に薪を拾ってくると庵を出る里女。けれども寝屋だけは「けっして覗かないで」と言いおき、長い長い橋懸かりへ。(里女といえどもすでに老婆、そろりそろりと出てゆき、一旦立ち止まり振り返るが、その後の疾走が凄まじい。鬼女へ変貌していくのである。この長い橋掛かりを逆手に取った演出演技の銕之丞はさすが。)ところが従者が寝屋を覗くと、そこには屍が累々とある。面も変わって鬼女となった里女は、薪一握り、庵に帰ってくるが、そこで山伏と鬼女の念力合戦となる。(これはもう、笹公人真っ青のネンリキ能なのである。) 夕日を背に屋外の座席に座る。篝火と校舎の窓に反射する夕日が燃えているようで、自然のすさまじい舞台装置である。ほどなく気がつけば周囲は暗転、寒さが増して膝掛けの毛布を被りながらの観劇。囃子、地唄が途絶える瞬時に、その静寂の中に小さな蛙の声が遠くから聞こえてくる。 夕焼けも篝火も爆ぜ鬼女の面 閑(しずか)さや蛙(かわず)も謡う薪能 閑さや蝉は地中で死ぬ準備 古池に蛙は飛ばず芭蕉の句 十四代傾け寒し夏の山 一同が薪能に満足したかどうかは、その後の飲み会の様子で判断できよう。一様に面白がってはいるが、深く論議には至らない。それはそうである。能狂言の世界は素人が語るには深過ぎる。それよりも、山形牛の串焼きと、郷土の素材を使った料理と、銘酒十四代をはじめとする地酒の飲み比べに俄然、話は盛り上がった。 「そういえば、カエルが鳴いていたじゃない」「春夏ちゃん、カワズといってよ、一応おれたち俳人なんだからさ」と、花鳥が突っ込む。「ははは、ごめん。あれよかった」「そうね、自然の中で創造的なことが行われるって、なんか信頼できるわ」と、蕎麦子。「『やせがえる負けるな一茶ここにあり』って感じだったですよね」と、春夏。「でも、一茶ってさ、ネガティヴとポジティヴが捩じれてんだよね。性同一性障害というか、多重人格というか、香山リカに診断してもらうと面白いんじゃないの?」とずるる。「あの瞬間は、芭蕉の『古池や蛙飛びこむ水のおと』ではなくて、『閑さや岩にしみ入る蝉の声』のほうに近かったね。そういえば、長谷川櫂の書いた『古池に蛙は飛びこんだか』(花神社)は読んだ?と、ケリー。ずるると春夏が手を上げる。「さすがに教養人だね」と、ケリー。「面白かったわ」「面白いけど、まあちょっと強引だな」と、ずるる。「どういう本なの?」と、花鳥と蕎麦子が身を乗り出す。 「つまりね、山寺に上がってみると、周囲はとてつもない静寂に包まれている、ただ、蝉の声だけが、岩山にしみ込むように聞こえてくる、というのが一般的な解釈なわけだけど、長谷川櫂は、違う。『岩にしみ入るように鳴く蝉の声を聞いて天地の閑かさに気がついた』ととるべきだといってるのね」と、ケリー。「ほとんどおんなじじゃない!」と、花鳥。「いや違う。蝉の声を聞いて閑かさを認識したのか、閑かさの中に蝉の声を聞いたのではね、確かに違う。『古池や蛙飛び込む水のおと』もそう。ほとんどの解釈は、蛙が古池に飛び込んで水の音がした、と読んでいる。正岡子規は『古池に蛙が飛び込んでキャブンと音のしたのを聞いて芭蕉がしかく詠みしものなり』(俳諧大要)と書いてる。『キャブン』というのがいいよね。高浜虚子だってね、『芭蕉が深川の庵にあって、聞くとも鳴く聞いていると、蛙が裏の古池に飛び込む音がぽつんぽつんと聞こえてくる』と、ごく平凡に解説している。虚子の場合は、蛙が複数飛び込んでいるところが面白い。でもね、この一句でね、貞門、談林の俳諧が終息して、蕉風開眼の一句とされている。まさにこの句から、芭蕉の芭蕉らしい俳句が始まったといわれている。それにしては、一般の解釈ではこの一句の凄さを少しも感じない。そこで長谷川櫂の古池探検が始まるわけだ」と、ケリー。 長谷川櫂は「古池や」の「や」にまず注目する。切字である。「古池に」であれば、一般に解釈されている内容になる。しかし「古池や」であることで、ここで句は一旦切れる。そもそもこの句ができた状況を、支考が書いた『葛の松原』から解説している。芭蕉は最初「蛙飛びこむ水のおと」だけを作って思考に入ってしまった。するとそばにいた其角が、「山吹や」にしてはと提案する。万葉集の歌にも、蛙と山吹を取り合わせたものがあったからだ。(もっとも、この歌の作られた頃からずっと、蛙は鳴く声をいつも歌われてきた。しかし芭蕉は飛びこむ水音に注目したのである。これがまずエポックメイキングな着眼だった。)しかし、芭蕉は「山吹」を採用せず「古池や」としたのである。ここから、芭蕉古池コードの謎が始まるわけだ。で、長谷川櫂はこう解釈するにいたる。「蛙が水に飛びこむ音を聞いて古池の面影が心に浮かんだ」というのである。 「確かに、制作のプロセスを見ると、古池が後からくっつけられたという事実はわかるけど、だからといって、この古池は、やっぱり蛙が飛び込みそうな気配を満々と持しているんだよね。だから、櫂さんの蛙が水に飛びこむ音を聞いて、芭蕉は静謐な古池をイメージしたという解析が正しいとしても、だとしても水の音と古池が近すぎていて、やっぱり誤解を免れない句ではあるね」と、ケリー。「かりにそうだとしても、蛙が飛びこむ水の音から、古池をイメージしたという解釈は、やっぱりとっぴだねー、いきなりだよ。とっぴは、粋なりってね」と、花鳥。「そのとっぴを、蕉風開眼のとんでもなさと解釈しましょうか」と、ずるる。「とっぴ句って、いうところですか」「うまい、さすが噺家!」「ご祝儀に、春夏ちゃん、今晩付き合ってよ」と、花鳥。「さー、どうしようかな」といって、春夏はケリーの表情をうかがう。ケリーはしかとして杯を口に運ぶ。 (つづく) |
07 春の霧にドゥオモ朦朧と立ちにけり
ところで、午前中のミラノの街をうっすらと湿らしている早春の霧に包まれたドゥオモ大聖堂を、金谷ケリーは、まるで水墨画で描いたような風景だなと思いながら見上げていた。それは白い大理石を積み上げ、奇岩のように装飾されたファサードや尖塔群が、北魏式の仏像や、嶮しい山塊のようにも見えるからなのかも知れない。うっすらと陽が射して、陰翳が明らかになってくると、あの長渕剛の描く激しい書画のようにも見える。もとより、すべての存在は一通りにしか見えるわけではない。幾通りかの見え方をすることにこそ、そのことを人はよろこび、その変幻をためつすがめつ楽しみ、とらえようとする。それが詩になり、絵になり、音楽におきかわる。 春の霧にドゥオモ朦朧と立ちにけり 春祭りドゥオモを煽る旗の波 車輪の下の石畳ケルト古人の骨軋む ハトバトバタガッレリア潜る春の音 つまりほかでもなく金谷ケリーが思索していたことは、風土と表現メディアということになる。端的にいえば、俳句はミラノを描けるか、ということだ。つまり俳句はあまりに日本の風土を描写し過ぎてきた。山村、田園、市井の四季、風情、生活ばかりを描写していたではないか。いまでも日本を描写する最良のデッサン道具と思っているふしがある。歳時記、季寄せで集める季語は日本の四季風物ばかりである。日本画家がどんなに現代的なモチーフを描こうが、畢竟日本画になってしまうという苦渋から、解放されてはいない。平山郁夫の中国、加山又造の裸婦、内田あぐりの具象と抽象の中間領域、千住博の滝、モチーフと気配はさまざまだが、歴然と日本画である。それでも内田や千住の世代は、日本画という概念を拡張することに格闘していることも事実だ。グローバルな表現であることを目指している。かといって洋画において、佐伯祐三や荻須高徳が描写したような、まったくの無国籍な、ユトリロ風模倣的パリ街区も、いまの時代では恥ずかし過ぎる表現となってしまっている。これらは日本びいきのフランス人が日本で俳句を詠むような、小ジャレたエキゾティシズムとどこが違うのか。再び問う。俳句は、日本以外の風土を、グローバルに記述し得るか。 摩天楼より新緑がパセリほど 三十数年前に鷹羽狩行がアメリカに滞在していたときの作品である。エンパイアステートビルの高さから、セントラルパークを覗き込んだ。その新緑の木々たちが、まるでパセリほどに小さく見えたという驚き。摩天楼はなぜかハリウッド映画の背景のように映え、パセリの一語が洋風のカルチャーを明るく表示している。けれどもこれはどう見ても、観光旅行者の視線である。ニューヨークでなくては体験できない鳥瞰図ではあるが、世界的な都市型公園を、まるで盆景のように描いている。それにしても、山本健吉にいわせれば、「俳句は(訪ねた処への)挨拶」であるという。芭蕉の「おくのほそ道」も、旅行者としてご当地への挨拶として残された。ならば、鷹羽狩行もニューヨークの旅行者として挨拶を残したといえる。しかし、芭蕉の「おくのほそ道」には、地つづきを歩一歩線を引くような連続性があるのだ。 あらたふと青葉若葉の日の光 田一枚植て立去ル柳かな 風流の初めやおくの田植うた 笈も太刀も五月にかざれ帋幟 けれども芭蕉の旅もまた「観光」だった。観光というのは本来、珍しいところをへ巡るだけの旅ではない。旅の途中「こんな場所にいたい、住んでみたい」という思いになることは、現実界の極楽浄土探し、結果「死に場所」探しなのだそうだ。だから「観光」は「観音」にも近い概念となる。結局、芭蕉は近江琵琶湖畔の膳所(ぜぜ)を選んで「死に場所」としている。 いずれにしても、絵はがきほどの小さなスケッチブックにデッザンしているような、手中懐中の愉楽。そんな俳句に、ミラノの風土など収まるわけもないか。和歌のしっぽ(七七)の切れた俳諧は、和句となり、日本の貌、心、風をもっぱらに詠う。豚の毛の洋画筆ではなく、馬の毛の面相筆のような道具となった。この物質、この素材、このメディアの峻別は、表現領域を厳しく限定しているのではあるまいか。あるいはこうした筆使いで決定する世界の出来上がりようが、そのメディアの特性でもあるのだけれど。それゆえに、表現する対照を選り好みしざるを得なくなった。例えば俳句の十七字(音)というのは、いろいろな色の十七本のマッチ棒でどんな図形が描けるか、といったゲームに近いのかも知れない。そのくらい限定された条件の中での創作なのである。いやそれがマッチ棒ではなく、爪楊枝のようなものか。また、時々新聞の俳壇欄に、海外で生活する人の俳句が選ばれていたりするけれど、なにやら「日本という臍の緒」から、一向に切り離されることのない、異邦人の描写になっている。あるいは、異土で俳句を書くことで、日本につながっているという感覚。俳句がどのように国際化しても、まあなんといっても、五七五という様式にひそむナショナリズムが、想像以上にグローバルな表現の、障壁になっていることだけは間違いないな。金谷ケリーは、賑やかに晩餐のすすむリストランテのテーブルで、ビルラを飲み干したとき、「ブォナセーラ」ジュリエッタは小さく笑って店に入ってきた。 ジュリエッタは立ち上がった金谷ケリーの両頬に頬をあわせてくる。オフィスでは握手をしただけなのに、なにかがうれしく進化している。金谷ケリーはコマーシャル制作のリサーチにミラノにやってきていた。ミラノの若いデザイナーたちをテーマにしたシリーズ広告企画だ。同伴する予定のディレクターが直前に撮影がはいって、結局金谷が一人で動くことになった。その仕事のコーディネイトをしてくれるミラノのエージェンシーにジュリエッタはいた。アシスタント・マネージャー。最初の打ち合せが終わったあと、ディレクターのアレッサンドロに食事を誘われたが、「若い人がいくようなリストランテにいきたい」というと、「おー、それならジュリエッタがよく知っている」とウインクしながら振ってくれた。アレッサンドロは英語が得意ではない。金谷と食事をするのが少々面倒だったようだ。「わたしが?」と最初は驚いた表情をしていたが、「オーケー、オーケー」とうなずきながら、ジュリエッタはレターヘッドに地図を書いてくれる。ブレラ芸術大学の近くだった。「9PM?」「そう、夜は長いわ」そういったジュリエッタは、ブルーのセーターに着替えてやってきた。 「ワインは?」「赤、フルボディの」「オーケー、パスタは?」「なにがおいしい?」「フェットゥッチーネかな」「じゃあそれ」「わたしは、ニョッキにする」「シェアしないの?」「うーん、ミラノの人はあんまりしない」「日本のイタリアンは、シェア、常識」「ふーん」不思議そうに金谷の顔を見つめる。「きみは、ブレラに通っていたの」「ブレラに入るのは大変だわ。ボーイフレンドがいっていたの。わたしはカレッジでアニメーションの勉強してた。日本のアニメーション好きよ。ハヤーオミヤザーケ、カッツヒーロオトモ、マモールオッシイ、テズーカ・・・」「オサムね」「ナイスね、日本には興味あるわ」左の指のはらを右の指のはらで押し開くようにしてジュリエッタはアニメーターの名前を数えた。黒い髪の下の黒い大きな瞳がジーッとケリーを見つめている。魔法にかけられたように金谷の心はほどけだしていた。
死ぬために生きているの赤ヴィーノ呑む ブォナセーラ黒いオリーヴァ齧る春情譜 フェットゥッチーネに舌まくパーネ喰う アモーレカンターレマンジャーレ今宵も それにしても、日本のアニメーションはどうして世界的に成功することができたのだろうか、と金谷ケリーは考えた。古く、鳥獣戯画の時代から、江戸の北斎漫画につながり、岡本一平、北澤楽天、田河水泡、長谷川町子、手塚治虫、そのあとに続くマンガの膨大な文化があり、それに気の遠くなるようなアニメの手作業をいとわぬ人手がかき集まり、テレビというメディアに侵略し、劇場アニメも挑戦して、ディズニーをしのぐ芸術性のあるアニメーションの世界を構築していった。進化と開発を求めて止まない日本人の気質は、デザインや工業製品の圧倒的な制覇を導くことにもなる。その反面の守旧思想。天皇制の尊守から、俳句の花鳥諷詠まで、芭蕉、蕪村、子規から、新傾向俳句、新興俳句、前衛俳句と、俳句にも伝統に対抗する何度かの改革の波が起こったが、現在の俳句世界にはまるで痕跡を残していない。すさまじい伝統の前になす術もなしってところかい。なんてことだ! 進歩のないものに未来はないのにと、金谷ケリーはぼんやり考えた。 「そうそう、ジュリエッタ、きみはハイクって知ってるかい?」「ハイク? ノー!」「日本のすごく短い詩なんだけどね、たとえば、The old pond; A frog jumps in, --The sound of the water.みたいなの」(R・H・ブライスのは、直訳過ぎて面白くないが)「なにー、それが詩なの? わたしは蛙きらい。フランス人はよく食べるけど、わたしはだめね」「そう、それじゃあ、In the rain closing my eyes under the cherry blossoms(「花の雨花の下にて目をつむる」五島高資『雷光』の一句)というのはどうかな」「雨でまわりがよく見えないの、それで目をつむって花の匂いを感じているんでしょ。さくらんぼの木は見たことがあるわ、どこだか忘れたけど。でも、わたしは花が咲いていたら花を見るわ」「そうだろねー、だけど、日本人はね、花があるから目をつむる。そしてきれいな花をもう一度、心のなかで見ようとする」「ふーん、よくわかんないけど」「たとえばいまわたしはジュリエッタを見ている。で、目をつむるわけ。そしてジュリエッタを心のなかにしっかりと記憶する」「ふーん、それで?」「それだけ」「それだけ?」「そうかー、そうだよねー、やっぱりミラノに、俳句のこころは似合わないよねー」と日本語でつぶやくと、ジュリエッタもわかったふうに「ネー!」とこたえて笑う。
バローロと、ブルネッロのワインを二本空けて、どうせならとドールチェも食べて、さてというところで、ジュリエッタが、「ホテルはどこですか」ときく。「エンタープライズだけど」というと、「ほんと、スノッブなホテルね。ファッション関係の人がよく泊まるわ」「そうだね、ミラノコレクションが近いから、そんな業界っぽい人とモデルに、朝食でいっぱいあったよ」「うおー」「興味ある?」「もちろん!」「くる? これから」「これから?」「夜は長いよ!」金谷ケリーは、ジュリエッタのいった台詞をそのままに返した。 (つづく) |
06 いいかげん舐めまわしたる春の猫
「さあ、私は咽喉科の医師ですから、便通のことはよくわかりませんが」 「あら、お医者様って、一応何でも身体の基本的なことは勉強されるんじゃないですか。私をこんなに気持ちよくさせてくれるのだって、きっと、お医者様だからだと思ってましたわ」 「いや。しかし太くて立派なのは健康のあかしのようにも思えますし、排便の快感というのは別に異常なものとも思われません。でももし気になるようでしたら、内科の先生を紹介してもかまいません。それからいいわけじみますけど、セックスの仕方まで、医大や医学部が教えてくれるわけではありませんよ」 「それじゃあ、やっぱり五室さんは天才なんだわ。お勉強とセックスの、ああ、それから俳句も」 「いやいや。綾小路さんはもしかして、スカトロがお好きなんですか。別にかまいません。子供の頃はみんな肛門愛期というのを経験しますから、なごりは誰にでもあるはずです。もちろん私にも」 「それで五室さんたら、肛門をお舐めになったり、指をお入れになったりするんですか」 「そんなことしましたっけ」 「あら、私は好みではありませんが、でも、絶対ヤダというのでもありません。それなりの違った興奮というのがやっぱりあるんだと思います。そうされたら、もう逃げないみたいな、覚悟というより、引き受けるぞみたいな。その人の趣味、嗜好についていくぞみたいな」 「いい人ですね。そういう人、好きです」 春にひるロシア潜水艦肛門愛期 春日陰汝の趣味嗜好とどまらず 軒に吊る肌着しんなりと早春賦 午後の太陽の光をぼんやりとさえぎる、うすい曇り空が、さゆりの部屋から見える。窓の半分ほどは近隣の家々にさえぎられ、鳥の影がチュッとひと啼き、軒低く飛んでいった。ベランダの隅には洗濯物のかたまりが、何かを期待するように、しんなりと水気を発散しきれずに吊られている。まるで時間が片栗粉を流し込んだように、ゆるやかに固まっていた。五室は頭の後ろに手を組んで目を閉じた。さゆりは五室の太ももをゆっくりと撫でていたが、固くなり始めたそこに手をあて、井戸の手綱をたぐるように手をすべらす。その付け根にあるお手玉ほどの、皮袋にたゆとう双のうずらの卵が、鋼にように硬直し発熱し、さゆりはそれをたなごころで強く握りしめる。やがて湧水の水面に顔を近づけるように、屹立するほむらを頬をほそめて口中にみちびく。うなずくように顔を上下に動かす。 土曜日の午後の早く、その日は夕刻から句会があるので、本屋などに立寄ると家人にはことわって、五室は家を出た。松山での出会いから、五室は月に一、二度、さゆりの部屋をたずねていた。「綾小路さゆり」とからかわれるのはその容貌からというよりも、言動からだと五室は考えた。やや奇天烈なもののいいようが、奇人の印象を人に与えているのだ。しかしさゆりに逢うたびに、その肉体の妖艶さと気疲れしない気遣いに、投身するように蟻地獄にはまる誘惑と、同時にわずかな困惑も感じていた。どうしておれがここまで、という自問だった。そこはゆるやかな砂丘の斜面をのぼるほどの努力で離れることは出来たが、五室のこころは次第に、倫理を無化する犯意を楽しむことに、没頭しているようだった。 さゆりはそれをくわえながら、五室の顔を覗き込んでいたが、ゆっくりと態をかわし、白いねっとりとした太ももで五室の顔をまたぎ、その上に重なった。たっぷり膨らみ垂れる両の乳房が、五室の腹にさわさわと触れ、顔の前には大きな桃の丸みがのしかかり、しっかりとした柔毛の陰が近づいてくる。五室は桃の匂いを感じた。錯覚ではなかった。両手で大きな丸みを持ち上げるように、たしなめるように、少し離し、紡錘形にかげろう柔毛のふくらみを確認すると、そのなかへゆっくりと舌先を突き立てていく。丸みが恣意の重力を得たようにぐっと沈んでくる。ねじれるようにほぞる穴に鼻先が密着する。五室はいやいやをするように顔を左右に少し振ってこする。それから顔を少し上げてそこらあたりにためらわず舌をまわす。あごに湿ったホトがあたる。くわえたままのさゆりの声がくぐもって漏れる。言葉にならない奇妙な音がいとおしかった。 たなごころにあふれるものありふきのとう いいかげん舐めまわしたる春の猫 門くぐる女の陰に猫じゃらし しばらくはおたがいをその舌先、口内でたしなみ、いつくしむように堪能していたが、刀身から鞘が離れるようにするりと顔を遠ざけると、さゆりは濡れたホトをぺたりと腹の上に密着させ、背筋を和弓のように反らしてふりかえった。「よろしいでしょうか」「もちろん、のぞむところでした」馬から下りるようにまたがりかえし、背中に腕をまわすように手をそえてゆっくりと内襞に迎い入れた。そこは五室の形どおりに姿を変え、程よく締めつけてくる。折りたたんだ膝の弾力で上下に肉体を浮き沈みさせ、髪のしなだれた肩がそびえ、腹がたわみ、のび、そのつど臍に皺をきざみ、両の乳房がゆったりと揺れている。軀の底から洩れるような息づかいが激しくなり、五室が太ももから背に手をまわすと、そのままさゆりは五室の上に倒れこんできた。大きな乳房が五室の胸の上で、ふた方にわかれた。じっとりと汗をかいている。五室は強く背中を抱いた。さゆりは五室の頭を抱え込むように腕をまわしてくる。唇を吸い合う。舌がからむ。二人の唾液が口内に流れだし咀嚼する。その間もさゆりの尻はリズムをとってゆっくりと動いている。 推す敲くあくこともなく春の門 果て足りてもうなにもいらぬ春の水 夕月の透けるごとくあり東窓 ベッドの上は二人の汗で湿めり、さゆりは五室の上で、手びねりされた粘土のように冷たくなって寝ている。五室は寝たまま腕をのばし、ベッドのきわに丸まっている打ち掛けを引き寄せてさゆりの上にかけた。「ありがとう、少し寒くなってました」「そう、背中が冷たい」「ありったけの熱が放出してしまった、まるで死体みたいに」「死体と交わったことはないけど、反応のないセックスというのも虚しいものじゃないかな」「反応するなといわれても、無理です」「でも、死体になった肉体を弄ぶというのは、やっぱり刺激的なんだろうか」「わたし、死にますよ、お望みなら」「ありがとう、考えさせて」さゆりはぎゅうっと五室を抱きしめると起き上がり、五室にまたがったまま、ベッドサイドのテーブルからペットボトルをとり、五室にわたす。五室は少し体を起こしてミネラルウォーターを飲むと、さゆりに返した。さゆりもうまそうにのどをならしてそれを飲んだ。さゆりのぼんやりとしたシルエットがかくす窓の外はまだ明るい。低い屋根のすぐ上に、オブラートを重ねたようなあえかな丸い月が見えた。「この窓は、東向きなの?」「そう、午前中だけ光が入るんです。でも、なんで?」「月が見える。この時期この時間にはもう、月は東に出ている」 (つづく) |
05 雨雲に突っ込む人力ソロモン号
「東京は曇りですが、松山は今日の夜明け前から雨だそうです。市街劇ですから、影響はあるかと思いますが、でも、雨の市街劇というのも一興ではないですか。四人分の雨ガッパも用意してますし、ご心配はありません」 何でもポジティヴに判断し、手回しのいい五室を、春夏は信じられなーいといった表情で見つめた。老教授・下奈出氏はといえば、市街劇などどうでもよかった。晩に宿泊する道後温泉のことの方がずっと気になっている。綾小路は春夏から五室を紹介されて飛行機に乗る前から舞い上がっていた。というのも綾小路には、「医者で俳人のいい男を紹介してあげる」といってあったので、綾小路はすっかりその気なっている。春夏は五室からのガード役にこの二人を誘い出していた。(ちなみに、この市街劇『人力飛行機ソロモン』は、一九七〇年に東京新宿で、七一年にフランス・ナンシー市、オランダ・アルンヘン市、九八年には青森市で上演されている。ナンシー公演も一日中雨だった。) 雨雲に突っ込む人力ソロモン号 隕石のゆっくりと落下する冬日 雨粒の密集動かざる瀬戸の島 地平線幾度も書き直して冬の旅 雨雲に突っ込んでいく飛行機の中で綾小路さゆりは思わず「あーあ」と嘆いた。「ごめん、春夏ちゃん、私、雨女だった」「えー! 今頃いったって遅いですよ」「でもほんと、忘れてた。私ね、幼稚園の時から、学芸会でも、運動会でも、遠足でも、ほんとによく雨にぶつかったの。だって、それが自分のせいだなんて誰だって思ってもみないでしょ。でもね、小学校、中学、高校になっても、結構雨の確率が高かったの。おかしいじゃない。やっパリコレって、私の雨女という才能のなせる技なんじゃないかって」「今、パリコレっていった? 冗談?」「ややね」「冗談じゃないですよ。それに雨女って別に、才能なんかじゃないんじゃないですか」「そーかなー、めんごめんご」「反省がまるで足らないみたいですけど」「やあ、でも、私がいくことで、寺山修司の市街劇が雨になるなんて、すごくない?」「すごくない! 単なる迷惑です!」「うん、私は歴史を演出する人かも知れないわね」「そうだとして、ほかにどんな歴史的な事実があったんですか」「そうねー、ちょっと待ってね、今思いだしてみるから」「ケッコーです!」 人間とはこんな空の上まできて、なんと意味のない話を永々やっていられるのだろうと、後ろの席で話を聞いていた五室は思った。「ランボーを五行とびこす恋猫や」、五室剛は寺山修司の一句を思いだしていた。下奈出氏はもう熟睡に入っている。 何行も乱暴にとびこす恋女 雨女歴史も濡らす冬芝居 我を待つや子規山頭火氷雨町 三十八年の時空を飛んで冬に入る 松山空港は雨の中だった。年間通して雨の少ない松山市で、特に夏は渇水の危機がしばしばあるというのに、こんな日に限って雨だなんてなんということだろう。空港の食堂でジャコ天うどんを食べた四人は、タクシーでいったん道後温泉のホテル努盆館に荷物を預けると、11時からの搭乗券(公演チケットを主催者はそう呼んでいた)の引き換えに、再び市街の市役所前に向かう。コの字型に設置したテーブルに人だかりが出来ている。 「記念のタオルポスターが500円でーす!」という係員の元気な呼びかけに、五室剛は四枚をすかさず購入。「帰りにみなさんにお分けします」といって、大きなバッグにしまう。それから、子規のお面と地図を受け取ると、市役所の軒下にみんなを集結させて、地図を広げながら、「さて、ここの市役所前が①の表示ですから、オープニングは②のついている大街道に違いありません。時間も12時00分となっています。急ぎましょう、遠くありません。歩いても十分とかかりません。みなさん雨カッパです。春夏さんはピンク、綾小路さんはイエロー、下奈出先生はグレー、私はブルーを着ます。冷えますからご注意ください。下奈出先生、今日は随分と歩くことになりそうですが、お疲れになりましたら申してください。すぐに車をつかまえますから」 頭に後ろ向きに子規のお面をつけた綾小路さゆりは、うれしそうにビニールの雨ガッパを着ながら、「ねえ、春夏ちゃん、五室さんてテキパキしてて、FBI長官みたいな人ね、ステキッ!」喩えがわからなかった。春夏は、市街劇を見る前からすっかり疲れ出していた。(ちなみに、お面に使われている写真は、松尾芭蕉のたどったおくのほそ道を踏破する、旅の門出に撮った若き日の子規である。) 五室剛は、「俳句甲子園」のイベントですでに何度か松山を訪れている。松山は正岡子規生誕の地。高浜虚子、河東碧梧桐、時代が下がって中村草田男も生まれている。そして種田山頭火終焉の一草庵も再生された。まさに近代俳句のメッカなのである。子規好きの司馬遼太郎が書き出した長編歴史小説『坂の上の雲』は、子規の同郷友人でもある秋山真之と、兄の好古を軸として、日露戦争に突入していく一大叙事詩。これが、NHKのスペシャルドラマとして二〇〇九年より三年間放映されるということで、松山市がそれをきっかけに、文化発信プロジェクトとして立ち上げたのが、まつやまEPOX(エポック)という連続イベントだった。その一環のプログラムとして市街劇は計画された。ひとつには、寺山修司の創作が、少年時代の俳句から始まったというのが、この企画の発端だったという。寺山は飛行機好きの少年だった。いや、飛ぶこと、旅することになによりも憧れた人だった。
出奔す母の白髪を地平とし 血と麦とわれに亡命する土地あれ 冬畳旅路の果ての髪ひとすじ 冬の葬列吸殻なおも燃えんとす 出奔す人力飛行機異形隊 亡命の国境画す血の絨毯 冬の少女手旗信号燃えんとす 剃髪の儀式真っ白に葬列止む 大街道は全長が500メートル程もある巨大なアーケード街である。傘はいらない。しかし雨ガッパを着ているので蒸すような不快さだ。正午、堀端の通りから滑り込むように設置されている大型トレーラーから、血色の絨毯が敷かれ出し、そこに白塗り黒衣の異形群が発煙筒の中から、湧き出るように現れてくる。イントレの高く組まれた上では、セーラー服の少女が二人手旗信号を送っている。どこに? なんと? プロローグは大音響のアジテーションから始まった。そしてちょうど俳優たちが「太陽がいっぱい! 太陽がいっぱい!」と叫び出したとき、日が射し始め、雨は奇跡のように止んだ。五室剛はこのスペクタクルに身震いする。清瀬春夏は判断不能で当惑する。綾小路さゆりは群衆の後ろから背伸びする。下奈出三郎はひたすら尿意する。 下奈出教授が三越のトイレから戻るのを待って、五室剛はいった。「すでに、番町小学校で『1メートル四方1時間国家』の建設が始まっています。急ぎましょう、市役所の少し手前あたりです」まるで国家建設に立ち会う傭兵のように歩き出した。これから六時間もの間こんなにして町をへめぐるのか思うと、春夏は卒倒しそうだった。そんなこともよそに、五室はいう。 「気づきましたか、綾小路さんのとなりに総演出のJ・A・シーザーが立っていたのを。銀髪を後ろで束ねてミラーのサングラスをかけた大きな男です。それからイントレを組んだその下のベンチに腰をかけていた、いかにも若い頃は美貌だったという女性、あれが九條今日子、寺山修司の元夫人。その後ろに立っていた黒ブチの眼鏡の人が、この企画者でプロデューサーのエノモトだと思います」綾小路がすかさず突っ込む。「だったら、早くいえよ!」「いえ、写真はちゃんと撮ってありますから」「ナマが見たかったのよ、ナマが。私、ミーハーだから。でもー、五室さんてスゴいわー、みんな知ってるなんて、ポ、よ。ポ! ポニョ!」綾小路の表現は難解にして、わかりやすい。 番町小学校に着くと、白い布を巻いただけの半裸体の男女が、アダムとイヴの神話を思わせるような姿で校庭にうずくまっている。少し離れたところで笛を吹いている男がいる。それを数十人の観客がまるで爆弾処理現場のように遠巻きに囲んでいる。五室はしばらく見ていて、「ふむ、国家の態をなすまでには一万年はかかりそうですね。次ぎにいきましょう」と歩き出した。下奈出教授は「さっぱりわからん」と春夏を見る。「前衛ですからね」と、春夏は応える。 「これからロープウエイ街の煉瓦館でやっている『注文の多い料理店』、ジャズ・イン・グレッジの『詩劇・思想への望郷』、愛媛銀行のところに回って、『青空を私有することへの犯罪性』、大街道に帰って美容室Bee Hiveのヤミーダンスのパフォーマンスを見たあと、すぐ前のこまどりの焼きカレーを食べて、うーん、やっぱりNTT社宅の『天文学者の孤独』も見たい。しかし時間的に無理だ、あきらめて、一五時には道後温泉のほうに向かいましょう」という五室一行のまわりを、子規面をかぶった人たちが、地図を片手にぞろぞろと行き交う。まるで難民キャンプを探す流浪の民のように。 望郷の故郷は冬の子規ばかり 仮想の国難民流民冬の旅 プロペラの冬の手触りふるふる雨 またも雨虚構地獄のクリスマス 結局、五室の計画通り仮想の国家で行われている、虚構の祭事に立ち会う地獄めぐりは順調に進行していった。道後温泉本館の二階から繰り広げられた、下馬二五七と、蘭妖子の『老嬢交換B二階の兄弟劇』を観てから再び大街道に戻り、まことクラヴのスクランブル交差点ダンスを観て、そのまま堀の内にある市民会館に直行する。すでに二階ピロティの入口には、多くの観客が開門を待っていた。「やっぱりここだ。市役所でエピローグはないと踏んでました。さあ、ここで最後のスペクタクルを楽しみましょう。これこそがテラヤマワールドですよ」 会場になだれ込むと黒衣の役者に「合言葉は?」と問われる。五室は四人分の大声で「黒く塗れ!」と怒鳴った。大音響の呪術音楽と、アジテーションは繰り返される。市街を歩き回って座席に着きほっとしている観客を、叩き起こすように芝居が進行していく。そして、観客をすべて舞台に上げての大撮影会。観客が舞台に上がって子規の面などかぶっている間に、ダーッと役者が姿を消す。それを追って観客が外に出ると雨は一段と激しくなり、市民会館の裏手の野球場跡あたりが煌々と明かりに照らされ、音楽が流れてくる。さらにもうひとつのステージが作られていて、そこには翼長十二メートルの人力飛行機ソロモンが、雨にずぶ濡れになって離陸を待っていた。 道後温泉の努盆館に一行が帰ったのは午後七時過ぎ。温泉に入って大食堂のテーブルに着いたのは八時を回っていた。みんな浴衣に着替え、羽織を羽織っているが、綾小路さゆりの白いおおきな胸元が、湯上がりに桃色に染まり五室はしばらくそこから目を離せないでいる自分に赤面した。 「それにしても、こうして一日中回ってみると、寺山修司という人がどんな人だったのか、分かるような気がしてくるのだから、おかしなものですね」と、下奈出教授は述解する。「亡くなってからもこんなにリアルに寺山を感じる演劇が存在することだけで、これはもう奇跡じゃないでしょうか」五室剛は感嘆する。「そうね、ほんとね」と清瀬春夏は軽く相づちを打つ。「それにしても、五室さんが一緒じゃなかったら、こんなに市街劇を楽しめなかったと思うわ。ありがとう、感謝、感謝のアイラヴユーよ」五室は顔をぽっと赤らめながら「いやいやそんな」と軽く否定し、綾小路の空になっているコップにビールを注いだ。「注いだついでに、それじゃあ今から句会をやりましょうか」と五室。「えー、みんなは俳句をお書きになるけど、私はだめ、まったく出来ません」「お遊びだからともかく、五七五でつくればいいのよ」と、春夏。するとしばらく考えていた綾小路が、 ドボンと跳ぶ愛はいきおい冬の闇 と、一句作り上げた。「なにそれ」と、春夏が突っ込むと、「私はそれ、いただきます」と、五室。「え、いただいていただけますの? 五室さんに」五室は綾小路の豊かな胸元にちらりと目をやって答える。「はい、とても素敵です。いただきます」春夏はこのやり取りに相当白けた。食事と句会が終わり、ラウンジで少し飲み直したあと、春夏と綾小路は部屋に戻った。春夏は用心深く、綾小路に相部屋を頼んでいたのだ。しばらくテレビなどを見てから、布団に入ろうとしたとき、「あー、やっぱり私、もう一度、温泉につかってくるわ」といって綾小路さゆりは部屋を出ていった。しかしそのまま朝まで部屋にはもどってくることはなかった。 (つづく) |
04 赤い線震える憤怒あり文庫本
金谷ケリーはとどいた書籍を開封しながら、その本の薄さに多少驚いた。文庫本一四〇ページほどのそのなかのたった二〇ページに過ぎい小論文が、当時(昭和二十一年)の俳壇を激震させたというのが、奇妙にも思えてくる。 講談社学術文庫⑱『第二芸術』桑原武夫著、定価三六〇円。Amazon.comで検索すると中古本が一〇〇〇円ぐらいから五〇〇円まで何冊か並んでいた。金谷は一番安い五〇〇円のものを購入することにして、ショッピングカートに入れた。とどいたのは、徳島県板野郡板野町犬伏字角橋の「高原書店 徳島倉庫」からだった。昭和五一年六月初刷りの六〇年七月の九刷り物。送料が三四〇円かかった。 ネットで、『第二芸術』に触れてから、実際この本がどんなものなのか気になっていた。まあいまはもう、『第二芸術』は俳句の歴史のなつかしい一齣に過ぎなくなってしまったほど、俳句はふたたび現在流行のおもむきすらあるが。とすると、桑原武夫の『第二芸術』は、俳壇にとって、日本の文学・文芸の領域にとって、いかなる価値があったというのだろうか。金谷は窓の外のまだ散らずに揺れている百日紅を見ながら、好物のユーハイムのバームクーヘンにフォークを刺し、口に運んだ。 散りきれず十月の風百日紅 午後三時バームクーヘン何歳(いくつ)なり この文庫本『第二芸術』には、「第二芸術」をはじめ八本の小論文、「短歌の運命」「良寛について」「ものいいについて」「漢文必修などと」「みんなの日本語」「伝統」「日本文化の考え方」が集められており、桑原自身のまえがきと、多田道太郎の解説という構成になっている。本を開いてすぐ、金谷はその本が最安値であったことを了解する。それはいく箇所にも赤いボールペンで線が引かれていた。線はぶるぶるとふるえており、老人の形跡を感じた。その赤い線は「第二芸術」の章に限られていた。文章構成からいえば、すべて日本文化批判なのだから、読んでない訳もないだろうが。しかし、この中古の文庫本には思わぬ隠し物が畳まれていた。三枚の黄色くなった新聞の切り抜きである。 一枚は、一九八七年十月二八日夕刊の「文化勲章受章者の横顔」。草野心平、尾上松録らと並んで、桑原武夫の名前がある。もう一枚は、一九八八年四月十一日、「桑原武夫氏死去 新京都学派の基盤築く」の記事。共に、赤いボールペンで日付が記入されていた。その記事の下に大岡信の「折々のうた」があり、 ひっそりとまた死にゆくは何ならむ 春の嵐に耐えていたれば モーレンカンプふゆこ の短歌が紹介されている。桑原へのはなむけというには、あまりに苦節を詠んだささやかないのちの歌だけれど。文化勲章授章から半年である。もう一枚は、「評伝」というコーナーで、「先入観嫌う大知識人 学問的探検隊をリード」長井康平編集委員の記事。いつの物か、何新聞かもわからない。裏はラテ版で、TBSの夜九時の「女はいつも涙する・代議士の妻たち」の解説があるので、調べればわかるかも知れない。いずれにしてもこの文庫本の最初の持ち主は、恐らくは俳句に関心を持ち、あるいは書いていたのだろう。そして桑原の「第二芸術」に心を揺らす誠実な人であったのだと思う。 たとえば「そこで、私の希望する所は、成年者が俳句をたしなむのはもとより自由として、国民学校、中等学校の教育からは、江戸音曲と同じように、俳諧的なものをしめ出してもらいたい、という事である。俳句の自然観察を何か自然科学への手引きのごとく考えている人もあるが、それは近代科学の性格をまったく知らないからである。」というようなところに、赤い線は震えながら引かれている。この文庫本の持ち主はあるいは、国語の教師だったのかも知れないなと、金谷ケリーは思った。 教師引く消えざる赤きボールペン 赤い線震える憤怒あり文庫本 長井康平編集委員の「評伝」によれば、桑原武夫という人物は、父である桑原隲蔵(じつぞう)をひんぱんに訪ねてくる大学者たちに触発され素養を養ったという。幼年、「数学者を目指すが、京都一中時代に病気療養中にフランス文学を読みふけったことなどから専門にするようになった。京大卒業後、三年間フランスに留学。幅広い交友と京都のまち、漢籍、史学、西欧的教養から、独特の学風が生まれた。」とある。学者家系のボンボンで、フランス留学というのだから、ある人たちにとってはそれだけで、鼻持ちならない男だったのかもしれない。歯に衣を着せぬやんちゃなモダニストとして、日本文化批判、西欧近代主義の先鋒役として元気に動いた。 芸術の秋信ずればセーヌ河 ワインに酔い書籍の塵の黒死病 文庫本の初代所有者は、こんなところにも赤い線を引いている。 「しかし、菊作りを芸術ということは躊躇される。「芸」というがよい。しいて芸術の名を要求するならば、私は現代俳句を「第二芸術」と呼んで、他と区別するがよいと思う。第二芸術たる限り、もはや何のむつかしい理屈もいらぬわけである。俳句はかつての第一芸術であった芭蕉にかえれなどとはいわずに、むしろ率直にその慰戯性を自覚し、宗因にかえるべきである。」と書く。 また別の行に、 「かかるものは、他に職業を有する老人や病人が余技とし、消閑の具にするがふさわしい。しかしかかる慰戯を現代人が心魂打ちこむべき芸術と考えうるだろうか。小説や近代劇と同じように、これにも「芸術」という言葉を用いるのは言葉の乱用ではなかろうか。」と、断言している。 桑原武夫の言説は、そのまま現代の俳句の状況を予見しているようにも読める。「老人や病人が余技とし、消閑の具とし慰戯すること」とは、必ずしも外れた発言ではないだろう。 しかしこの文庫本『第二芸術』は初出より三〇年の歳月がたっている。まえがきでの桑原の論調も緩やかになっている。この文庫本がでる五年ほど前『流行言』という短文の採録のなかに、 「昭和二十二年ごろ、虚子の言葉というのが私の耳にとどいた―「第二芸術」といわれて俳人たちは憤慨してるが、自分らが始めたころは世間で俳句を芸術だと思っているものはなかった。せいぜい第二十芸術くらいのところか。十八級特進したんだから結構じゃないか。戦争中、文学報国会の京都集会での傍若無人の態度を思い出し、虚子とはいよいよ不適な人物だと思った。 数年後、ある会で西東三鬼さんに紹介された折り、あなたのおかげで戦後の俳句はよくなってきました、と改まって礼をいわれて恐縮したことがある。『第二芸術』については多くの反論をうけたが、今はほとんど忘れてしまって、虚子、三鬼両家のことしか思いだせない。まことに勝手なものである。」と述懐している。 秋青しことばのちから三十年 忘らばや今はむかしの風あらず キホーテよそれは風力発電という幻影 (つづく) |
03 初よりも二番手のすさまじき野分くる
隔月で発行している同人誌『トホホギス』の締め切りが迫っていた。以前、若者雑誌の編集をしていたという『トホホギス』編集人の朝洞怪海(あさぼらけかい)(みんなからはカイカイさんと呼ばれている)から、メールに再三の入稿請求が入っていた。鬱陶しいとも思うのだが、こんな催促がないと、俳句など本気で書くこともない。いや、本気かどうかは別として、俳句をやっている連中の多くは、けっこう閉め切り過ぎてドタバタと俳句を作る、実にいい加減なものなのではないだろうか。だからって、やらないよりはやっている方が、張り合いもあるし、面倒くさいがそれなりの面白さもある。こんな連中が多いから、俳句は今も、趣味の世界から、第二芸術のままでいるのだろうか。深夜、金谷が事務所でネットを覗いていると、桑原武夫の第二芸術論を、中川広という人物がこんなふうに紹介をしているのにぶつかった。 「日本の明治以来の小説がつまらない理由の一つは、作家の思想的社会的無自覚にあって、そうした安易な創作態度の有力なモデルとして俳諧があるだろうことは、すでに書き、また話した」の書き出しで始まる「第二芸術論・現代俳句について」は、昭和21年9月雑誌「世界」に発表された。虚子をはじめとした大家の「家元俳句」の実体を完膚なきまでに暴き、文学・芸術の足を引っ張る「俳句」の社会的悪影響を厳しく指摘し、それ以後、俳句は井戸端会議の世間話の断片と同様の「第二芸術」の印象が蔓延した。少し長くなるが、「第二芸術論」の要旨を引用したい。 「私は試みに次のようなものを拵えてみた。手許にある材料のうちから現代の名家と思われる十人の俳人の作品を一句ずつ選び、それに無名あるいは半無名の人々の句を五つまぜ、いずれも作者名が消してある。こういうものを材料にして、たとえばイギリスのリチャーズの行ったような実験を試みたならば、いろいろ面白い結果が得られるだろうが、私はただとりあえず同僚や学生など数人のインテリにこれを示して意見を求めたのみである。読者諸賢もどうか、ここでしばらく立ちどまり、次の十五句をよく読んだうえで」優劣の順位をつけ、どれが名家の誰の作品か推測を試みてもらいたいと、以下の15句を記した。 1 芽ぐむかと大きな幹を撫でながら 2 初蝶の吾を廻りていずこにか 3 咳くとポクリッとべートヴエンひゞく朝 4 粥腹のおぼつかなしや花の山 5 夕浪の刻みそめたる夕涼し 6 鯛敷やうねりの上の淡路島 7 爰に寝てゐましたといふ山吹生けてあるに泊り 8 麦踏むやつめたき風の日のつゞく 9 終戦の夜のあけしらむ天の川 10 椅子に在り冬日は燃えて近づき来 11 腰立てし焦土の麦に南風荒き 12 囀や風少しある峠道 13 防風のこゝ迄砂に埋もれしと 14 大揖斐の川面を打ちて氷雨かな 15 柿干して今日の独り居雲もなし 桑原武夫は言う。「これらの句を前に、芸術的感興をほとんど感じないばかりか、一種の苛立たしさの起こってくるのを禁じ得ない」と。「これらの句のあるものは理解できず、従って私の心の中で一つのまとまった形をとらぬからである。3・7・10・11・13などは、私にはまず言葉として何のことかわからない。私の質問した数人のインテリもよくわからぬという。これらが大家の作品だと知らなければ(草田男、井泉水、たかし、亜浪、虚子)、誰もこれを理解しようとする忍耐心が出ないのではなかろうか」「わかりやすいということが芸術品の価値を決定するものでは、もとよりないが、作品を通して作者の経験が鑑賞者のうちに再生産されるというものでなければ芸術の意味はない。現代俳句の芸術としてのこうした弱点をはっきり示す事実は、現代俳人の作品の鑑賞あるいは解釈というような文章や書物が、俳人が自己の句を解説したものをも含めて、はなはだ多く存在するという現象である。風俗や語法を異にする古い時代の作品についてなら、こういう手引きの必要も考えられぬことはないが、同じ時代に生きる同国人に対してこういうものが必要とされるということは、そして詩のパラフレーズという最も非芸術的な手段が取られているということは、よほど奇妙なことといわねばならない」と断じ、俳人の言葉遊びを痛撃した。 金谷は、ぼんやりとPCの画面を眼で追っていた。 面白くない人が一杯いるように、面白くない俳句も、もちろん一杯ある。有名俳人であってしかり、無名であればなおのことである。俳句はほとんど瓦礫の山なのだ。だからって、面白くないものばかり十五句上げて、それで俳句が芸術ではないと言っちゃあ、極端である。大人げない。この傑作の少なさこそ、かえって俳句の芸術性の高さを証明しているようなものでもある。芸術がエライという時代というのがあったのだろうが、イギリスのなにがしという人の実験も、随分いい加減なものだなあ。それにしても、これじゃあ、俺たちがクライアントをだますプレゼンと一緒だね、と、金谷ケリーは思った。 一度より二度熱き日や蝉時雨 二番目のおんなのにおい忘れ草 第一第二第三と倉庫の並ぶ炎天下 二階屋の窓のほかげのキャミソール 二度あれば三度目を待つ失楽園 初よりも二番手のすさまじき野分くる 二番煎じますます渋し鄙の茶屋 金谷ケリーは俳句を書くとき、よく、山本健吉の『定本 現代俳句』(角川選書)をペラペラとめくった。正岡子規から角川春樹まで人選と選句がずば抜けている。この類いの俳句鑑賞の本はほかにも割とよく読む。句集を手にしても、ほとんど頭に句が入らないのだ。あるいは、尾形仂・編『俳句の解釈と鑑賞事典』(旺文社)も手にする。季寄せや歳時記は見ない。これを見て書くと、どうしても俳句が、やらせ捏造ものになる。形式化する。類型化する。 山本健吉は桑原武夫の「俳句第二芸術論」に真っ向対峙した俳論の勇である。その山本の書を今読むと「挨拶と滑稽」を掲げる彼がいかに守旧派かがよくわかる。しかしその鑑賞力や、背景の読み取りの正確さは、金谷が読むたびに俳句の面白さを味わうことができた。尾形の『俳句の解釈と鑑賞事典』は、山崎宗鑑から始まり、芭蕉、蕪村、一茶から、現代俳人まで連なる大山脈を簡単に一望出来る。 こうして紙に水がしみ込むように、金谷の神経が俳句モードに変換するのをゆっくりと待つ。感情や、感想や、沢山のヒト・コト・モノのモチーフや、アイディアを、十七文字に圧縮する作業が始まる。やっと俳句モードになってきた金谷のPCに、メール受信のサインが入った。午前一時四十七分、こんな時間にメールなど、おバカな奴もいるものだと、開いてみると、清瀬春夏だった。 「今日、五室剛とデートしちゃったよ。ヤバくない?(笑)チョイ危なかったけどさ、一応テイソー守った。ケリーのためにじゃないよ、心配しないで。少しもったいぶったってところかな。素直じゃないね、やな女だね。(笑)ちょっと自己ギマン、肉マン、オレ、アゲマン! 酔ってねーよ、ちょいと飲んでるけどね。でもさ、思ってたより、五室ったら面白い奴だった。思ってたよりはね。デザインしろってさ、『万青』の。「マンセー」なんてアンニョンハセヨーっぽいよね。アンマン、アオマン、オレ、アゲマン! お笑いってさ、ひつこいほーがいいだってね。イチマン、ニマン、オレ、アゲマン! ヒャクマン、イチマン、オレ、サゲマン! ・・・なーんかねー、すぐ弱気になっちゃうのが、はるかチャンのよくないところだよねー。ケリーちゃんごめんね。愚痴っちゃったね。愚痴っちゃねーって! じまんたらりん、でもないけどね。俳句書いてる? いいの書いたらメールして、読むから。私、アンニョンハセヨーマンセーのデザインした方がいいのかな? 結構忙しいんだけどー。悩んじゃうよ。五室だしさー。相手が相手じゃない。ヤバくない、断るのって。どーしようー、わたしのケリーちゃま! うー、もうねるわ。」 金谷ケリーはこのメールを五回読んで、PCを閉じた。 (つづく) |
|
02 わが航海暗室の水を滑るかな 五室剛(ごしつごう)は『万青』の編集人をしている。大きな俳句結社はまず主宰者がいて、句誌発行の編集人が別に立つ。編集人は、投句を選考したり、特集を考えたりといった編集能力もさることながら、結社をまとめるリーダーシップも求められる。大きな結社になれば、地域ごとの句会などもあり、主宰者の代理で句会に出ることもある。しかも五室はJ大学病院に勤める医師で、咽喉科を専門としていた。相当多忙なはずである。水原秋櫻子はじめ、軽部烏頭子、高野素十、中村若沙、吉川春藻、近くは五島高資と、医師で俳人であることも少なくない。五室は、医大生の時に「暗室の水音」という寺山修司の俳句の評論で『俳句海』の論文新人賞を受賞した。五室剛はその時使ったペンネームである。津軽弁では五七五が、「ごすつごう」になるからだという。東京生まれの男としては、イヤミな筆名の選択である。
暗室より水の音する母の情事 母を消す火事の中なる鏡台に 母恋し鍛冶屋にあかき鉄仮面 母とわが髪からみあう秋の櫛 いずれも、昭和五十年(一九七五)に発行された寺山修司最初の句集『花粉航海』に出てくる作品である。この『花粉航海』は、十代の寺山作品とされていたが、その後の研究で半数ほどが、底本としている『わが金枝篇』や、『わが高校時代の犯罪』を編んだ三十代半ばの作であることがほぼ確実なものとなった。掲上句四句はすべて三十代の作品である。 五室の論文は俳句を通して、少年時代の寺山と母親との異常な母子愛を解析したものであるが、もしそれが、十代の作品だけではなく、三十代の作品を含むとなると、事情はかなり変わってくる。十代の作品の中に紛れ込ませた自己模倣、自己客観、自己劇化の仕掛けが入るわけだから、さらにねじれ構造で虚構化した母子関係と読めるはずなのだ。とはいうものの、五室剛の論文は、若々しいひらめきに満ちた佳作であった。 闇にふる花粉白衣の手を汚す わが航海暗室の水を滑るかな 軒渡る雨の津軽やつばくらめ 夏帽子書斎の犀を幻想し 五室の医大生時代の作品である。明らかに寺山修司の影響を受けている。 見れば座敷の奥にうずくまるようにして蕎麦をすする五室の姿があった。金谷ケリーはさけるようにして、座敷の反対側に清瀬春夏を伴って入った。すぐに蕎麦と酒が運ばれてくる。春夏が酒の銘柄を訊ねると作務衣のような仕事着を着た若い女性が「浦霞です」と答える。「わお!」小皿にのったコップになみなみと注いである。常温だ。口からコップに近づく。春夏はすかさず詠む。 菜の花や霞ヶ浦の飛行船 蕎麦の粉を香ばしく延ぶたなごころ 「浦霞は宮城県、霞ヶ浦は茨城県」「そんなに離れてないわ」「それに、野ブタな心、というのも奇妙なものだね」「またすぐ、そのような冷やかしを」「冷やよりやっぱり常温酒」「もー、どこまで突っ込むの!」「どこなりと、お望みのところを」「やらしい」金谷と春夏がこの日の趣向を喜んでいる時に、風月亭花鳥が濃茶の座布団の上に、鶯色の羽織の裾をひらりとひるがえして座ろうとしていた。 「なんの花や築地は東本願寺、はい、お葬式に大変よい季節になってまいりました。お葬式と申しましたらなんといっても菊の花、夏目漱石も『有る程の菊抛げ入れよ棺の中』と詠んでおりますとおり、明治時代まではみなさん秋に亡くなっておりました。ところが、漱石さんが菊の花を使い過ぎてしまいまして、棺に入れる菊がない。『すみません、菊の花が咲くまで、ちょっとお待ち願えますか』と、葬儀屋。『えー、棺にしてよ! いや、堪忍してよ』というわけで、それからはみなさん、いつお亡くなりになってもよいということになりまして、はい。太宰治はさくらんぼ飾って桜桃忌、司馬遼太郎は菜の花がお好きだというので菜の花忌、芥川龍之介は河童忌ということで、祭壇にはレインコートがズラーッと並んでおります。それじゃー私もと、日本中の課長さんを集めまして、花鳥忌・・・」 こんな枕から、フグにあたって死んだ男の葬儀の噺「らくだ」にするりと入っていく。金谷の二句。 雨具着て水洟垂れる河童の忌 河豚喰って死んだららくだ常温酒 「らくだ」が終わると中入り。金谷ケリーと清瀬春夏は酒と板わさ、出し巻き玉子を注文する。 漱石の「有る程の―」の句に話を戻す。明治四三年(一九一〇)胃潰瘍で修善寺に療養中大吐血し、生死の境をさまよった漱石ではあったが、奇跡的に生還し東京に帰っての静養中、友人で美学者の大塚保治の妻、楠緒子の死を知る。歌人で小説も書いた楠緒子(くすおこ)に漱石は恋慕の情を抱いていた。漱石の悲しみはひとしおだった。病床でこの句を書く。最初「棺(ひつぎ)には菊抛げ入れよ有らん程」と書かれたが改作する。ずっとよくなった。修善寺での一句に「腸(はらわた)に春滴るや粥の味」がある。胃潰瘍のはらわたが熱い粥を吸収していく感覚。大病を経験しての楠緒子の死は、漱石にとってひとしおのものがあったことだろう。 白菊の目にたてゝ見る塵もなし 松尾芭蕉 白菊や呉山の雪を笠の下 与謝蕪村 しらぎくの夕影ふくみそめしかな 久保田万太郎 しらぎくのあしたゆふべに古色あり 飯田蛇笏 菊白く死の髪豊かなるかなし 橋本多佳子 多佳子の一句は、手向けの白菊に隠れそうにある棺の中の女性の髪の量に、生の生なましさを圧倒されている。白菊はやはり死の匂いがする。 金谷の一句は、芥川龍之介の「洟水や鼻の先だけ暮れ残る」を前提としたものだ。『鼻』の作家である芥川の大正八、九年(一九一九—一〇)頃の作と推定されている。この句には「自嘲」という前書がついており、自死する前にたびたび揮毫したという。しかしシュールな句である。洟水を垂らした鼻先だけが生き残っているとでも言っているのだろうか。 それにしても、風月亭花鳥の菊の花の枕はいささか大げさだが、俳句をたしなむ噺家らしい趣向だ。こうした誇張や、肥大した誤解こそが笑いの源泉であることは言うまでもない。店がざわめいているなか出囃子が流れ、二席目が始まる。 「それではお客様からお題をいただきまして、わたくしが出来ますものがありましたら、一席お伺いを」と言うと、「時そば」という声が上がった。花鳥は「そうですね、SOVASOVAですから、それもよろしいかと思いますが、ほかに」というと、「芝浜」という声。五室剛だ。「今日はお客様、お酒も入っておりますし、それでは『芝浜』を一席・・・」花鳥も五室にはいささか気を配っているようである。 少し注釈。八木忠栄著『落語はライブで聴こう』(新書館刊)は、金原亭世之介の項で「芝浜」に触れている。「商いに身の入らない勝五郎、昨夜も酒を飲んで寝込んだ。どうしても河岸へ商いに出かけたくない勝五郎を、しっかり者の女房が叩き起こす」時間を一時(いっとき)程も早く間違えて、芝の浜にくるとそこで四十二両の入った財布を拾ってしまう。こうなればもう河岸どころではない。女房に事情を話してから仲間を呼んでの大騒ぎ。深酔いの翌朝、けれども女房は「あんた、夢でも見たのと違うかい」と拾った金のことは白を切る。勝五郎は悄然とするが心を入れ替えて仕事に精進。やがて三年目に拾った金が返ってくる。事情を女房から聞いた勝五郎は、女房に「よーくがんばりましたね」と、酒をすすめられるが、酒を断っている勝五郎は飲みたさをこらえてきっぱりという。「また夢になるといけねえ」 忠栄は現代詩花椿賞を獲る詩人でありながら俳句をよくする。しかも大変な落語狂である。俳号、蝉息(喘息が持病である)、ブセオ。世之介の俳号は皀角子(甲虫が好きだった)という。二人ともかいぶつ句会の同人。 芝浜の泥酔に消ゆ四十二両 ありやなしや夢のまた夢酒はさけ 席が終わるとそのまま客が残って二次会となった。金谷と春夏が、「じゃあもう一杯」と注文しているところに、ぬっと五室剛が来る。 「金谷さん、お連れさんを紹介してください」単刀直入である。「清瀬春夏さん、大学の同級で、彼女も俳句をやっています。こちら『万青』の五室剛さん」「よろしく」「どちらの結社ですか」「いえ、デザイン学校の仲間達のほんのお遊びです」と春夏。「そうでもない。私よりもずっといい」と金谷。「それなら、すごいじゃないですか。あ、僕もお酒」と五室。 「それにしてもあの『堂々たる胴、なんていってられないメタボ腹』は、金谷さんでしょ。うまい、さすがです」と、五室。金谷の作ったダイエット食品のコピーに触れる。五室は広告業界誌『アドヴァ』に「コトバ力」という連載を書いている。その雑誌に金谷のコピーが取り上げられたのだ。「どうも」と、金谷は応えたものの、五室のこうした発言が社交辞令であることを感知している。五室は広告のコピーに批判的な論評が多いからだ。 「『万青』は大きな結社ですから、編集のお仕事も大変なんでしょ」と春夏が投げかけると、「ええ、医者をやりながらですからね、正直、大変です。そうそう清瀬さん、デザインのお力を貸してはいただけませんか。句誌というのはデザインがおざなりで、どうもいけません。それにあなたの俳句も拝見したい」「そんな! でも、デザインはお手伝いできるかも」と、春夏はうれしそうに応える。金谷は、春夏とは何もないのだけど、軽い嫉妬心を覚える。この冷え性のエックス脚女! と、心の奥で叫ぶ。 エックス脚尻軽ろき跳ね花見酒 どこまでもほんとうのなき春の酔い コピー書きに俳句ごころもおぼろなり さみだれに乱れる花や闇の花 見つめられて乳首も固き春の宵 さすがさすが俳人の背に春の匂い
三人の暗黙の句会が繰り広げられる。そこに、SOVASOVAの亭主陳蕎麦(ひねそば)ずるると、風月亭花鳥がやってきた。 「いやあ、芝浜はさすがでした。それに今日の一席目の枕は秀逸、漱石が出てくるとは感嘆ものです」「五室さんがいらしてるので、緊張しましたよ」「それは申し訳ありません」「五室さん、蕎麦のお替わりは?」「ではもう一枚」陳蕎麦ずるるも気を使う。「それにしても花鳥さんたちの『トホホギス』は面白い人が集まってる。ずるるさん、ケリーさん、女優の地遊りつさん、画家の棟方ゴッホさん、それから・・・」「よくご存知で」「羨ましい、『万青』にもこうしたにぎやかな方がほんとに欲しい。いかがですか、『万青』にも加わっていただけませんか」「いやいや、私たちの句会は洒落ですから。それにそんなことになったら、吸収合併されてしまいます」と、ずるる。「洒落が欲しいんです。それでは春夏さんだけでも『万青』に、いらっしゃいませんか」「えー、だって私がどんなの書くか、ご存知ないじゃありませんか」にやりと笑って五室が答える。「いえ、お顔を拝見すればわかります、その人の俳句が」「ほんとですか?」春夏の顔が一瞬明るく輝いた。 (つづく) |
月は公園の池の東側にある動物園の森の上に、肌色にぼんやりと昇り出していた。菜の花はここからは見ることがない。ほとんど満月である。午後五時を回ったというのに空はまだ明るい。緑色に塗られた木製のベンチで、冷めかけたあったかい伊藤園のおーいお茶のペットボトルのキャップをひねり一口飲む。 「月は東に、か」男はぽつりとつぶやいた。説明するまでもない、安永三年(一七七四)蕪村の名句。いかにも画家の蕪村らしい屏風絵を思わせるパノラミックな俳句である。しかも「菜の花や月は東に日は西に」と、漢字とかながきれいに交互に並んでいる。書にしても特別の面白さがあるはずだ。 突然、野鴨が三度ほど池の暗がりで水面をたたいた。 ジャバザバダ月したたりし野鴨かな 水音が消えると、一層のこと公園が静かになったように思えた。 「古池や蛙(かわず)飛び込む水の音」というのがこれである。わずかな水音がして、初めてあたりの静けさを知る。芭蕉の詠んだ古池は、深川芭蕉庵の近く、芭蕉の高弟にしてパトロンだった杉山杉風(さんぷう)が魚を囲っていた場所だという。貞享三年(一六八六)閏三月、この句は最初「古池や」ではなく、「山吹や」と詠まれていたというから、晩春の頃と判断してよい。いまでいう五月初旬。それにしても「山吹や」だったら、名句として残らなかっただろう。さすが、当たり前過ぎるようにも思える「古池や」に推敲した芭蕉が偉い。 しかし、オノマトペ(擬声語)のジャバザバダは11PMのテーマソングのシャバダバダのパクリみたいだし、野鴨の羽音で月が濡れるというのも少々大げさである。「まだまだだなあ」金谷ケリーはもう一口おーいお茶を飲んだ。金谷がサントリーの伊右衛門や、アサヒ飲料の新撰十六茶ではなく、おーいお茶を飲むのは、伊藤園が俳句に協力的な企業だからだ。歳の離れた弟が、「キリストも生きていたなら二千歳」という作品で、伊藤園の俳句公募の佳作に入った。その頃、金谷は俳句にまったく興味を持っていなかったから、弟の作品を鼻で笑った。もちろん弟はもう俳句を書いていない。 古池やかわずにかえる草団子 金谷ケリーは一応俳人である。俳人には、「一応」の人が多かった。俳句をやる人のほとんどは俳句では喰えない。必然、ほかの仕事を持っている。金谷は広告プロダクションに勤めていた。大学ではデザインの勉強をしていたのだけど、職場に入ると、企画や、コピーライターの腕を買われて、移動した。そのうち広告の仕事で知り合った噺家の風月亭花鳥に「ケリーさん、君コピーがうまいんだから、俳句なんざ簡単ですよ」と誘われて、句会に出るようになった。そんなに面白いとも思わなかったが、つまらないとも思わなかった。そのまま続けているが、金谷は自分を俳人とは思っていない。コピーのように俳句が出来るのを時々うんざりしていたし、俳句はコピーではないとも考えていた。いや、俳句は世界を言葉でコピーするものとも考えていたから、自分は「俳句を作る人」程度には思っている。桜の咲く予告編、辛夷が巨大な綿菓子のように公園の薄暗闇に数本立っていた。 吾はたれの予告編やら辛夷咲く やわらかい白い辛夷を握る闇 金谷は俳句に闇を使うのが好きだ。白と闇の対比。あるいはアンニュイ、トワイライトゾーン、形の見えづらい曖昧な領域への誘惑。これはニュアンスのごまかしにもなる。辛夷と拳のダブルイメージも新鮮味がない。しかし白い辛夷の花をそっと握りしめる感触は、悪くないと思った。ドラえもんのテーマの着メロが鳴った。金谷は子供の頃からドラえもんが好きだった。「どこにいるの?」「ああ、雷橋のところ」橋は、雷のようにジグザグに曲がっていた。「わかった」 清瀬春夏(きよせはるか)のケータイにはピンクのラメが鱗のようにびっしりと貼ってある。そのざらざらした感触を楽しむようにケータイを握ったまま、春夏は雷橋の方に急いだ。 ケータイのラメの寒さよ白き爪 花冷えのエックス脚がきたりけり マッキントッシュのゴワッとした細身のコートを羽織り、大股に歩く伸びやかな脚が、しかしエックス脚だった。惜しい! 胸も大きいのに、エックス脚だった。しかも花冷えのこの夕暮れ時に、そのエックス脚はひときわ寒そうに見えた。よく女性がトイレに行きたくなるとエックス脚のポーズをとるが、清瀬春夏はいつもそうだ。それが悲惨にもブリッ子的可愛ゆさにも見える。いやそれとも本当にトイレへ行きたかったのだろうか。エックス脚ときたりけりの取り合わせが滅茶苦茶でいいなと思った。 「何考えているの?」「決まってるじゃないか、世界のことさ」「えらそうに」「偉くない人が、世界のことを考えてはいけないのかい」「さあ、そういえばそうかも」「冗談だよ、君の歩いてくる姿のことを考えていたの」「私、歩き方下手だから」「いや、支那のお姫様のようだと思って眺めていた」「どういうこと?」「ほら、大切な姫が逃げ出さないように、纏足とやらの小さな緞子の靴を履かされて、世界を小さくさせられる」「ふうん、靴で世界を縮められるんだ。で、ケリーは、私が小さな世界に生んでいると思ってるわけ?」「そんなことは、思ってないけど」「でもさあ、たとえば私にはどのくらいの小ささが似合うと思う?」「ウォーターボールくらいの小ささはどうだい」「三分で退屈しそう」「クリオネくらいの小ささになれば、もう少し持つかも知れない」「いずれにしても、窒息死してしまうわ」 緞子の靴で巡る小さき世界桃香る 塔もある椰子もある星満天の水の球 クリオネほどの小さきいのちガラス球 セールで買ったフェラガモの靴を履いている清瀬春夏は、ずいぶん俳句を読んでいた。一句は夏目漱石の「菫程の小さき人に生まれたし」の句を思い出しながらまとめている。時として俳句の本歌取りは、研鑽を積んだ老獪な作家にも思われ推奨される。西に傾いていた日の光はもうまったく隠れて、水銀灯の明りが広がり出していた。 春夏は金谷とは美術大学の同級生で、今勤めているデザイン専門学校の老教授が俳句をやっていて、ほとんど無理やり句会に引っ張り込まれた。 「君の親御さんは俳句をやってましたか?」「いえ、ないと思います」「そうかなあ。おかしいなあ。しかしともかく君は、俳句をやる運命を持った人です」老教授はきっぱりといった。「そんな」「いや、まず、清瀬という苗字だけど、これは俳句の季語を分類して、その作例を鑑賞学習する本のことを季寄せというんだ」「はあ」「それから春夏という名前」「私、五月四日生まれで、立夏の二日前だったものですから、春と夏の間の子というわけで」「季寄せは一冊物と、二分冊物と、四分冊物がある。二分冊物は春夏の部、秋冬の部に分かれている。君はそれだ!」 春夏はファッション・コレクションみたいだと思った。老教授は懲りもせず、研究室の本棚から葉書ほどの小ささの布装丁の本をさっと取り出した。「あげよう!」春夏の鼻先にそれを突き出した。『季寄せ 上 春夏 山本健吉編』と書いてある。「なにこれ! 確かに私かも・・・」それは細かい活字で雨粒のように組まれていた。 四季を編む活字の行に春の雨 清瀬春夏の名前と俳句の関係に触れたついでに、金谷ケリーについても少し語っておく。金谷の父親は、社会人サッカーのクラブメンバーだった。三〇代半ばまでゲームに出ていたその頃、金谷は生まれた。本名、蹴(しゅう)。もちろん蹴球の蹴をとっている。弟は球。男なら「きゅう」、女なら「たま」と読ませるつもりで決めていた。親の夢で蹴も地元の少年サッカーチームに入る。ディフェンダーのポジションにいた。中学になって、仲間が蹴の字を「ける」と読めるようになると、金谷のニックネームが「ケリー」に定まった。 初めての句会に向う道すがらで、風月亭花鳥はいった。「ケリーさん、君は凄いんだよ! 俳句の世界では切れとか、切れ字というんだけど、つまり短い言葉を有効活用するために、言葉を切る、そんな手法があってね。かな、や、けり、というのはその代表的な切れ字なんだ。いや、お尻のほうの切れ痔とは違うの。そんなわけで、君は俳句をやる宿命があるんだ」「はあ」「もっとも、最近は切れ字を使うと古臭い俳句に見えるし、守旧派なぞといわれてね。私は子宮派だけど、いやいや、あまり使われなくなってはいるんだ」「じゃあ、廃棄物寸前の名前ってわけですか」「そんなこといったら、噺家だって、今はブームだなんていわれてるけど、世界遺産にもなれない悲しい古物ですよ。ともかくそんなわけで、君の名前は俳句作りにとって、とても重要だったんだ。それだけでも君が俳句をやる十分な理由になる」「そんなもんですか」 かなやけり切れ三態の輝けり
蕎麦すする音や春めく月まどか 一合の酒一会の噺月一夜 風月亭花鳥は、SOVASOVAのオーナー陳蕎麦(ひねそば)ずるる(彼も俳人だった)と受付に立ち、客一人一人を迎えている。花鳥は金谷の連れて行った春夏を見るとすぐに、眉毛をピクリとあげ目をのの字にして「素っ敵ですねー!」と感嘆の声を上げた。春夏もまんざらではない。すると花鳥は追いかけるようにして、「『万青』の編集人の五室剛(ごしつごう)さんが来てますよ」という。金谷の眉間が曇った。 (つづく) |